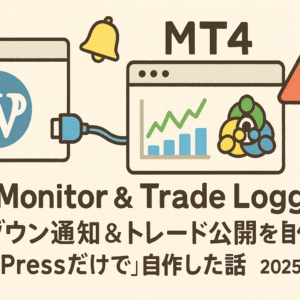「まず、稼いでから使え」という感覚って、単なる“倹約”以上に、いくつかの心理や文化が混ざっています。ざっくり分解するとこんな感じです。
「お金を使う資格」は“十分に稼いだ人だけ”という価値観
- 「ちゃんと稼いでいないのに、贅沢するのは後ろめたい」
- 「まだ年収も貯金も大したことないのに、新しいPCや趣味にお金を使うのは甘え」
こういう「自己採点」が頭の中にあって、
“合格ライン(年収・貯金額)に達してからじゃないと使う資格がない”
と無意識に思っているパターンです。
裏側には、
- 自己肯定感の低さ(「稼いでない自分には価値がない」)
- 「楽しみ=ご褒美」「ご褒美をもらうには、まずガマンと成果」
という条件付きの自己承認があります。
昭和〜平成初期までの「家族を養う男」ロールの残り香
日本の男性に多い理由として大きいのがこれです。
- 「男は稼いでなんぼ」
- 「家庭を守る・支えるのが男の役目」
- 「浪費する男=ダメ親父」
という昭和の“理想像”が、親世代・祖父世代から
メッセージや空気として刷り込まれていることが多いです。
その結果、
- 自分の趣味・自己投資 < 家族のための貯金・住宅ローン返済
- まず貯蓄力・安定収入を固めないと“男として一人前じゃない”
という、「使う前にまず稼いで、家計を固めるべき」という思考になりがちです。
借金・リスクへの過剰な恐怖(失敗したら終わり思考)
「使ってから稼ぐ(ローン・先行投資)」に対する強い抵抗も関係します。
- 借金=絶対悪、人生終わり
- 失敗したら取り返せない、恥ずかしい
- 一度コケたら再起が難しい社会だ、という感覚
日本は「失敗に厳しい社会」だと感じている人が多く、
「先に使って失敗したら…」という恐怖が、行動を止めてしまう。
だから、
- 「リスクを取るくらいなら、まず安全圏まで貯める」
- 「生活防衛資金」「老後資金」ができるまで、あまり使いたくない
という強い防御モードになりやすいです。
「ガマン=美徳」「楽しみは後回し」の教育
日本の学校・家庭では、
- 我慢強い子=褒められる
- 自分の欲を抑える=大人
- 「遊ぶ前に勉強」「楽しみは最後に取っておけ」
という刷り込みがとても多いです。
これが大人になっても形を変えて残っていて、
- 「まず死ぬほど働いて、結果を出してから遊べ」
- 「今から使うのではなく、目標達成後にドカンと使う」
という、“楽しみは常に後回し” ループになってしまうことがあります。
デフレ時代と「貯金信仰」の影響
平成の長いデフレ&不景気の中で、
- 「給料は増えないけどモノはそこそこ買える」
- 「だから使うより、貯金しておくのが正解」
という貯金正義の空気がすごく強かった時代があります。
- 投資=怖い、ギャンブル
- 先行投資・自己投資よりも、とにかく現金を残すことが安心
この空気の延長で、
「まず稼いでから。それまではあまりお金を動かさない」
というスタイルになっている人も多いです。
メリットとデメリット
メリット
- 借金地獄・浪費癖になりにくい
- 家計が破綻しにくい
- 長期的な安定を作りやすい(貯蓄・保険など)
デメリット
- 自己投資・チャレンジのタイミングを逃しやすい
(「もう少し貯まったら」が永遠に続く) - 「稼げてない自分には価値がない」という自己否定につながる
- 人生の“楽しい部分”を、先送りしすぎて消耗しがち
もしこの感覚を少しゆるめたいなら、
- 「全部“稼いでから”じゃなくて、“一部は先に使ってもいい”」
- 「将来のため+今の自分のため、のバランスを決める」
- 「自己投資(スキル・健康・人間関係)は、むしろ先に少し使ったほうが“稼ぎやすくなる”」
みたいな発想に少しずつ書き換えていくと、
“真面目さ”はそのままに、だいぶ動きやすくなります。
デフレと「1円でも安いもの」心理
デフレだと、“今使うより、あとで使うほうが得”に感じる
デフレ=物価が下がりがちな状態なので、
- 「今より将来の方が安く買えるかも」
- 「だから今はなるべく出費を抑えよう」
という支出ガマンモードが合理的になってしまいます。
そこに、
- 給料が上がらない(もしくは下がる・ボーナス減)
- 将来も不安(年金・雇用不安)
が重なると、
「とにかく安く」「少しでも出費を減らす」ことが防衛本能レベルになるんですよね。
デフレ期間が長かったことで、“安さ探し”が習慣化
日本は90年代後半〜2010年代くらいまで、長期のデフレ~低インフレでした。
その間に、
- ドラッグストア・ディスカウントストアの価格競争
- 「底値をチェック」「チラシ比較」「ポイント還元」
- クーポン、特売、100均文化
などが生活の標準装備になったので、
「少しでも安く買える店を探すのが当たり前」
「定価で買うのは損」
という感覚が、かなり強く染み込んでいます。
これは
“生活を守るための合理的な戦略”が、そのまま価値観レベルに固定された
という側面があります。
「資本(株式)を持ちたがらない」心理との関係
デフレ環境では「現金>株式」になりやすい
インフレが強い国だと、
- 現金のままだと価値が目減りする
- だから株式・不動産など“実物・資本”を持つ方が有利
という感覚が生まれやすいんですが、
日本は長い間、
- 物価があまり上がらない
- むしろ物やサービスが「安くなっていく」イメージ
- 金利もずっと低い
だったので、多くの人にとっては
「現金で持っておいて、必要な時に安くなったモノを買えれば十分」
という“現金信仰”が合理的に見えてしまったんです。
バブル崩壊のトラウマ × デフレで、株=危険という刷り込み
- 80年代バブル → 株・不動産バブル崩壊
- 「株で人生壊れた人」のストーリーが大量に共有される
- 親世代・メディアが「株=危ない」「投資=ギャンブル」と教える
こうした背景に、
その後のデフレ・不景気が長引いたことで、
- 「せっかく貯めたお金をリスク資産に突っ込むなんて、正気じゃない」
- 「株なんてプロがやるもので、一般人が手を出したらやられる」
というイメージが固定されていきました。
つまり、
・バブル崩壊の恐怖体験(自分 or 周囲 or メディア経由)
・その後も景気がパッとせず、給料も伸びない
・だからこそ、減る可能性のある投資なんて怖くて仕方ない
という流れです。
「安さ至上主義」と「資本を持たない」がセットになりやすい理由
これ、実は同じ根っこから出てます。
根っこにあるのは「守りに徹するマインド」
- 攻めより守りを重視
- お金は「増やすもの」より「減らさないもの」
- 「失敗したくない」「損したくない」が超強い
だから行動パターンとしては、
- 支出 → とにかく削る、安くする、我慢する
- 資産運用 → とにかくリスクを取りたくない、元本割れが怖い
という“徹底防御型”のマネー行動になりやすい。
デフレと低成長が長く続いたことで、
「頑張ってもそんなに増えない世界」
「だから、とにかく減らさないようにするしかない世界」
という前提で考えるクセができてしまったとも言えます。
じゃあ全部デフレのせいかというと…
完全にデフレだけのせい、ではなくて、
- もともとの文化:
- 貯金好き
- 借金嫌い
- 失敗に厳しい社会
- 歴史的イベント:
- バブル崩壊
- 銀行・証券への不信
- 政策・制度:
- 金融教育ほぼなし
- 投資より貯蓄を推奨してきた時代が長い
- そこに デフレ+低成長が長期で追い打ち
という複合技で、「安く買う・現金で持つ」が最適解っぽく見える世界観が固定された、という感じです。
もしこのマインドを少し変えたいなら
ここからは“自分の行動を変えるなら”という話ですが、
- 「1円安い」より「1%成長する資本」を持つ発想に慣れる
- 生活防衛資金までは徹底防御、それを超えた分は“攻め枠”と割り切る
- 「完全に安全なお金」と「リスクを取って増やすお金」を分けて考える
- 「失敗=終わり」じゃなくて、「小さい失敗をたくさんやって慣れる」方針に切り替える
みたいな感じで、
“一部だけでも攻めのマインドを許可する”のが現実的なスタートかなと思います。