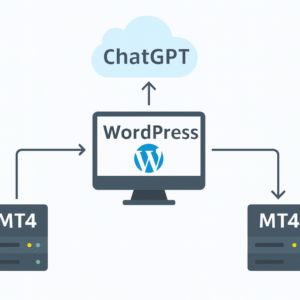「1円でも安く」のその先にあるもの
ここ30年くらい、日本の空気ってずっとこんな感じでしたよね。
- 少しでも安いスーパー
- 少しでも安い格安SIM
- 少しでも安い電気・ガス
「同じものなら1円でも安い方がいい」──これは家計を守るためには、ある意味すごくまっとうです。
ただ、結果として日本は「失われた20年/30年」と呼ばれる長期停滞と、実質賃金のマイナス成長を経験してきました。1990年代以降、物価がほとんど上がらず、むしろ下がりがちな“デフレ”の中で、実質賃金は長期的に低下し、1990年代後半と比べて2020年代までに実質賃金が1割前後下がったとされます。
経産省の報告でも、この約30年を通じて、
「将来に対する悲観と“デフレマインド”が日本社会に広がった」
と指摘されています。
「安くしないと売れない → 企業は人件費を削る → 賃金が上がらない → みんなもっと安さを求める」
このループが、結果的に「20年以上のデフレ」を招いた側面は、やっぱり否定しづらいところです。
デジタル赤字 ― クリックするたびに海外へ流れていくお金
もうひとつ、最近はっきりしてきたのが「デジタル赤字」です。
- 動画配信
- アプリストア
- クラウド
- 広告プラットフォーム
- サブスク系サービス…
これらの多くは GAFA など海外企業のサービスで、日本から支払われたお金がそのまま海外の売上・利益になります。
政府の統計によると、日本のデジタルサービスの貿易収支は2024年に約6.65兆円の赤字で過去最大、2014年比で3倍以上に膨らんでいます。
2025年上期だけ見ても、デジタルサービスの赤字は約3.5兆円規模に達していて、日本のデジタル基盤がどれだけ海外依存かが数字で分かるレベルです。
- 僕らは毎日スマホを触り、
- 課金し、広告を見て、サブスクを払い、
- そのかなりの部分が「海外プラットフォームの売上」になっていく。
これはある種の「デジタル経常赤字」=デジタル赤字とも言えます。
「国産SNS」と共創資本主義の芽
とはいえ、この流れに対してカウンターの芽も出てきています。
たとえば日本発の分散型SNS Misskey。
日本人エンジニアによって開発されたオープンソースのSNSで、ActivityPub対応の「国産SNS」として、X(旧Twitter)の代替候補にまで名前が挙がるようになりました。
- ソフトはオープンソース
- サーバーはコミュニティや個人が運営
- ユーザー同士が「場」を育てていく
という構造自体が、「みんなでサービスを作る・支える」という 共創的な資本主義のミニチュア版のようなものです。
最近は Misskey や mixi2、Wick のような「国産SNS」も話題に上り、
「全部ビッグテックに握られている構図、ちょっとキツくない?」
という違和感を持つ人もじわじわ増えています。
「本気で戦争を終わらせる男」がやっていること
ここで出てくるのが、
本気で世界平和について発信し続けている男・前澤友作です。
前澤さんは
- noteで「世の中からお金をなくすことで世界は平和になる」といった構想を語り
- 国際平和デーには「投資先は、世界平和。」という日本経済新聞1面広告でメッセージを出し
- 以前から「戦争反対」を掲げたTシャツを着た写真をSNSで何度も再掲している人でもあります。
もちろん「戦争を一人で終わらせる」なんてことは現実的ではありません。
ただ、お金の循環と平和を結びつけて、真面目に議論の土台に乗せている数少ないプレイヤーであることは確かです。
そんな前澤さんが、
「お金配りはもうやめた。これからは未来につながる“株配り”」
と言って立ち上げた会社が 株式会社カブ&ピース(KABU&PEACE Inc.)。
ここで掲げているスローガンが、
「目指せ、国民総株主。資本主義を民主化しよう。」
です。
国民総株主という発想 ― みんなで発電、みんなで販売
カブ&ピースが運営するサービス「カブアンド(KABU&)」では、
- 電気
- ガス
- モバイル
- ひかり回線
- ウォーターサーバー など
日常のインフラをカブアンド経由で契約すると、利用料金に応じて「株引換券」がたまる仕組みになっています。
この株引換券は、
- 1枚=1円相当
- 一定条件のもとでカブ&ピースの種類株式に交換可能
- あるいは割引券としても使える
という形で、ポイントではなく「資本」そのものへの入り口になっています。
ここで重要なのは、
「電気代を払って終わり」
から
「電気代を払うことで、その会社の株主にもなっていく」
という構図の変化です。
- みんなで電気を使い
- みんなでその会社の株を持ち
- 利益が出れば、みんなにも配当や株価上昇という形で跳ね返ってくる
これはまさに「みんなで発電」「みんなで販売者」「みんなでオーナー」という状態です。
なぜ「最安じゃない」のに意味があるのか
正直に言ってしまえば、
こうした「株がもらえるインフラサービス」は、料金だけで見ると“業界最安”ではないケースも普通にあります。
では、なぜそれでも契約する意味があるのか。
それは、支払い方を変えると、お金の“行き先”が変わるからです。
① 「支払い」がそのまま“自分の資本”になる
これまで:
- 電気料金 → 大手電力 or 新電力の売上
- 通信費 → キャリアや海外プラットフォームの売上
で終わりでした。
これから:
- 電気料金 → その一部が自分の持ち株として蓄積される
- 通信費 → その一部が自分の将来キャッシュフローのタネになる
という「モードチェンジ」が起きます。
もちろん企業がうまくいかなければ株は下がるし、リスクもあります。
でも、
同じ生活費を払うなら、
「一方的に払うだけ」より
「自分も資本側に少しずつ近づく」
という構図の方が、長期的には合理的じゃないか?という問いかけです。
② 「1円でも安い」から、「誰を太らせたいか」にシフトする
これからの選び方は、こういう感じでいいのかもしれません。
- A社:月額 3,000円(最安クラス)
- B社:月額 3,200円(ちょい割高)だけど、
- 利用額の1〜2%が株(or持分)になる
- 利益が出れば配当や値上がりの可能性
- 利用者=株主としてサービスづくりに参加できる
差額200円をどう見るかです。
- 単純な節約の世界観:
→ 「200円でも安い方がいい。A社一択」 - 共創資本主義の世界観:
→ 「200円多く払っても、B社と一緒に“自分たちの経済圏”を育てる方が面白いし、長期リターンも期待できる」
正解は人それぞれですが、
選択肢の軸が「値段だけ」から「価値観・資本・参加感」に増えること自体が、デフレ脱却の一歩になります。
③ 「みんなで販売者」になることで、広告費の流れも変わる
カブアンドモバイルのような構想を考えるなら、
「みんなで販売者」モデルは相性がいいです。
- 友だち・フォロワーに紹介する
- その人が契約すると、自分にも株引換券 or 手数料 orポイント
- さらにその人もまた紹介者になれる
こうすると、
- 従来:広告費の多くが Google / Meta などに流れる
- これから:広告費の一部がユーザー・コミュニティに還元される
という構図に変えられます。
「みんなで販売者」=紹介報酬の民主化とも言えますし、
「デジタル赤字の一部を取り返す仕組み」とも言えます。
④ 国産SNS × みんなで発電 × みんなで販売 という組み合わせ
想像してみてください。
- 情報発信の拠点は、Misskey などの国産SNS/分散SNS
- コミュニティで「この電気・モバイルを使うと、株がたまって、セルフベーシックインカムのタネになるよ」と共有
- 紹介した人も、された人も、みんなで株主になっていく
ここでは、
- SNSのタイムラインは「ただの暇つぶし」ではなく
- 「みんなで資本の流れをデザインする場」になります。
しかも、そこで流れるお金は
- 海外プラットフォームの広告費だけでなく
- 日本発のサービスやコミュニティにも戻っていく
つまり、デジタル赤字の一部を「コミュニティ黒字」に変えることができる。
「1円でも安い」がもたらした20年と、これからの20年
ここまでをざっくりまとめると、こんな図式です。
過去30年
- 「1円でも安い」を徹底
- 企業:価格競争 → コストカット → 賃金抑制
- 家計:将来不安 → 支出を絞る → デフレマインド強化
- 結果:失われた20年/30年、賃金停滞、デジタル赤字の拡大
これからの30年に必要そうなこと
- 「最安」だけでなく、「どこにお金が流れるか」を考える
- 国産SNSや共創的なサービスを意識的に選ぶ
- 「みんなで発電」「みんなで販売者」「国民総株主」のように、
支払いを“資本参加”に変える選択肢を混ぜる
もちろん、生活がギリギリのときは
「最安を選ぶ」のは完全に正しい防御行動です。
でも、もし少しだけ余裕があるなら、
生活費の何割かを
「最安」ではなく「共感できる資本の流れ」に振り向けてみる
というのは、個人にとっても、社会にとっても
かなり面白い実験になるはずです。
最安じゃないけど、ここで契約したくなる理由
最後に、このブログタイトルの答えを、シンプルに並べておきます。
最安じゃないけど、ここで契約したくなる理由
- 支払いが、そのまま自分の資本になるから
- ポイントではなく、株・持分として将来のリターンのタネになる。
- 「誰を太らせたいか」を自分で選べるから
- GAFAだけでなく、日本発のサービスや共創的な仕組みを応援できる。
- みんなで販売者・みんなで発電の一員になれるから
- ただの消費者ではなく、紹介者・共同オーナーとして関われる。
- デフレマインドから一歩抜け出す“行動”になるから
- 1円安いだけを追いかけるのではなく、「価値観に合うお金の流れ」を選ぶ練習になる。
- 本気で世界平和や格差是正を語るプレイヤーと、お金の流れでつながれるから
- 「投資先は世界平和」「国民総株主」といったビジョンに、
自分の生活費を通じて参加できる。
- 「投資先は世界平和」「国民総株主」といったビジョンに、
つまり、「最安じゃないけど、ここで契約したくなる理由」は、
“節約”から“自分の経済圏づくり”へシフトしたい人の理由でもあります。早期に上場してくれるといいな~と期待しつつ
これからカブアンドモバイルのようなサービスを設計するなら、
- 料金は“そこそこ”でOK
- その代わり、
- 資本参加
- コミュニティ
- 共創のストーリー
をクラウドファンディングのストーリーのように、どこまで濃く描けるかがソーシャルビジネスモデルの勝負どころになりそうです。
安いところから買いたいをあなたから買いたいといってもらえる商売にシフトする時がやってきましたね!