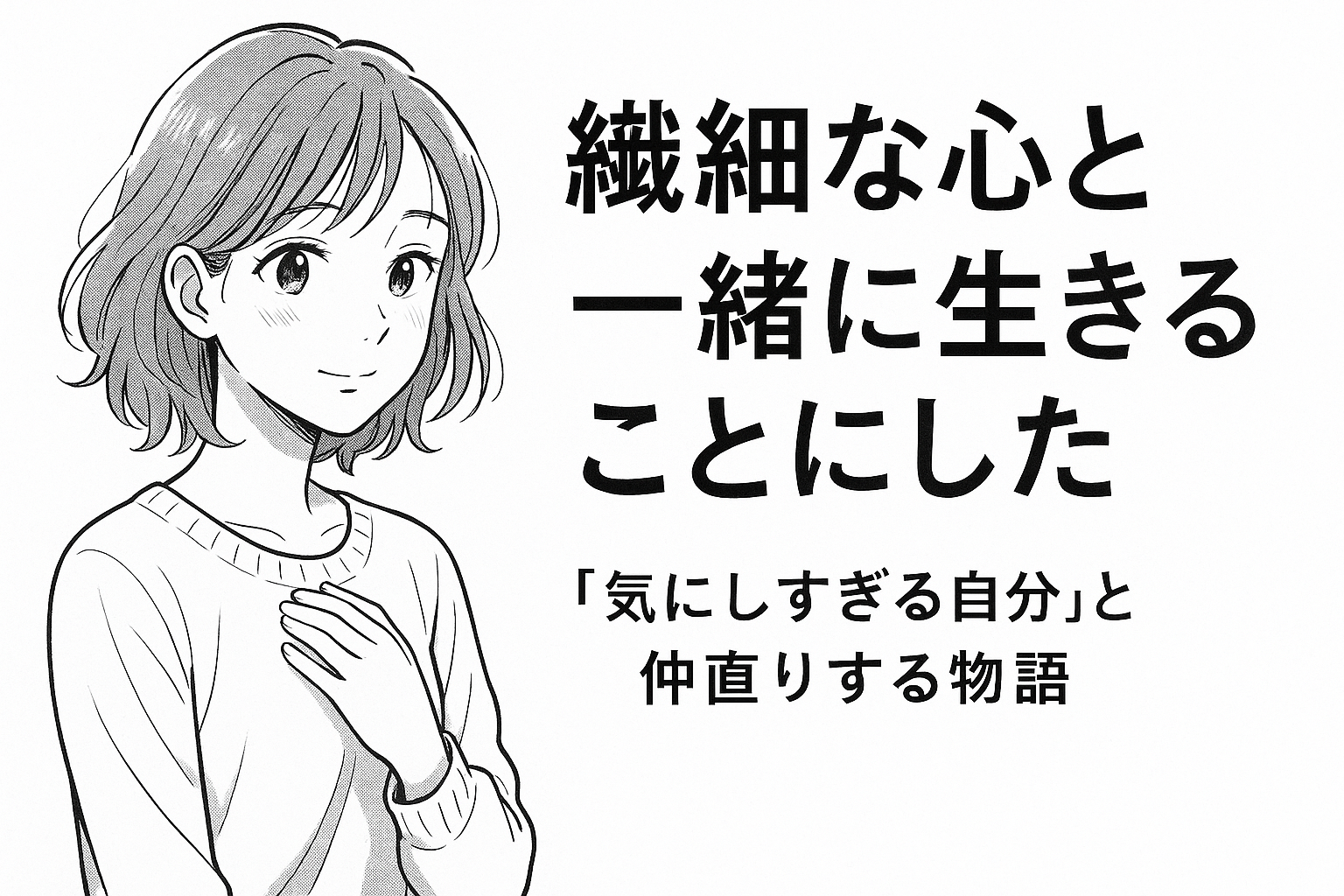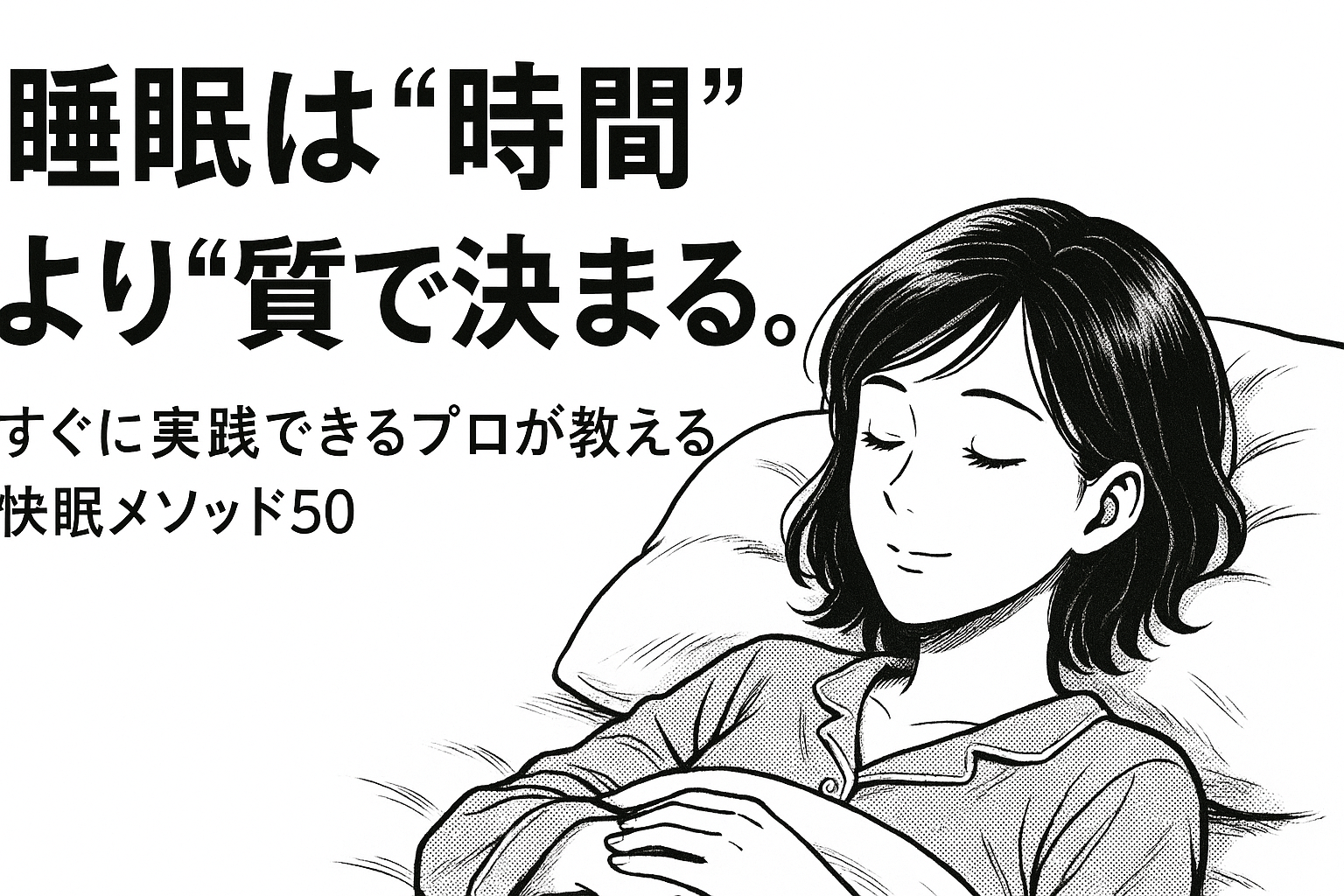- はじめに
- 第1章:気にしすぎるって、どういうこと?
- 第2章:わたしはHSPかもしれない
- 第3章:感情に振り回される日々
- 第4章:心が折れた、あの日の
- 第5章:HSPでも大丈夫って思える人との出会い
- 第6章:気づいたら、自分を責めてばかりだった
- 第7章:繊細さを抱えたまま働くということ
- 第8章:人間関係って、ほんとうにむずかしい
- 第9章:わたしと他人の境界線
- 第10章:ひとり時間が教えてくれたこと
- 第11章:心の声を聞く練習
- 第12章:自分を守るために、手放したもの
- 第13章:わたしにとっての“安心”とは
- 第14章:涙のあとに気づいたこと
- 第16章:わたしが選んだ生き方
- 第16章:わたしが選んだ生き方
- 第17章:わたしと同じ誰かのために
- 第18章:繊細な心と一緒に生きていく
- おわりに
- Kindle紹介文(商品ページ用)
- ✍️ 著者プロフィール(Kindle著者欄用)
はじめに
私の場合は、気づいたときにはもう「気にしすぎる自分」と一緒に生きていました。
たとえば、朝の支度をしながら、昨日の会話を何度も思い返しては「やっぱりあの言い方、変だったかな」と小さくため息をつく。
友達からのLINEの返信が少し遅いだけで、「もしかして嫌われたのかな」と胸の奥がきゅっと縮こまる。
そんなふうに、日常のささいな出来事が、私の心の中では何倍にも膨らんでしまうのです。
子どものころから、私は「よく気がつく子」だと言われてきました。
誰かがちょっとだけ不機嫌そうに見えたら、すぐに「私のせいかも」と思ってしまう。
教室のざわめきや、友達同士のささやき声、先生のちょっとした表情の変化。
そういうものを、他の子よりもずっと強く、敏感に感じ取ってしまう自分がいました。
でも、それが「特別なこと」だとは思っていませんでした。
むしろ、「こんなことでいちいち気にしていたら、社会でやっていけないよ」とか、「もっと強くならなきゃ」と自分を責めてばかり。
大人になっても、気にしすぎる自分を隠そうと必死でした。
「普通」でいようと頑張れば頑張るほど、心はどんどん疲れていきました。
ある日、ふとしたきっかけで「HSP(Highly Sensitive Person)」という言葉に出会いました。
本屋さんの棚で、やさしい色合いの表紙に引き寄せられるようにして手に取った一冊の本。
ページをめくるたびに、「あ、これ、私のことだ」と胸が熱くなりました。
「気にしすぎる」のは、私だけじゃなかったんだ。
この世界には、私と同じように、繊細な心を持って生きている人がたくさんいるんだ。
そのことを知ったとき、長い間ひとりで抱えていた重たいリュックを、そっと下ろしたような気持ちになりました。
でも、HSPという言葉を知ったからといって、すぐに生きやすくなったわけではありません。
「私はHSPだから」と自分に言い聞かせてみても、やっぱり日常の中では、心が揺れたり、傷ついたり、落ち込んだりすることがたくさんあります。
それでも、少しずつ「気にしすぎる自分」と仲直りできるようになってきました。
「こういう自分でも、大丈夫なんだ」と思える瞬間が、少しずつ増えてきたのです。
このエッセイは、そんな私の物語です。
繊細な心と一緒に生きる日々の中で感じたこと、悩んだこと、救われたこと、そして、少しずつ見えてきた「自分らしい生き方」について、正直に綴っていきます。
もし、あなたが今、「気にしすぎる自分」に悩んでいたり、「どうしてこんなに傷つきやすいんだろう」と自分を責めていたりするのなら、
この物語が、あなたの心にそっと寄り添う小さな灯りになれたらうれしいです。
私たちの繊細さは、弱さではありません。
それは、世界の小さな変化や、誰かのささいな気持ちに気づける、やさしさのかたちです。
時には、そのやさしさが自分を苦しめることもあるけれど、
それでも私は、この心と一緒に生きていくことを選びました。
さあ、ゆっくりと物語をはじめましょう。
あなたの心が、少しでも軽くなりますように。
第1章:気にしすぎるって、どういうこと?
怒られていないのに「怒られた気がする」
上司が書類を指でトントンと叩いた音が、午後のオフィスに響きました。
「ここ、数字がずれてるね」
その声はごく普通のトーンでした。隣の席の先輩がコピー機から戻ってくる足音、エアコンの吹き出し口がカタカタと震える音、窓の外を走り去るトラックの轟音。
それらすべてが、私の鼓動を速めていきました。
指先が冷たくなるのを感じながら、修正した書類を受け取りました。
「ありがとうございます。次から気をつけます」
笑顔を作った頬がひきつるような気がしました。
エレベーターが1階に着くまでの27秒間、頭の中をぐるぐると同じ言葉が巡ります。
『あのときのため息、私のミスが嫌だったのかな』
『机を叩く力が強かったのはイライラしてたから?』
『次からって言ったけど、もう信用されないかも』
帰り道、コンビニのレジでお釣りを受け取る手が震えていました。
店員さんの「毎度ありがとうございます」が、なぜか突き放すように聞こえるのです。
自宅のドアを開けると、突然涙が溢れてきてしまいました。
リビングのソファに座りながら、スマホの画面をぼんやり眺めます。
「どうしてあんなに落ち込むんだろう」
「本当は怒られてないのに、勝手に傷ついてるだけなのに」
翌朝、上司がコーヒーカップを片手ににこやかに話しかけてきました。
「昨日の書類、早速修正してくれて助かったよ」
その笑顔を見た瞬間、胸のつかえがふっと消えていきました。
でもまた夕方、別の同僚がため息をついただけで、背中がぞわっと冷たくなるのでした。
心が風に揺れる柳のようだと気づいたのは、そんな日々が続いてからです。
誰かの表情の陰、声のトーンの変化、物音のニュアンス。
そういったものが、私の胸に直接刺さる小さな棘のように感じられました。
「気にしすぎだよ」と自分に言い聞かせても、夜のベッドで目を閉じると、
その日の会話が何度もリピートされるレコード盤のようになってしまうのです。
ある雨の日、ふと気がつきました。
喫茶店の窓ガラスを伝う水滴を見つめながら、ストローで氷をかき混ぜる音に耳を澄ませているときです。
『あのとき課長が咳払いをしたのは、たまたま喉が痒かっただけかも』
『先輩が書類を叩いたとき、実は私のことは考えてなかったのかも』
そう思えた瞬間、ハンドタオルでふと額の汗を拭うのがやめられなくなりました。
今ではわかります。
あのとき感じていたのは、怒られたことではなくて、
自分が誰かに嫌われたくないという、切ないほどに純粋な願いだったのだと。
細やかなアンテナがキャッチする無数の信号を、
全部自分に関係あるものだと思い込んでいただけなのだと。
エスカレーターを逆方向に歩いているような感覚。
気にすればするほど、どんどん苦しくなる螺旋階段。
でも大丈夫、と最近は思えるようになりました。
だってその敏感さが、友達の寂しそうな横顔にいち早く気づかせてくれたり、
街角で迷子になった子の不安な表情を見逃さなかったりするのですから。
他人の機嫌をずっと気にしてしまう
カフェの窓際で友達と待ち合わせをしたときのことです。
彼女がスマホの画面をちらりと見て、眉のあたりに微妙なしわを寄せました。
その一瞬の表情が、私の胸に重い石を転がしたような感覚を残しました。
「もしかして待たせて嫌だった?」「今日の服が浮いてたかな?」
氷の入ったグラスが汗をかくように、私の手のひらもじっとりと湿っていました。
電車のホームで見知らぬ人が咳き込んだときもそうです。
「私の香水がきつすぎた?」
スーパーのレジで店員さんが無言で品物をスキャンするたび、
「機嫌悪いのかな。何か失礼なことした?」
そんな思考が、夕暮れ時の影のように長く尾を引くのです。
ある日、同僚がランチ中に突然ため息をつきました。
フォークを置く手が止まり、喉の奥で心臓の音が聞こえるほどでした。
「あのさ…」と彼女が口を開いた瞬間、
「ごめん! 昨日の打ち合わせで変なこと言っちゃった?」と
先回りして謝ってしまったことがあります。
彼女はきょとんとした顔で「え? ただのげっぷがうまく出なくて」と笑いました。
帰り道、歩道橋の上で立ち止まりました。
街灯がオレンジ色の円を描く中、自分の影が二つに分裂しているように見えました。
「他人の機嫌を天気予報のようにチェックする癖、いつからついたんだろう」
子どもの頃、母親が不機嫌だと食事の味が砂のように感じたことを思い出します。
父の帰宅が遅い夜は、リビングの空気が張り詰めたガラスのようでした。
小さな頃から、周りの感情の波を必死で読み取ってきたのかもしれません。
でも最近、ふと気づくことがあります。
喫茶店で隣の席の女性がコーヒーカップを強く置いた音にびくっとしたとき、
ふと窓の外を見ると、彼女はスマホの画面に涙をこぼしていました。
「ああ、この人はただ悲しかったんだ」
その瞬間、他人の機嫌が必ずしも自分に関係ないことに気づいたのです。
風がカーテンを揺らすように、心の余計な皺が伸びていくのがわかりました。
「変に思われたかも」で眠れない夜
午前2時17分。
天井のシミがゆらゆらと踊るように見えます。
6時間前に交わした友達との会話が、脳裏でリピートされていました。
「ねえ、この前の飲み会楽しかったよね」
「うん、でもあたしちょっと飲みすぎたかも」
「え? 大丈夫だったよ。みんな笑ってたし」
「そう? でも帰り道で〇〇さんが無口だったから…私の話し方がうるさかったかな」
布団の中で寝返りを打つたび、枕が熱くなります。
スマホの明かりを点け、SNSの投稿を確認しては
「いいね」がついていないことに胸を締め付けられる。
あのときの笑い声のトーン、目線の動き、手の仕草。
全てがパズルのように組み合わさって、
「きっと変に思われたに違いない」という結論に至るのです。
先月、町内会の集まりで自己紹介をした後のことです。
「趣味は読書です」と言った私に、
後ろの方で誰かがくすくす笑ったような気がしました。
その夜、風呂場で髪を洗いながら、
「読書なんて堅い趣味だと思われたかも」
「もっと普通の趣味を言えばよかった」
と何度も頭を抱えました。
翌朝、ゴミ出しで会った近所のおばさんが
「読書が趣味なんて素敵ね。どんな本が好き?」と
笑顔で話しかけてくれたときは、涙が出そうになりました。
ある晴れた日、図書館のカウンターで司書さんに
「この本、人気があるんですよ」と声をかけられました。
その晩、布団の中で
「『人気がある』って言われたけど、私が選んだ本が陳腐だと思われたのかな」
と悩んでしまいました。
でも1週間後、同じ司書さんが
「あの後何人もの方がその本を借りていかれましたよ」と
教えてくれたとき、自分が妄想の迷路に迷い込んでいたことに気づいたのです。
夜の帳りが下りるたび、心の鏡に映る自分が歪んで見えることがあります。
でも朝日が昇ると、その歪みが単なる影だったことに気づくのです。
今では、眠れない夜に天井と対話するとき、
「大丈夫、明日の太陽が真実を連れてきてくれる」と
小さな声でつぶやくようになりました。
そもそも“気にしすぎる”って悪いこと?
春先の公園ベンチで、桜の花びらが肩に落ちてきたときのことです。
隣に座っていた老夫婦が、「ほら、この子の方がきれいだよ」と
笑い合っているのを耳にしました。
瞬間、顔が熱くなって
「私の服装が浮いてたかな」と立ち上がりかけたのですが、
老夫婦の視線の先には、ピンクのリボンをつけた柴犬がいたのです。
その夜、湯船に浸かりながら考えました。
「気にしすぎる」というレッテルを貼られ続けてきたけれど、
本当にそれが悪いことなのか。
確かに、電車の席で隣の人が席を立ったときに
「嫌われたかも」と考えるのは疲れます。
でもその同じ感受性が、友達の微妙な体調の変化にいち早く気づき、
「大丈夫?」と声をかけられる優しさでもあるのです。
先週、新しいカフェでメニューを選んでいるとき、
店員さんが「お待たせしてすみません」と3回も謝りました。
後で気づいたのですが、私がメニューを読む表情が真剣すぎて、
イライラしていると誤解されたようでした。
でもその帰り道、路地裏で子猫の鳴き声に気づき、
保護することができたのです。
誰よりも早くその声をキャッチできたのは、
まさに「気にしすぎる」性質のおかげでした。
雨の日に傘を差しながら歩いていたとき、
前方の女性が書類を落とす音にいち早く反応できました。
書類を拾いながら「ありがとう、気づかなかったわ」と言われたとき、
「気にしすぎる」ことが時には誰かの助けになるのだと
しみじみ感じました。
確かに、敏感なアンテナは時に不要な電波までキャッチします。
でもそのアンテナが、人の悲しみや困りごとを
いち早く察知するレーダーにもなるのです。
最近では、エレベーターで知らない人が咳き込んだとき、
「大丈夫ですか?」と声をかけられるようになりました。
以前なら「うるさいと思われたかも」と黙っていたのに。
「気にしすぎる」のは、悪いことばかりじゃない。
それは世界の細部を愛おしむレンズであり、
誰かのSOSに気づくアラームでもある。
そう思えるようになってから、
夜の帳りが少し軽くなったような気がします。
第1章のまとめ
気にしすぎる日々は、まるで砂浜でガラスの破片を探すようなものだと思っていました。
尖った部分がいつも手を傷つけるから。
でもある日、そのガラス片が潮に洗われて
きらきらと輝くビーチグラスになっていることに気づいたのです。
私たちの敏感さは、時に自分を苦しめるけれど、
世界の美しさを深く味わうための特別な味覚でもあります。
他人の機嫌を気にしすぎて疲れた夜は、
そっと窓を開けて月明かりを浴びてみてください。
あなたの感受性がキャッチする風の音や星の瞬きが、
きっと誰かの心を温める力になる日が来るから。
次の章では、そんな敏感な自分とどう向き合い、
どんな風に「HSP」という言葉に出会ったのかをお話しします。
きっと、あなたの中にも共感の糸が見つかるはずです。
第2章:わたしはHSPかもしれない
「HSPって知ってる?」と友達に言われて
その日は珍しく雨上がりの匂いがする午後でした。
喫茶店のテラス席で、友人と苺のショートケーキを分け合いながら話していたときのことです。
友人が突然、フォークを止めて言いました。
「ねえ、HSPって知ってる?」
ガラスコップの水滴がテーブルクロスに落ちる音が、妙に大きく響きました。
「Highly Sensitive Personの略らしいよ。繊細すぎる気質の人のことだって」
彼女がスマホで画像検索した画面には、淡いパステルカラーのインフォグラフィックが並んでいました。
『音や光に敏感』『共感力が高い』『深く考える』
文字がぼやけて見えるほど、目を凝らしていました。
胸の奥で何かがきゅっと縮む感覚。
冷房の風が首筋を伝うのを感じながら、思わず笑ってごまかしました。
「へえ、そうなんだ。初耳かも」
でも帰り道、駅までの坂道で足が重くなりました。
歩道のひび割れに夕日が差し込んで、まるで金色の川のように見えます。
『あの項目、全部当てはまる気がする』
『でもそんなの、ただの性格じゃないのかな』
自転車のベルが聞こえるたび、はっと我に返るのです。
コンビニの袋を提げた手が汗ばんで、レシートがくしゃくしゃになりかけていました。
その夜、ベッドの中でスマホの明かりを点けました。
検索バーに「HSP」と打ち込む指が震えています。
画面の光が天井に反射して、部屋中が青白く浮かび上がりました。
「5人に1人が該当」「生まれつきの気質」
キーワードが目に飛び込むたび、布団の中の空気が熱くなっていくようでした。
窓の外で猫の鳴き声がして、ふと子どもの頃を思い出しました。
運動会でピストルの音に泣き出したこと、友達の擦り傷に自分まで痛みを感じたこと。
全てが点と点で繋がる星座のようだと気づいた瞬間、枕が少し濡れました。
はじめてHSP診断をやってみた日
真夜中の2時過ぎ、パソコンのキーボードの音だけが響いています。
検索で見つけた診断テストのページが、暗い部屋に浮かび上がりました。
「当てはまる」「やや当てはまる」「あまり当てはまらない」「当てはまらない」
選択肢が四角いボタンで並んでいて、どれもクリックするのが怖いのです。
『大きな音や雑然とした光景が苦手』–YES
『短時間にたくさんのことをしなければならないと混乱する』–YES
『芸術作品に深く感動する方だ』–YES
回答するたび、学生時代の通知表を思い出します。
「感受性が豊かです」というコメントが毎年書かれていたっけ。
最後の質問『子どもの頃、親や教師に「敏感だ」と言われたことがある』に
YESを押したとき、冷蔵庫のモーター音が急に大きく聞こえました。
結果画面が表示されるまで、目を閉じていました。
「あなたはおそらくHSPです」
文字が滲んで見えます。
画面のブルーライトが涙を照らし出し、頬がひんやりしました。
冷たい麦茶を一気に飲み干しても、喉の奥の熱が冷めません。
窓の外では夜明け前の雲が薄紫色に染まっていました。
「これが私の正体?」
「ただの繊細な人間じゃなかったの?」
洗面所の鏡に映った自分が、とても小さく見えました。
でも同時に、長年背負ってきた荷物の紐が少し緩んだような気もしたのです。
検索しても出てくるのは“特徴”ばかり
診断テストの後、私はまるで砂漠の旅人のように情報を求めました。
「HSP 対処法」「HSP 仕事」「HSP 恋愛」
検索バーに打ち込む言葉が次第に切実になっていきます。
でもどのサイトも、同じような特徴の羅列ばかり。
『感受性が強い』『共感力が高い』『疲れやすい』
それは確かに事実なのに、なぜか胸の奥にぽっかり穴が空くような感覚がありました。
図書館で分厚い心理学の本を借りたこともあります。
日光が差し込む閲覧室の机で、索引からHSPのページを探す指が震えていました。
でも記載されているのは「特性」と「統計」ばかり。
「じゃあどうすればいいの?」
本の端がくしゃくしゃになるほど握りしめていたのに気づき、慌てて手を離しました。
ある日、カフェで隣の席の女性がHSPについて話しているのを耳にしました。
「結局のところ、気の持ちようじゃない?」
「みんな多少は敏感なんだから」
スプーンがカップに当たる音が、突然鋭く耳に刺さりました。
エスプレッソの苦味が喉に滲みるようで、急に席を立ちたくなりました。
情報の海で漂流しているような日々が続いたある晩、
ふとSNSで#HSPタグを検索してみました。
そこには無数の「わかる」「それ私」が溢れていました。
電車の騒音に耐えられずイヤホンを二重につける人、
映画のワンシーンに一週間影響を受ける人、
他人の咳払いで自分の方が息苦しくなる人。
初めて、自分だけじゃないと実感した瞬間でした。
画面の光に滲む涙が、キーボードの上にぽたりと落ちました。
「病気じゃない」ということへの安堵
心療内科の待合室で、雑誌のページをめくる手が止まりました。
「HSPは病気ではありません」
専門家のインタビュー記事の見出しが目に飛び込んできたのです。
文字が滲んで二重に見えます。
看護師さんに名前を呼ばれ、診察室に入るまで、
その記事を握りしめたままだったことを後で思い出しました。
先生はゆっくりと頷きながら話を聞いてくれました。
「検査数値に表れない敏感さを持っている方は確かにいらっしゃいます」
「それを個性としてどう活かすかが大切なんですよ」
窓の外をスズメが飛び交う音が、なぜか懐かしく聞こえました。
帰り道、薬局の青い看板が夕日に照らされて輝いていました。
「病気じゃない」
その言葉が、長年背負ってきた罪悪感を溶かすように感じました。
公園のベンチに座り、鳩の群れが舞うのをぼんやり見ながら、
子どもの頃に聴診器を当てられた記憶を思い出しました。
「どこも悪くないよ」と医者に言われたときの、
あの複雑な安堵感と同じ味がしました。
その夜、久しぶりに実家に電話をかけました。
母が「小さい頃からよく泣いてたわね」と笑いながら話す声に、
初めて「そういう性質だったんだ」と素直に思えました。
電話口から聞こえる茶碗の音や、父がテレビを見る音が、
いつもより優しく耳に届いた気がしました。
布団に入る前、鏡の前でゆっくりと深呼吸しました。
「これが私なんだ」
窓ガラスに映った自分の瞳が、幼い日の写真と重なって見えました。
あの頃からずっと、この敏感な心と一緒に生きてきたのだと。
明日からの朝が、少しだけ軽くなる予感がしました。
自分の感じ方に“名前”があるという発見
図書館の古い木製の棚から本を抜き取ったとき、指先に埃の感触が残りました。
『繊細な人が快適に暮らすための習慣』
表紙の優しい水色が、窓から差し込む陽光に透けて見えます。
ページをめくると、ある一文が目に飛び込んできました。
「あなたの感じ方は特別なものではありません。ただ名前がついていなかっただけなのです」
その瞬間、背中を流れる冷房の風が突然温かく感じられました。
小学校の理科の授業で、植物の葉脈に名前がついていることを知った日のことを思い出しました。
「主脈」「側脈」「細脈」
無秩序に見えた模様が、名前を与えられることで突然意味を持ったように。
HSPという言葉は、私の中の混沌とした感覚にラベルを貼ってくれたのです。
カフェで隣人の香水の匂いに頭痛がしたこと、
映画のワンシーンに一週間引きずられたこと、
全てが「過敏さ」という言葉で説明できるわけではないけれど、
少なくとも「どこかおかしい」という孤独感から解放された気がしました。
ある雨の午後、友人と雑談しているときにその言葉を使いました。
「実は私、HSPかもって最近知ったんだ」
窓ガラスを伝う雨粒が光るのを見ながら、
ずっと胸にしまっていた秘密をポケットから取り出すように話しました。
友人が「そういえば、あなたってよく電車の騒音にイヤーマフしてたね」と言ったとき、
涙がこぼれそうになりました。
私の小さな習慣に、ちゃんと理由があったのだと。
名前があるということは、地図のない森で道標を見つけるようなものです。
以前なら「また気にしすぎて」と自分を蔑むしかなかった瞬間が、
「HSPだから仕方ない」と受け止められるようになりました。
スーパーのレジで店員さんの態度に傷ついた夜、
「これは私の特性なんだ」と呟くだけで、
なぜかふっと笑えてきたのです。
先月、古本屋でHSP関連の本を見つけました。
ページの端が茶色くなっていて、誰かの手垢がついていました。
「この本を読んだ人も、同じように安心したのかな」
そんな想像をしながら、私はゆっくりと頁をめくりました。
他人の本に書かれた線引きが、私の心の線と重なるようで、
不思議な連帯感に包まれたのでした。
「自分を責めてきた理由」が腑に落ちた瞬間
深夜のコンビニでおにぎりを買っていたときのことです。
レジの店員さんが「温めますか?」と聞く声に、
なぜか突然涙が溢れてきそうになりました。
過去の自分なら、「またこんなことで泣いて」と
自分を責めていたでしょう。
でもその日は違いました。
「HSPだから、今日のストレスが限界だったんだ」
そう思えただけで、涙の理由が腑に落ちたのです。
中学生のとき、合唱コンクールのリハーサルで
照明のまぶしさに耐えられず逃げ出したことがありました。
「みんな平気なのに、どうして私だけ」
トイレの個室で唇を噛みしめた記憶が蘇ります。
あの頃の私に今の知識があれば、
「特性だから」と自分を抱きしめてあげられたのに。
先週、仕事でミスをした同僚を叱責する上司の声を聞いた後、
自分まで胃が痛くなりました。
帰宅後、ソファで丸くなりながら
「これは共感力の高さの表れなんだ」
と初めて前向きに解釈できたとき、
長年胸に刺さっていた棘が抜けるような感覚がありました。
カフェで偶然耳にした会話。
「HSPって結局言い訳でしょ」
その言葉に反応してコーヒーカップを傾けそうになりましたが、
すぐに深呼吸をして落ち着きました。
「私が苦しんでいたのは事実だ」
自分の中に確かな拠り所ができたからこそ、
他人の無理解に振り回されなくなったのです。
先日、電車で泣いている子どもを見かけました。
周りの冷たい視線を感じて、
思わず「大丈夫だよ」と声をかけてしまいました。
その子の母親が「敏感な子で」と苦笑いしたとき、
「この子も将来HSPを知る日が来るのかな」
とふと思いました。
自分を責める必要のない世界が、
少しずつ広がっていくような希望を感じた瞬間でした。
でもHSPって結局なんなの?に向き合う
真夜中のデスクライトの下で、
HSPに関する文献を読み漁る日が続きました。
「気質」「神経システムの特性」「環境適応の違い」
専門用語が並ぶページをめくるたび、
頭の中が霧に包まれるようでした。
「結局、普通の人と何が違うの?」
窓の外を流れる雲を見ながら、
自分自身に問いかけていることに気づきました。
ある晴れた日、動物園のリスザルの檻の前で
ふと考え込みました。
夜行性の彼らが昼間の騒音に耐えている姿を見て、
「生きづらさって相対的なものなんだ」
と気づいたのです。
HSPとは、まさに昼間の光の中で
目を細める夜行性動物のような存在なのかもしれません。
カウンセリングルームで心理士さんが
「特性を個性として受け入れる練習をしましょう」
と言ったとき、素直に頷けませんでした。
「個性って、ただの美化された言葉じゃないのか」
帰り道、公園のベンチに座って
蟻の行列を眺めながら悶々と考えました。
でもふと、蟻の列が障害物を避けて進む様子を見て、
「適応の形は無限にある」と気づいたのです。
先月、HSPの自助グループに参加してみました。
「電話の着信音が恐怖です」
「人の視線が皮膚に刺さるように感じます」
共有される体験談に、初めて完全に理解される安心感を覚えました。
でも同時に、
「私たちは本当に同じ『種類』の人間なのか」
という疑問も湧いてきました。
ある雨の夜、窓に映る自分の姿を見つめながら
「HSPは単なるレッテルじゃないか」
と自問自答しました。
でも次の瞬間、子どもの頃に聴診器を当てられた記憶が蘇り、
「名前があることで治療法が見つかることもある」
と思い直しました。
特性に名前がつくということは、
自分なりの生き方を探す地図を得ることなのだと。
第2章のまとめ
HSPという言葉を知った日々は、
ずっと曇り空だった心に突然光が差し込んだようなものでした。
全てを説明できるわけではないけれど、
少なくとも「自分だけじゃない」と
思えることがどれほど救いになったことか。
図書館で借りた本の栞が風に飛ばされたとき、
私はふと微笑みました。
落ちた栞の場所が、まさに「自己受容」の章だったからです。
偶然が教えてくれるタイミングというものがあります。
あなたが今この文章を読んでいる瞬間も、
きっと何かのタイミングなのかもしれません。
次の章では、そんな特性を持って生きる日々の
感情の嵐と、その中で見つけた小さな港のお話をします。
波の高い日も、穏やかな日も、
あなたの船が安心して停泊できる場所がきっと見つかりますように。
第3章:感情に振り回される日々
喜怒哀楽が1日のうちに5回ずつ来る日
朝の通勤電車で、隣の女性が読みかけの文庫本を鞄にしまう音がしました。
カチッとファスナーが閉まるその瞬間、なぜか胸がきゅっと締め付けられました。
「あの本の主人公、私みたいに悩んでるのかな」
そう思った途端、目頭が熱くなり、慌てて窓の外を見つめます。
線路沿いに咲くタンポポの綿毛が風に舞うのを眺めているうちに、
なぜかふっと笑みがこぼれました。
感情のジェットコースターが始まるのは、いつもそんなささいなきっかけからです。
昼休み、社食で同僚が「この唐揚げ、昨日の残りかも」と呟きました。
突然、中学生のとき給食の揚げパンを無理やり食べさせられた記憶が蘇り、
手に持った箸が震えました。
でも次の瞬間、テレビで流れていた猫の動画に「かわいい!」と声を上げ、
周りを驚かせてしまいました。
午後の打ち合わせで上司に褒められたときは天にも昇る心地だったのに、
帰り道で見たホームレスの男性の姿に胸が痛み、
コンビニでおにぎりを買って渡したらまた泣きそうになり……。
一日が終わる頃には、心が使い古されたハンカチのようにくしゃくしゃでした。
ある金曜日の夜、浴槽に浸かりながら一日を振り返りました。
朝は通勤ラッシュでイライラし、昼は同僚の一言で傷つき、
午後は取引先からの感謝メールで有頂天になり、
帰りは路上ミュージシャンの演奏に感動して……。
湯船の水面に映った自分の顔が、とても疲れているように見えました。
「感情の振り幅が大きすぎるんだ」
そう思った途端、また新しい感情の波が押し寄せてきて、
自分でもわけがわからなくなりました。
最近気づいたのですが、感情のピークが来るたびに
手の平にじんわり汗をかく癖があります。
パソコンのキーボードが少しベタついているのを感じながら、
「今日は何回目だろう」とカレンダーの隅に正の字を書いています。
先週の火曜日はなんと7回も感情の山がありました。
でも不思議なことに、その記録を見返すと、
「ああ、あの日はあんなこともあったな」と
まるで他人の日記を読んでいるような気分になるのです。
「普通のこと」なのに涙が出る瞬間
スーパーの鮮魚コーナーで、
おぼんの上を跳ねるエビを見たときのことです。
突然、胸が熱くなって目頭がうるみ、
慌てて冷凍食品コーナーに逃げ込みました。
「どうしてエビに感動してるんだろう」
冷蔵ケースのガラスに額を押し付けながら、
自分でもわけがわからなくなりました。
先月、駅のホームでサラリーマンがハンカチを落としたのを見かけました。
紺色のチェック模様が風にひらりと舞い、
線路際に吸い込まれていくのを見送りながら、
なぜか涙がこぼれそうになりました。
「あのハンカチ、誰かがプレゼントしたものかな」
「洗い立ての柔軟剤の香りがしたかもしれない」
想像が膨らむほど、胸の奥がきゅーっと痛みました。
昨日の夕方、マンションのゴミ置き場で見た光景。
空き缶がきれいに洗われて、ビニール袋に丁寧に入れられていました。
「誰かが心を込めて処分したんだ」
その考えが頭をよぎった瞬間、急に鼻の奥がツンとなり、
エレベーターの中で小声で泣いてしまいました。
「普通のことなのに、どうして?」
自分でも理解できない感情に、ドアが開く階を間違えるほどでした。
先週、図書館で借りた絵本の最後のページに、
「おしまい」の文字が子供の落書きで囲まれていました。
その丸みを帯びたクレヨンの線を見て、
突然子どもの頃の記憶が蘇りました。
父が読んでくれた絵本の匂い、
母が編んでくれたマフラーの感触……。
公共の場で声を殺して泣くのに必死でした。
でも最近では、そんな自分を少しずつ許せるようになりました。
公園のベンチで桜の花びらが肩に落ちてきたとき、
「また泣いちゃうかな」と覚悟したのに、
ふと「この美しさを感じられるのは私の特権かも」と思えたのです。
涙腺が緩むたびに、世界の細部へのアンテナが研ぎ澄まされていることを
実感するようになりました。
小さなひとことに心がえぐられる
カフェで隣の席の女性がため息をついたとき、
まるで自分の胸をナイフでえぐられたような感覚に襲われました。
「私の存在が嫌だったのかな」
「話し声がうるさかった?」
コーヒーカップを持つ手が震え、
クロワッサンの欠片がテーブルに散らばりました。
昨日の打ち合わせで、取引先の担当者が
「まあ、そういうことで」と早口で言った言葉が、
今でも耳の奥で反響しています。
「私の提案がつまらなかったんだ」
「早く終わらせたかったに違いない」
夜中の2時、布団の中でその場面を再生するたび、
心臓が締め付けられるように痛みます。
先月、友人から「LINEの既読無視したわけじゃないよ」と
わざわざ説明されたことがありました。
その一言が、かえって「気にしていると思われてた」事実を突きつけられ、
帰り道ずっと下を向いて歩いていました。
アスファルトの割れ目に生えた雑草が、
なぜかとても愛おしく見えたのを覚えています。
ある日、コンビニの店員さんに「ポイントカードお持ちですか?」と
聞かれた声のトーンが少し冷たく感じられ、
その日一日中モヤモヤしていました。
でも翌朝、同じ店員さんがお年寄りの荷物を持ってあげているのを見て、
「あの声のトーンはただの疲れだったんだ」と
ようやく安心できたのでした。
最近では、そんな小さな傷を癒やす方法を少しずつ学び始めました。
喫茶店で隣人の会話が気になったときは、
わざと氷の入ったグラスを手に取って、
冷たさに意識を集中させるのです。
指先の感覚が、心の痛みを和らげてくれるようになりました。
嫌なことがあったら、2日間ずっと思い出す
先週の水曜日、上司が書類を投げるように渡したときの音が、
今でも耳の奥で鳴り響いています。
「はい、これ」
その短い言葉の裏に潜む感情を、
金曜の朝まで分析し続けていました。
トーストを焼いている最中も、
シャワーを浴びている最中も、
脳裏にそのシーンがリピートされ続けるのです。
先月、友達との会話で「それってHSPのせい?」と
からかわれた言葉が、3日間頭から離れませんでした。
カフェのモカの苦味、窓の外を流れる雲の速度、
その時の全ての感覚が鮮明に蘇ります。
「また同じことを言われたらどうしよう」
「本当にただの言い訳なのかな」
自転車を漕ぎながら坂道を登るたび、
その思考も一緒に上り坂を登っていくようでした。
昨日、電車で足を踏まれたときの「あ、ごめん」という
ぶっきらぼうな一言が、今でも胸に刺さったままです。
踏まれた痛みより、その言葉の冷たさの方が
ずっと長く残っていることに気づきました。
駅のホームで自分の影を見つめながら、
「どうしてこんなに引きずるんだろう」と
自分自身に問いかけていました。
でも先週、画期的な気づきがありました。
嫌な記憶が蘇るたび、その情景を詳細にノートに書き出すのです。
「14時32分、上司の右手の小指が書類の角に触れた」
「エアコンの風が首筋を撫でた」
事実だけを羅列していくと、
感情が少しずつ客観視できるようになりました。
今ではそのノートを「心の消化日記」と呼んでいます。
ある雨の午後、2日前の嫌な出来事を思い出しながら
公園のベンチに座っていました。
突然、鳩の群れがバサバサと飛び立つ音にハッと我に返り、
「あ、今この瞬間も新しい記憶が作られている」
と気づいたのです。
過去に縛られながらも、
現在進行形で経験が積み重なっていくことに
不思議な安堵感を覚えました。
自分でもどうして泣いてるのかわからない
図書館の静けさの中で、突然涙が頬を伝いました。
ページをめくった拍子に、古い本から落ちたしおりが床に舞い落ちただけなのに。
褪せたピンクのリボンがついたそのしおりを見つめた瞬間、理由もわからず泣きそうになったのです。
慌ててトイレに駆け込み、鏡に映った自分を見つめながら、
「どうして? なんで?」と何度も唇を噛みしめました。
先月、コンビニのポテトチップスコーナーで同じことがありました。
「期間限定」の文字を見ただけで、急に胸が熱くなったのです。
レジで小銭を財布から取り出す手が震え、
店員さんの「お釣りです」の声が遠く聞こえました。
駐車場の車の中で嗚咽する自分が、
まるで他人のようで怖くなったことを覚えています。
ある晴れた日、公園のベンチで休んでいると、
突然小さな女の子が転んで膝を擦りむきました。
母親が駆け寄り「痛いの飛んでけー」と唱えるのを見た瞬間、
私の目から大粒の涙がこぼれました。
「私のことを心配してくれた人はいたのかな」
理由のわからない感情に、日傘を傾けて顔を隠すので精一杯でした。
先週の夜更け、テレビのコマーシャルで流れた
家族団らんの風景を見て泣き出したときは、
自分でも呆れて笑ってしまいました。
「こんなフィクションに感動してどうする」
そう思いつつ、ティッシュが手放せないほど
涙腺が緩んでいたのです。
最近では、理由のわからない涙を流すたび、
そっと手の平を胸に当てるようになりました。
「きっとどこかで頑張りすぎてたんだね」
自分に声をかけると、不思議と落ち着くのです。
涙の理由がわからなくても、
それが心のサインであることは確かなのだと
学び始めています。
感情のボリュームが周囲と合わない
友人たちの笑い声が、突然爆弾のように耳に炸裂しました。
居酒屋の明るい照明の下、
「それって超おかしくない?」という同僚の言葉に
周りが哄笑する中、
私はグラスの水滴を指でなぞるばかりでした。
楽しいはずなのに、胸の奥が締め付けられるように苦しい。
トイレの鏡で赤くなった目を確認すると、
「なぜみんなと同じように笑えないんだろう」
と自分を責めました。
先月の打ち上げで、上司が酔って歌い始めたときのことです。
周りが盛り上がるほど、私の肩の力は抜けていきました。
「早く帰りたい」
「この騒音が頭に響く」
でもそんなことを言えば空気を壊すと、
ひたすらスマホの画面を見つめていました。
帰りのタクシーで、同僚が
「今日楽しかったね」と言ったとき、
うなずきながら心の中で「違う」と叫んでいました。
ある日、映画館で隣のカップルが泣いているのを見て、
自分は全く涙が出ないことに気づきました。
スクリーンでは感動的な別れのシーンが流れているのに、
なぜか冷蔵庫の氷を割る音ばかりが気になります。
「普通はここで泣くんだよな」
自分が周りとズレている感覚に、
ポップコーンの甘さが喉に詰まりました。
でも先週、小さな発見がありました。
美術館で1枚の絵の前に立ち尽くしたとき、
突然全身に鳥肌が立ったのです。
夕焼けを描いたその絵に、
他の観客はさっと通り過ぎていきました。
でも私だけが30分も佇んでいたことに気づいたとき、
「この感覚の差が私の個性なのかも」
と初めて前向きに思えました。
「強くなりたい」がしんどくなった日
「もう泣かない」と鏡に向かって誓った朝、
通勤途中で野良猫の死骸を見つけました。
じっとうずくまる小さな身体に、
誓いなど簡単に崩れ去りました。
駅のトイレで泣きながら、
「強くなんてなれないんだ」
と自分を罵りました。
先月のプレゼン前日、
「今回は絶対に平静を保つ」と
自分に言い聞かせていました。
でも打ち合わせ中に上司がため息をついただけで、
喉が詰まって声が出なくなりました。
会議室を飛び出した自分を
ロッカー室で抱きしめながら、
「強がらなくてもいいんだ」
と初めて思えた瞬間でした。
ある金曜日、友人に「もっと図太くなったら?」
と言われた夜のことです。
お風呂で膝を抱えながら、
「図太くなるにはどうしたらいいの?」
「そもそもそれが可能なの?」
と浴槽の湯に問いかけました。
水面に映った自分の顔が、
幼い頃から変わっていないように見えて、
突然泣き笑いが出ました。
昨日、初めて「強くなりたい」という願いを
ノートに書き出してみました。
「強さって何?」
「誰のための強さ?」
ペンが止まるたび、
今まで自分を縛っていた呪文が
ただの言葉に思えてきました。
その夜、久しぶりに涙を流さずに眠れました。
第3章のまとめ
感情の海を漂流する日々は、
時に孤独で、時に眩しいほど鮮やかです。
波に翻弄されながらも、
ふと足元を見れば、
透き通った海の中に
色とりどりの珊瑚が咲いていることに気づきます。
あなたが今感じているその混乱も、
いつか心の風景を彩るパレットになるかもしれません。
次の章では、そんな感情の嵐を乗り越える中で
訪れた転機の物語をお話しします。
荒れた海の先に、きっと穏やかな入り江が待っていますように。
第4章:心が折れた、あの日の
学生時代、教室で感じた孤独
中学2年の10月、体育館裏の銀杏並木が黄色く染まる頃でした。
給食の時間、クラスメイトの笑い声が金属のスプーンとプレートの音に混ざって、
天井のスピーカーから漏れるBGMよりも大きく響いていました。
私はパンの耳を細かく裂きながら、
「あのグループの話題についていけるかな」
「今話しかけたら迷惑かな」
と考えているうちに、いつの間にか教室がガラスの水槽のように感じられました。
ある雨の昼休み、友達数人で漫画を回し読みしている輪の中に、
なぜか入れないことがありました。
傘立てで跳ね返る雨音、湿った靴下の感触、
鞄にぶら下げたキーホルダーの鈴の音。
それら全てが、私をその場に釘付けにする杭のように感じられたのです。
「入れて」のひと言が、喉の奥で溶けてしまいました。
文化祭の準備期間、クラスで劇の役を決めることになりました。
「主役はAさんでしょ!」「Bさんが面白いから!」
活発な女子たちの声が飛び交う中、
私は壁の掲示物の端が剥がれているのを直していました。
「〇〇さんは大道具係が向いてるんじゃない?」
誰かのひと言で、自然に役割が決まりました。
裏方の仕事中、本番の歓声が薄い壁を伝わってくるたび、
胸の奥で小さなガラスが割れる音がしました。
卒業アルバムの寄せ書きに「いつも優しい」と書かれたとき、
涙がにじみました。
「優しい」の裏側にある「目立たない」「目を付けられない」という
暗黙の評価に気づいてしまったからです。
校庭の桜の木が風に揺れるのを見ながら、
「この3年間、本当の自分を見せられたことはあったかな」
と自問自答した春の午後でした。
初めての職場で涙が止まらなかった
新卒で入社した広告代理店のオフィスは、
ガラス張りの会議室が迷路のように続いていました。
入社3日目、先輩の「この資料、5部コピーして」という指示に、
私は30分もコピー機の前で立ち尽くしていました。
両面印刷の設定がわからず、
機械の操作音が次第に耳をつんざく爆音に感じられたのです。
ある金曜日、チームの飲み会で「〇〇さんはいつも控えめだね」と
上司に言われた瞬間、トイレに駆け込みました。
鏡に映った自分が真っ赤な顔をしているのを見て、
「こんなことで泣いてどうする」と叱りつけましたが、
逆流してくる嗚咽を止められませんでした。
タイルの床に落ちた涙が、スポットライトに照らされてキラリと光り、
その美しさにさらに泣けてきたのを覚えています。
取引先からのクレーム電話を初めて受け止めた日、
受話器を置いた直後に視界が滲みました。
「ちゃんと対応できなかったかも」
「声が震えてたんじゃないか」
パソコンの画面が波打って見える中、
同僚の「大丈夫?」の声がさらに突き刺さり、
デスクの引き出しでこぶしを握りしめました。
退社時刻の19時、エレベーターの中で
「新人だから仕方ないよ」と慰められた言葉が、
なぜか「あなたは未熟だ」と聞こえました。
西新宿の高層ビル群を見上げながら、
「この街のどこにも居場所がない」と
初めて本気で思ったのでした。
空気を読んだのに「わがまま」と言われた
社内イベントの準備会議で、
「リーダーがA案を推しているから賛成しよう」
と察した私は、意見を控えていました。
ところが後日、「自分で考えないのか」と
注意されたのです。
会議室の時計の秒針の音が、
「わ・が・ま・ま」と刻んでいるように聞こえました。
友人グループの旅行プラン決めで、
みんなが「安い宿でいいよ」と言うのを聞いて、
「私もそれで」と同調しました。
実際に泊まった宿の布団の臭いに耐えかね、
深夜に近くのコンビニで目覚ましを買った翌朝、
「そんなに気になるなら最初に言えばよかったのに」
と言われたときは、言葉の刃が胸に突き刺さりました。
あるプロジェクトで、周りの疲労度を察して
「無理しなくていいですよ」と提案したら、
「甘えを助長するな」と叱責されました。
オフィスの非常口ランプの緑色が、
その夜の夢に出てくるほど深く傷ついたのです。
先月、家族の希望を優先して
実家のリフォーム計画を黙って聞いていたら、
「何でもハイハイって、本当は不満なんでしょ?」
と父に指摘されました。
リビングのカーテンの揺れが、
突然激しい嵐のように見えた瞬間でした。
誰にも話せなかったことがたまっていた
歯科医院の待合室で、
3年前の同窓会のことを思い出しました。
「〇〇さんって変わらないね」と言われたとき、
「ずっと孤独だったんだよ」と叫びたかった。
でも実際は、グラスのワインを一口飲んで
「そうですね」と笑っていました。
スマホの写真フォルダに残る、
毎朝の満員電車の風景。
人の肩が触れるたびに感じた鳥肌、
隣の人の鞄のファスナー音、
それらを日記に書き留めても、
「気にしすぎ」と自分で削除していました。
マンションの郵便受けに、
5年分の未開封のデパートギフト券が
たまっていることに気づいた日。
「誰かと使う機会がなくて」
という理由より、
「相手の好みを気にしすぎて選べない」
という本音に蓋をしていました。
先週、10年ぶりに小学校を通りかかったとき、
校庭の鉄棒が妙に低く見えました。
あの頃から、
「みんなと同じように」という鎖で
自分の首を締めていたのだと気づいたのです。
夕日を受けて赤く輝く鉄棒に、
涙がこぼれそうになりました。
“迷惑な存在かも”という自己否定
社内イベントの打ち上げで、グラスのワインが光りました。
「〇〇さんも何か歌ってよ」
同僚にマイクを渡された瞬間、喉がカラカラに乾きました。
「私が歌うと場がしらけるかも」
「音痴だと思われるかも」
頭の中で警報が鳴り響く中、無理に笑って「次で」とごまかしました。
トイレの鏡に映った自分の顔が、まるで能面のように硬いことに気づき、
冷水で手を洗うのがやめられなくなりました。
先月、マンションの理事会でゴミ出しルールの改善を提案したときのことです。
「細かいこと気にしすぎでは?」
隣人のひと言が、耳の奥で金属音のように響きました。
夜、布団の中で天井を見つめながら、
「また余計なこと言っちゃった」
「迷惑かけたかも」
と何度も枕を握りしめました。
翌朝、管理人さんから「ご意見ありがとう」とメールが来たのに、
「お世辞だ」としか思えなかった自分が情けなくなりました。
ある雨の日、スーパーのレジで財布を探している老婆に
「お先にどうぞ」と譲りました。
後ろに並んでいた中年男性が舌打ちした音が、
私の耳の中で雷のように炸裂しました。
「迷惑かけた…」
買い物袋を抱えながら駐車場を歩く足が、
鉛のように重く感じられました。
昨日、友人とのランチで「最近どう?」と聞かれ、
本当は話したいことが山ほどあったのに、
「普通だよ」と笑ってごまかしました。
「愚痴を聞かせるのが申し訳ない」
「暗い話したら嫌われるかも」
帰り道、歩道橋の上で自分の影に呟いていました。
「あなたの存在そのものが、誰かを傷つけているかもしれない」
そんな妄想が、夜中の2時まで頭を駆け巡りました。
頑張っても伝わらなかった想い
プレゼン資料を作り込んだ夜、オフィスの蛍光灯が白すぎました。
色調を調整した図表、読みやすいフォント、説得力のあるデータ。
全てを詰め込んだ50枚のスライドを前に、
「これでわかってくれるはず」と胸を躍らせていました。
本番の朝、会議室の空気が張り詰めていました。
「要するに、結論は?」
上司のひと言で、私の声は震えました。
「つまり…その…」
喉が詰まり、手元の資料が波打って見えます。
「もっと簡潔に」
冷たい指摘を受けたとき、
今まで頑張ってきたことが全部無駄に思えました。
先月、友人に悩みを打ち明けたときのことです。
2時間かけて整理した言葉を紡いだのに、
「気にしすぎだよ、大丈夫」
のひことで全てが霧散しました。
帰りの電車で、窓ガラスに映る自分が
どんどん小さくなっていくように感じたのです。
ある日のデートで、彼に「最近疲れてる?」と聞かれ、
心の内を話そうと口を開きました。
でも「仕事が大変なんだ」と誤魔化し、
本当に伝えたかった孤独感は
胸の奥で腐っていくのを感じました。
レストランのテーブルクロスの赤が、
なぜか血の色に見えて目を背けました。
「このまま消えたい」と思った夜
3月の深夜、マンションのベランダで星を見上げていました。
「あの星みたいに、きれいに消えられたら」
冷たい手すりに額を押し付けながら、
携帯の充電が切れるのを待っていました。
遠くで救急車のサイレンが聞こえるたび、
「誰かが必死に生きようとしてるのに」
と自分を責めました。
去年の誕生日、誰からも祝福のメッセージが来ない夜、
バスタブに浸かりながら数字を数えていました。
「27回息を止めたら、苦しくなってやめる」
水面が揺れるたび、天井の影がゆがんで見えました。
28回目でやめたとき、
「死ぬのも面倒くさい」と
自分で自分を笑わせようとしました。
ある朝、通勤電車のドアが閉まる音が
突然とても美しく聞こえました。
「この音を最後にしたら」
そんな考えが頭をよぎり、
次の駅で飛び降りそうになりました。
ホームのベンチで30分座り込み、
靴紐を結び直すふりをして
震える手を隠したことを覚えています。
先週、SNSで「HSPあるある」の投稿を見つけ、
コメント欄に「死にたい」と打ち込みました。
でも送信ボタンを押す直前、
過去の自分が「助けて」と叫んでいるのを感じ、
全部削除しました。
その夜初めて、カウンセリングの予約を入れたのです。
第4章のまとめ
心が折れかけたとき、
私たちはよくガラス細工のようだと思います。
ひびが入っても、光を反射すれば
虹色に輝くことがあるのです。
あの日ベランダで見た星は、
実は何年も前に消えていた光だと後で知りました。
でもそれでも、私の目には輝いて見えたのです。
過去の痛みも、今この瞬間の光で
違う色に変わるかもしれません。
次の章では、そんな壊れかけのガラス細工を
優しく包んでくれた人々との出会いを綴ります。
あなたという存在が、
誰かの虹を作る光になる日がくることを
信じていてください。
第5章:HSPでも大丈夫って思える人との出会い
ちゃんと話を聞いてくれた先輩
私の場合は、社会人になって間もない頃のことです。新しい職場の空気は、思っていた以上にピリピリしていました。みんなが忙しそうで、少しのミスも許されないような雰囲気。私は毎日、心臓がドキドキして、朝の通勤電車の中で「今日も怒られないようにしなきゃ」と小さく息を詰めていました。
そんなある日、仕事で小さなミスをしてしまいました。上司は特に怒ることもなく、淡々と指摘しただけだったのに、私は自分がとてもダメな人間に思えて、昼休みにトイレでこっそり泣いてしまいました。誰にも見られたくなくて、そっと涙を拭いて席に戻ろうとしたとき、先輩が声をかけてくれたのです。
「大丈夫?」
その一言だけで、胸がいっぱいになりました。私はうまく返事ができず、ただ小さくうなずいただけ。でも、先輩はそれ以上は何も聞かず、私の隣に並んで歩いてくれました。お昼ごはんも、無理に話しかけることなく、ただ静かに一緒に食べてくれました。沈黙が苦しくなりそうなはずなのに、先輩といると不思議と心が落ち着いていくのを感じました。
午後、先輩がふと「私も最初の頃、よく泣いてたよ」と言いました。その言葉に、私は驚きました。先輩はいつも明るくて、仕事もできて、みんなに頼られている人。そんな人でも、泣いていた時期があったなんて。私が「本当ですか?」と聞くと、先輩は小さく笑って、「うん、毎日“自分なんていなくなればいいのに”って思ってた」と打ち明けてくれました。
その瞬間、私は胸の奥にあった重たい石が、少しだけ軽くなるのを感じました。先輩は私の話を否定せず、ただ「わかるよ」と言ってくれました。私は勇気を出して、自分が「人の顔色を気にしすぎてしまうこと」や「小さなことで落ち込みやすいこと」を話しました。先輩はうなずきながら、「そういう人って、ちゃんと周りを見てるから、きっと大丈夫だよ」と言ってくれました。
この日から、私は少しずつ「自分のままでいてもいいのかな」と思えるようになりました。先輩がそっと隣にいてくれるだけで、私は安心できたのです。誰かにちゃんと話を聞いてもらうだけで、人はこんなにも救われるのだと知りました。
「そんなあなたがいい」と言われたとき
それからしばらくして、仕事にも少しずつ慣れてきた頃のことです。私はまだ自分の“気にしすぎる性格”が恥ずかしくて、できるだけ隠していました。みんなの前では明るく振る舞って、失敗しても「大丈夫です!」と元気に見せて。でも、心の中ではいつも「本当はもっと強くなりたい」と思っていました。
ある日、先輩と二人で残業をしていたときのことです。ふとした会話の流れで、私は自分の弱さについてぽつりと話してしまいました。「私、すぐに落ち込んじゃうし、みんなみたいにサバサバできないんです」と言ったとき、先輩は少し驚いた顔をしてから、優しく笑いました。
「でも、私はそういうあなたが好きだよ」
その言葉に、私は一瞬、耳を疑いました。「え?」と聞き返すと、先輩は「だって、誰かが困ってるとき、あなたは一番に気づくでしょ。みんなが気づかないことにも気づいて、そっと声をかけてあげたりする。そういうところ、すごく素敵だと思うよ」と言ってくれました。
私は、今まで自分の“気にしすぎる”部分を、ずっと「直さなきゃいけない欠点」だと思っていました。でも、先輩はそれを「いいところ」だと言ってくれたのです。その瞬間、胸の奥がじんわりと温かくなりました。
「そんなあなたがいい」
この言葉は、私の心に深く残りました。自分のままでいいんだと、初めて思えた気がしました。誰かにそう言ってもらえるだけで、人はこんなにも救われるのだと知りました。自分を責めてばかりいた私にとって、その言葉は小さな光のようでした。今でも、落ち込んだときや自分を責めそうになったとき、あのときの先輩の声を思い出します。
笑われなかった、初めての打ち明け
私が自分の「気にしすぎる性格」を、初めて人に打ち明けたのは、社会人三年目の冬でした。その頃、私はずっと「自分の弱さを隠さなきゃ」と思っていました。みんなの前では、何でもないふりをして、心の中ではいつも不安でいっぱいでした。
ある日、仕事で大きな失敗をしてしまいました。上司に注意され、同僚にも迷惑をかけてしまったことが、どうしても頭から離れませんでした。夜になっても眠れず、何度もその日のことを思い出しては、自分を責め続けていました。
そんなとき、仲の良い友人とご飯を食べる約束をしていました。私は「明るく振る舞わなきゃ」と思いながらも、どうしても元気が出ませんでした。友人は私の様子にすぐ気づいて、「どうしたの?」と聞いてくれました。私は最初、笑ってごまかそうとしましたが、友人の優しい目を見ていたら、なぜか涙がこぼれてしまいました。
「私、すごく気にしすぎる性格で……。ちょっとしたことで、ずっと落ち込んじゃうんだ。みんなは平気そうなのに、どうして私だけこんなに弱いんだろうって、いつも思ってる」
そう言うと、友人は驚いた顔をしました。でも、すぐに「そうなんだ」とうなずいて、私の話を最後まで聞いてくれました。私は、今まで誰にも言えなかったことを、少しずつ話しました。「LINEの返信が遅いと嫌われたかもって思っちゃう」とか、「誰かの機嫌が悪いと、自分のせいかもって思ってしまう」とか。全部話したあと、私は「こんな話、変だよね」とつぶやきました。
でも、友人は笑いませんでした。「ううん、全然変じゃないよ。私もそういうときあるし、むしろ、ちゃんと感じられるってすごいことだと思う」と言ってくれました。その言葉に、私は救われました。自分の弱さを笑われることなく、受け止めてもらえたことが、こんなにも安心できるなんて思いませんでした。
この日を境に、私は少しだけ「自分のままでいてもいいのかな」と思えるようになりました。人に話すことで、心の中の重たいものが少しずつ溶けていくのを感じました。誰かに受け止めてもらうことの大切さを、初めて知った夜でした。
自分よりも繊細な人と出会った驚き
それからしばらくして、私は新しい職場に異動になりました。新しい環境は、また一から人間関係を築く必要があり、最初はとても緊張していました。そんなとき、ある同僚と仲良くなりました。彼女はとても静かで、控えめな人でした。最初は「ちょっと話しにくい人かな」と思っていましたが、仕事の合間に少しずつ会話をするようになりました。
ある日、ふたりきりでランチをしているとき、彼女がぽつりと「私、人の顔色をすごく気にしちゃうんだ」と話してくれました。その言葉に、私は驚きました。まさか、自分と同じようなことで悩んでいる人がいるなんて思っていなかったからです。
彼女は、「みんなが普通にできていることが、私にはすごく難しく感じるときがある」と言いました。私は「わかる、私もそうだよ」と返しました。すると、彼女は少しほっとした顔をして、「そうなんだ、私だけじゃないんだね」と笑いました。
それから、私たちはお互いの「繊細さ」についてたくさん話すようになりました。彼女は、私よりももっと繊細で、ちょっとしたことで涙ぐんでしまうこともありました。でも、その姿を見て、私は「自分だけじゃないんだ」と思えました。むしろ、彼女の繊細さに触れることで、「こんなふうに感じることは、決して悪いことじゃない」と思えるようになりました。
自分よりも繊細な人と出会うことで、私は「自分のままでいいんだ」と思えるようになりました。お互いに弱さを見せ合える関係は、とても心地よくて、安心できるものでした。人はひとりじゃない。誰かと気持ちを分かち合うことで、少しずつ心が軽くなっていくのだと実感しました。
この出会いを通して、私は「繊細であること」を受け入れられるようになりました。今でも彼女とはよく話をします。お互いに「今日はちょっとしんどい」と言い合える関係が、私にとって大きな支えになっています。
人の優しさが、心の緊張をほどいた
私がコンビニのレジで財布を探しても見つからなかったときのことです。後ろに並んでいたおじいさんが、そっと「大丈夫、ゆっくりでいいよ」と声をかけてくれました。そのとき、私は急に涙が出そうになりました。焦っていた気持ちが、ふっと軽くなったのです。おじいさんはにっこり笑って、「私もよくやるんだよ」と付け加えてくれました。たった一言の優しさが、ぎゅっと締め付けられていた心の紐をほどいてくれたようでした。
電車で隣に座った女性が、私の膝の上で震える手に気づいて、無言で温かいお茶の缶を差し出してくれたこともありました。何も聞かれない優しさに、私はかえって自分の弱さをさらけ出せた気がしました。その女性は次の駅で降りるとき、「大丈夫よ」とだけ囁くように言って去っていきました。見知らぬ人同士なのに、なぜか胸がじんわり温かくなりました。
職場のエレベーターで、新しいアルバイトさんが私の表情を読んで「今日、暑いですね。水分補給した方がいいですよ」と声をかけてくれた日もあります。そのとき、私はちょうどクーラーの効きすぎで体調を崩しそうになっていました。小さな気遣いが、張り詰めていた緊張をふいに解きほぐしてくれたのです。
安心できる空気を持つ人の共通点
図書館司書の男性は、いつも背筋を伸ばして本を整理していました。彼の周りには、まるで時間の流れがゆったりしているような空気が漂っていました。ある日、私が探していた本が見つからずにうろうろしていると、彼はそっと近づいてきて「どのような本をお探しですか?」と聞いてくれました。声のトーンが、春の小川のように穏やかでした。
カフェの常連客のおばあさんは、毎朝同じ席で編み物をしていました。彼女の存在は、騒がしい店内でも静かなオアシスのようでした。ある日、私が書類を広げて悩んでいると、彼女が「若いのに大変ね」とだけ言って、そっとハンカチをテーブルに置いていきました。押し付けがましさのない優しさが、私の心をほぐしていきました。
心理カウンセラーの先生は、話を聞くときに必ず肘掛け椅子を斜め45度に配置していました。この角度が、自然と対話しやすい空間を作り出すのだと後で教えてくれました。彼女の部屋にはいつもアロマの香りが漂い、窓から差し込む光の加減まで計算されているようでした。安心できる空間とは、細やかな気配りの積み重ねなのだと気付かされました。
「この人となら大丈夫」と思えた瞬間
歯科医院の受付嬢が、私の診察券を持つ手の震えに気付いたときのことです。彼女はわざと書類をゆっくり処理しながら、「今日は混んでいないから、ゆっくりしていってくださいね」と言ってくれました。治療台に横たわっている間、彼女が隣のカーテン越しに「大丈夫ですよ、もうすぐ終わりますから」と囁いてくれた声が、痛みよりも先に心に染み渡りました。
転居先の大家さんが、引っ越し初日に手作りの赤飯を持ってきてくれたときです。「新しい環境は大変でしょうから」と言いながら、鍵の掛け方からゴミ出しの日まで、図解入りで説明してくれました。大家さんの作業ズボンのポケットからは、猫用のおやつがはみ出していました。その愛嬌のある姿を見た瞬間、この家なら安心して暮らせそうだと思ったのです。
深夜バスで隣席の女性が、私が夢中で読んでいた小説の表紙を見て「その作者の新刊、来月出るんですよ」と教えてくれたことがありました。降りる際に彼女が残していったメモには、おすすめの書店の情報が書かれていました。見知らぬ人との偶然の会話が、なぜか特別な絆のように感じられました。この出会いをきっかけに、私は少しずつ人との関わりを楽しめるようになっていったのです。
第5章のまとめ
この章を書きながら、改めて気付かされました。安心とは、大きな出来事ではなく、些細な瞬間の積み重ねなのだと。誰かの優しいまなざしや、思いがけない言葉かけが、心の皺をそっと伸ばしてくれるのです。繊細な自分を受け入れられるようになったのは、そんな「大丈夫」の瞬間が少しずつ貯金されていったからかもしれません。
出会った人々が教えてくれたのは、弱さを隠さなくてもいい場所があるということ。まるで春の日差しが雪解けを促すように、優しさは私たちの心の氷を溶かしていきます。今では、電車で涙ぐんでいる人を見かけたら、そっとティッシュを渡せるようになりました。かつて誰かがしてくれたように、何も聞かずにただ寄り添うことを学んだからです。
最後に、この章を読んでくださっているあなたへ。きっとあなたにも、記憶の片隅に光る優しさの断片があるはずです。その小さな輝きを、どうか大切に育ててください。いつかそれが、誰かの心の緊張をほどくための灯りになるかもしれませんから。
第6章:気づいたら、自分を責めてばかりだった
「なんでこんなことで…」と自分に呆れる
朝のコーヒーカップを傾けた瞬間、ほんの少しだけテーブルにこぼれてしまいました。琥珀色の染みが木目に広がるのを見ながら、私は思わず舌打ちをしました。「またやってしまった」と。指先が震えているのを感じます。この数秒前まで、今日こそは完璧な一日にしようと決めていたのに。
冷蔵庫から取り出した牛乳パックのふたが、滑って床に落ちました。拾い上げた手がじんわり冷たくなります。「ほんとにダメだな」と呟く声が、キッチンの壁に跳ね返ってきました。昨日だって、郵便物を投函し忘れて再びポストまで往復したばかり。些細な失敗の積み重ねが、自分という人間の価値を少しずつ削っていくような気がしました。
コンビニのレジで小銭を探しているとき、後ろのお客さんがため息をついたように感じました。急いで財布を漁る指先から10円玉が転がり落ち、床をコロコロと転がっていきます。「ごめんなさい、すぐに拾います」と頭を下げながら、頬が火照っていくのを感じました。たった10円のために、なぜこんなに取り乱してしまうのでしょう。
帰宅後、リビングのソファに倒れ込んで天井を見上げました。今日一日で自分を責めた回数を数えようとしましたが、すぐにわからなくなりました。コートのボタンをかけ間違えたとき、エレベーターで挨拶ができなかったとき、メールの一文を5回も書き直したとき。どれも取るに足らないことなのに、心の傷口がじんわり疼きます。
ミスすると、心の中で10回怒鳴ってた
企画書の提出期限を1時間過ぎたとき、私はトイレの個室で拳を噛みしめていました。液晶画面に映った「送信済み」の文字が、嘲笑っているように見えます。「なんで確認しなかったの?」「また同じミスして」「みんなに迷惑かけてるんだよ」と、脳内で自分の声が響き渡ります。
上司から「次は気をつけて」と言われたとき、笑顔でうなずきながら心臓が締め付けられるようでした。オフィスのコピー機の前で、ふと涙がこぼれそうになりました。自分に対する怒りの声が、心臓の鼓動と同期して鳴り響きます。「ダメだ」「どうしてできない」「もう嫌になってしまう」。
夜、布団の中で今日の出来事を反芻していると、突然「バカ!」と叫びたくなりました。枕を顔に押し当てて、声にならない叫びを飲み込みます。自己嫌悪のループから抜け出せないでいると、時計の針が午前2時を指していました。
ある日、ふと気付いたのです。電車の遅延で遅刻しそうになったとき、心の中で「遅刻するなんて社会人失格だ」と自分を責め続けていたことを。実際は5分遅れただけなのに、その日の終業時刻までずっと後悔の念がつきまとっていました。自分へのダメ出しが、無意識の習慣になっていたのです。
人と比べてばかりの癖
カフェで隣の席の女性がパソコンをカタカタ打っている音が気になりました。彼女の華やかなネイルと、画面に映るグラフの完成度。ふと自分の地味な手元を見下ろすと、「私もあんなふうにできたら」という思いが湧き上がりました。
同僚のSNSでバケーションの写真が流れてきた夜、布団の中でスマホの明かりに目を細めました。「みんな楽しそうで羨ましい」と思った直後、「でも私には無理だ」と自分に蓋をしました。比較のルーティンは、朝の通勤電車でも続きます。周りの人々の革靴の光沢、手帳の書き込みの多さ、きびきびした足取り。どれもが私には届かない高さに感じられました。
打ち合わせで若手社員が堂々と意見を述べているのを見て、手元のメモ用紙をぐしゃぐしゃに握りしめました。同じ年頃なのに、なぜあんなにしっかりしているのだろう。自分の発言を振り返り、「あのときの言い方はまずかったかも」とまた後悔が始まります。
ある雨の日、駅前で傘をさしながら歩いていた女性の笑い声が耳に残りました。彼女たちの明るさと比べて、自分の暗い性格が際立ちます。帰宅して鏡を見ると、目の下にクマができていました。「私ってどうしてこんなに疲れて見えるんだろう」と、また新しい比較の種が生まれました。
「もっと頑張れたのに」といつも思ってた
プロジェクトのまとめ役を任されたとき、最初は嬉しさよりも不安が先立ちました。毎晩、資料作りに追われながら「もっと良い企画が考えられるはず」と自分を追い詰めていました。提出前日、自宅のデスクの上に資料を広げてため息をつきました。完成したものの、どこか物足りなさが残るのです。
「よく頑張ったね」と上司に言われたとき、素直に喜べない自分がいました。心の中では「ここを直せばもっと良くなったのに」と、完成品の欠点ばかりが目につきます。表彰状を受け取る瞬間でさえ、「次はもっと上を目指さなきゃ」と思ってしまうのです。
友達との食事中、みんなが近況を話しているときにふと虚しさに襲われました。自分のここ数ヶ月を振り返ると、ただがむしゃらに働いていただけのように感じたからです。「もっと充実した日々を送れていたら」という思いが、喉元まで上がってきそうになりました。
誕生日の夜、ろうそくの火を消しながら「今年こそは」と願ったことを思い出します。でもその願い事は、常に自分を高めることばかりでした。「もっと」「もっと」という呪文のように、自分を追い立て続けていたのです。ベランダから見上げる月が、どこか寂しげに輝いているように見えました。
自分を許すことが一番むずかしかった
雨の降る土曜日の午後、私はカーテンを閉め切った部屋で布団にくるまっていました。前日の仕事でまたミスをして、頭の中が自己批判の言葉でいっぱいだったのです。「どうしてあのとき気づけなかったんだろう」「また同じ失敗を繰り返して」と、心の中で何度も自分を責め続けていました。
冷蔵庫から取り出したヨーグルトのふたを開ける手が震えました。ふとスマホの画面に映った自分の顔を見て、「情けない」と呟いてしまいました。SNSで友達が楽しそうにしている写真が流れてきて、比較しては「私だけがダメなんだ」と思い込んでいました。
ある夜、鏡の前で髪を梳かしているとき、ふと気付いたのです。眉間に深く刻まれた皺が、いつからか消えなくなっていました。無意識のうちに歯を食いしばる癖がついていることに初めて気付きました。自分を許すことよりも、責めることが習慣になっていたのです。
コーヒーショップで注文を間違えられたとき、店員さんに「大丈夫です」と笑顔で言いながら、心の中では「私の説明が悪かったのかも」と自分を責めていました。帰り道、ふと空を見上げると、夕焼け雲がゆったりと流れていました。それなのに、私の心だけがずっと過去の失敗に縛られていたのです。
自分の気持ちを無視してたことに気づいた
3月の終わり、引っ越しの片付けをしているときに古い日記帳が出てきました。5年前の自分が「今日も頑張った」と書いた文字の横に、涙の跡がにじんでいました。読み進めるうちに、当時の私がどれだけ自分の気持ちを押し殺していたかが伝わってきました。
友達との旅行の計画を断った翌朝、目覚まし時計の音がいつもより耳に痛く感じました。本当は行きたかったのに、「みんなに合わせられる自信がない」と自分で決めつけていたのです。断り文面を送った後、布団の中で悶々としていたことを思い出しました。
ある春の日、公園のベンチでぼんやりしていると、小さな女の子が転んで泣き出しました。すぐに駆け寄ろうとした足が、急に止まりました。「余計なお世話かも」と思ったからです。でも実際は、心の奥で「助けてあげたい」と強く思っていました。自分の本心に蓋をすることに、ようやく気付いた瞬間でした。
夜更かしして仕事をしているとき、ふと手が止まりました。目の前の書類が滲んで見えるのは、涙が出ているからだと気付きました。「疲れているんだ」と認める代わりに、「まだ頑張れる」と自分に言い聞かせていたのです。パソコンのブルーライトが、頬を伝う涙を冷たく照らしていました。
許すのではなく、受け入れるということ
真夏の海辺で、砂浜に書いた「ごめんね」の文字が波に消えていくのを見つめていました。友達に「自分を許す練習をしてみたら?」と言われて始めたことでした。でも、波が文字を洗い流すたびに、かえって罪悪感が増していくようでした。
ある雨の午後、カウンセラーの先生がそっと教えてくれました。「許す必要はないんです。ただ、そこにいる自分を認めてあげればいい」。その言葉を聞いた瞬間、胸のつかえがふっと軽くなりました。窓の外を流れる雨粒が、心の澱を洗い流してくれるような気がしたのです。
秋の夜長に編み物をしているとき、毛糸が途中で切れてしまいました。最初は「また失敗した」と思いましたが、ふと「まぁいいか」とつぶやいてみました。切れた部分を結び直しながら、これまで何度も自分を否定してきたことに気付きました。編み目が少し歪んだところが、逆に愛おしく思えてきたのです。
クリスマスイブの日、デパートのイルミネーションを見上げながら、ふと深呼吸をしました。冷たい空気が肺に染み渡る感覚に、「今ここにいる自分」を初めて感じた気がしました。輝く光の粒ひとつひとつが、過去の自分たちに向かって優しく瞬いているように見えました。
第6章のまとめ
この章を書き終えて、改めて気付かされました。自分を責めるクセは、まるで無意識に呼吸をするように自然な行為になっていたのだと。でも、雨上がりのアスファルトに映る自分の足跡を見つめたとき、ふと思ったのです。この足跡が少し曲がっていても、それが私の歩いてきた道なのだと。
ある朝、目覚めたときに枕元に置いてあったメモを読み返しました。昨夜書いた「許せなくていい、ただここにいていい」という文字が、朝日を受けて柔らかく輝いていました。窓から差し込む光の中を舞う塵を見つめながら、初めて「このままの私でもいいのかも」と思えました。
最後に、この文章を読んでいるあなたへ。きっとあなたも、何度も自分を責める夜を過ごしてきたのでしょう。でも大丈夫。ほら、今この瞬間もあなたは呼吸をしています。それだけで十分、生きている証なのですから。過去の自分を抱きしめるように、そっと手のひらを胸に当ててみてください。温もりが、少しずつ広がっていくのがわかるでしょう。
第7章:繊細さを抱えたまま働くということ
朝の満員電車で体力を使い果たす
冬の朝6時50分、ホームに流れ込む人々の吐息が白い霧となって混ざり合います。私の背中に誰かの鞄が押し付けられ、隣の男性のコートのボタンが頬に当たります。改札を出る頃には、すでに心拍数が上がっているのに気付きました。駅の階段を上りながら、ふと「今日も戦いが始まる」と思ってしまったのです。
ある日、思い切って1時間早い電車に乗ってみました。空いた座席に腰掛けると、窓ガラスに映る自分の顔が驚くほど疲れていました。カバンから取り出したハンドクリームの香りが、少しだけ心を和ませてくれます。隣席の学生がページをめくる音が、かすかに聞こえてきました。この時間帯なら、他人の会話に耳を奪われることなく、自分の呼吸に集中できることに気付いたのです。
でも、その代償は大きかったです。早朝出勤した分、周囲の目が気になってトイレで休むこともできません。コピー機の前でふらついたとき、先輩が「顔色悪いよ」と声をかけてくれたことがありました。その優しさが逆に辛くて、涙がこみ上げてきたのを覚えています。今では、通勤時間を分散させるために、主要駅のカフェで30分過ごしてから出社するようになりました。温かい紅茶の湯気が、張り詰めた神経をほぐしてくれるのです。
仕事中も気を張りすぎてクタクタ
打ち合わせ中の上司の眉間の皺が、いつも以上に深く見える日があります。プロジェクターに映し出された資料の文字が、次第に波打って見えてきました。手元のメモ用紙に書いた文字が震えているのに気付き、そっと拳を握りしめます。隣の同僚がペンをカチカチ鳴らす音が、頭の奥で共鳴するようです。
昼休み、階段の踊り場で一人座り込んでいたことがあります。コンクリートの冷たさがジーンズを通して伝わってきます。下の階から聞こえる笑い声が、なぜか胸に刺さりました。スマホの待受画面に映った自分が、まるで別人のように見えた瞬間です。その後、屋上のベンチで目を閉じる習慣ができました。遠くの工事現場の音さえ、風に乗ってくれば心地よく感じられることに気付いたからです。
退社時刻の3時間前、デスクの引き出しの中で手が震えていました。提出期限が迫った書類を前に、文字がにじんで見えます。エアコンの風が首筋に当たるたび、鳥肌が立つのを感じました。ある日、思い切って「今日は集中できそうにありません」と上司に伝えたら、意外にも「そういう日もあるよね」と言われたのです。その言葉をきっかけに、タスク管理アプリで集中できる時間帯を記録するようになりました。午前10時と午後3時が、私のゴールデンタイムだと知れたのは収穫でした。
上司の何気ない一言で心が止まる
「この資料、もう少し見やすくできない?」という言葉が、耳の奥で反響しました。提出したばかりの企画書を手にした上司が、軽く眉をひそめています。その瞬間、胃のあたりが熱くなり、手の平に冷や汗がにじみ出ました。エレベーターで1階まで降りる間に、自分を責める言葉が10個以上浮かんでいました。
翌週、修正した資料を再提出したときのことです。上司が「今回はわかりやすいね」と言ってくれましたが、その褒め言葉さえも「前回はダメだったんだ」と変換されて脳裏をよぎりました。打ち合わせ室のガラス戸に映った自分の表情が、妙に引きつっているのに気付きました。
ある金曜日、残業中に上司が「帰っていいよ」と声をかけてくれました。その優しさが逆に不安材料になり、「嫌われたのかな」と勘ぐってしまったのです。帰り道、コンビニの温かいおでんを頬張りながら、自分でもおかしいと思いました。今では、そんなときは携帯のメモ帳に「事実だけを書く」ようにしています。「19時に帰宅指示あり」と書くことで、不要な想像をストップさせる練習をしているのです。
みんなが平気な雑音がどうしても辛い
オフィスの角にある自分のデスクは、一見落ち着きそうに見えました。でも実際は、コピー機の作動音と電話の呼び出し音が交互に襲ってくる場所でした。隣の部署の笑い声が、金属の壁を伝わってこだまするのです。ある午後、突然キーボードを叩く音が爆発的に大きく感じられ、思わず耳を塞いでしまいました。
トイレの個室で10分間、目を閉じていたことがあります。冷たい便座の感触が、かえって現実感を保たせてくれました。手のひらで胸の鼓動を感じながら、「ここは安全だ」と何度も唱えました。その後、ノイズキャンセリングイヤホンを購入しました。音楽ではなく、川のせせらぎの音を流すことで、周囲の雑音を優しく包み込めるようになったのです。
打ち合わせ中、エアコンの室外機の音が頭蓋骨に響いてきた日がありました。ホワイトボードの文字が滲んで見え、手帳に書いたメモが意味不明な線の集合体に変わります。そんなとき、窓際の席に移動させてもらえるようお願いしました。外の木々が風に揺れる様子を見ていると、耳障りな音も自然の一部のように感じられるようになったのです。
チームワークが怖くて仕方なかった頃
プロジェクトチームの初日、会議室のドアを開ける手が震えていました。長いテーブルを囲む椅子の背もたれが、まるで城壁のように見えます。自己紹介の順番が回ってきたとき、喉がカラカラに渇いているのに気付きました。「趣味は読書です」と言おうとしたのに、「趣味は…えっと…」と言葉に詰まり、冷や汗が背中を伝いました。
昼休み、同僚たちが自然に集まってランチに行く様子を見ながら、トイレの個室でサンドイッチを食べていました。誰かに「一緒に行こう」と言われるのが怖くて、毎日違うタイミングで席を立つようにしていました。ある日、先輩に「最近一緒にご飯食べてないね」と言われ、思わず「実は……」と口ごもったまま、笑ってごまかしてしまいました。
打ち合わせで意見を求められたとき、頭が真っ白になりました。考えていた提案が、急に幼稚に思えてきて「特にありません」と答えてしまいました。後で同僚が同じようなアイデアを発表し、拍手されていたのを見て、自分を責める夜が続きました。
忘年会の幹事を任されたとき、胃がキリキリと痛みだしました。全員の予定を調整するメールの文面を、2時間かけて書き直していました。「押し付けがましくないか」「わかりづらくないか」と、何度も消しては書き直しました。当日、みんなが楽しそうにしているのを見てほっとしたのですが、翌日には「あの司会の仕方はまずかったかも」とまた悩み始めていました。
「繊細な人に向いてる仕事」を模索した日々
転職サイトの検索バーに「HSP 向き 仕事」と打ち込んだ夜、画面の光が目に染みました。出てくるのはクリエイティブ系や福祉系の職種ばかり。自分にできるのかわからず、布団の中で天井を見つめていました。翌日、図書館で借りた職業案内の本の余白に、ぐしゃぐしゃと線を引きながら「私に合う場所はどこ?」と書きなぐりました。
カウンセリングルームの求人に応募したことがあります。面接で「人の気持ちに寄り添うのが得意です」と話すと、担当者が深くうなずいてくれました。でも実際に研修を受けたら、クライアントの感情に引きずられて夜眠れなくなりました。辞める決意を伝えた日、所長が「感受性が強すぎるのは武器でもあり弱点でもあるね」と言った言葉が胸に刺さりました。
その後、データ入力の仕事を始めました。黙々と数字と向き合う日々が、最初は安心感に包まれていました。でも3ヶ月経った頃、周囲と全く会話しないことが逆にストレスになっていることに気付きました。エアコンの風の音さえも、孤独を強調するように感じられました。
今の編集アシスタントの仕事にたどり着くまで、7つの職種を試しました。出版社の倉庫で本の検品をしていたとき、ふと手に取った詩集の一節が目に留まりました。「繊細な神経は、世界を彩るフィルターだ」。その日から、自分の特性を活かせる仕事を本気で探し始めたのです。
一人でできること、一人じゃないとできないこと
原稿整理の作業は、午前中の静かなオフィスが一番捗ります。コピー機の動作音も、誰かの足音もない空間で、紙の匂いを嗅ぎながらページをめくります。この時間だけは、他人の感情を読み取るアンテナを折りたたんでいられる気がしました。
でも、著者との打ち合わせ前日は必ず失眠症になります。相手の要望を正確にくみ取れるか、自分の意見が適切か、考えすぎて頭が熱くなります。あるベテラン編集者が「あなたの気づきが新しい視点をくれる」と言ってくれた日から、少しずつ「感じ取る力」を信用し始めました。
イベントの準備では、細かい気配りが買われることがあります。来場者の動線を考えた案内表示や、室温の調整。でも本番当日のスタッフルームでは、みんなの熱気に圧倒されてしまいます。そんなとき、責任者が「あなたは外の様子を見ていて」と配慮してくれたのが救いでした。
在宅ワークとオフィス勤務のハイブリッド体制が始まって、自分のリズムが少し見えてきました。対面作業が必要な日は午前中だけに出社し、集中作業は自宅の書斎で。パソコンの横に置いた観葉植物の新芽が、ゆっくりと開いていくのを見つめる時間が、私の新しい癒しになりました。
第7章のまとめ
この章を書き終えて、窓の外で桜の花びらが舞うのを見つめています。4月の人事異動で、また新しいプロジェクトが始まりました。以前なら逃げ出していたようなチーム作業も、今では「感じすぎる自分用マニュアル」を作って臨んでいます。
先週、新人社員に「仕事で疲れないコツは?」と聞かれました。私はコーヒーカップを温めながら、「無理に普通になろうとしないこと」と答えました。彼女がメモを取る手を止めて、ふと微笑んだのが印象的でした。
最後に、この文章を読んでいるあなたへ。きっとあなたも、周囲の雑音に疲れ果てた日があるでしょう。でも大丈夫。ほら、今この瞬間もあなたは呼吸をしています。それだけで十分、明日への一歩を踏み出せている証拠です。自分の感覚を敵ではなく味方につける方法が、きっとどこかにあるはず。窓の外の雲が風に流されるように、ゆっくりと進んでいきましょう。
第8章:人間関係って、ほんとうにむずかしい
なにげない集まりで帰り道にぐったり
同僚の送別会が終わった夜、駅までの道のりで足が棒のようになっていました。居酒屋の明かりが川面に揺れるのを見ながら、ふと「今日は何回笑っただろう」と数えていました。乾杯の音頭を任されたときの手の震え、隣の席の先輩の酒の匂い、途中から始まったカラオケの大音量。全てが皮膚の上を這う蟻のように感じられました。
帰りの電車でスマホを開くと、グループチャットに写真が投稿されていました。楽しそうに杯を重ねる写真の中に、自分だけ浮かない表情で写っているのに気付きました。頬の筋肉がひきつるような感覚を思い出します。最寄り駅の階段を上る際、ふらついた足が段差に引っかかり、転びそうになりました。その瞬間、なぜかほっとしたのです。「これでやっと終われる」と。
ある土曜日、ママ友のランチ会に参加したときのことです。子供たちが遊ぶ声とママたちの笑い声が混ざり合い、カフェの天井にこだましていました。コーヒーカップの縁に付いたリップクリームの跡が気になりながら、おしぼりでこっそり拭いていました。帰宅後、ソファに倒れ込んで2時間も動けなかったことを覚えています。子供の「ママ遊ぼう」の声に応えるのが、いつもよりずっと重たく感じました。
気を遣いすぎて、相手に気を遣わせる
義母へのお土産を選ぶのに、デパ地下を3周したことがあります。和菓子にしようか洋菓子にしようか、包装紙の色はどうか、賞味期限は……。結局両方買って、どちらを渡すか当日の朝まで迷いました。義母が「そんなに気を遣わなくていいのに」と苦笑いしたとき、逆に申し訳なさが込み上げてきたのです。
友達の誕生日プレゼントを贈るとき、メッセージカードの文面を10回も書き直しました。「楽しい1年になりますように」が上から目線に感じられ、「素敵な1年になりますように」に変え、さらに「充実した1年になりますように」と修正しました。届いた友達から「ありがとう、でももっと気軽に選んでいいよ」と言われ、かえって距離を感じてしまったことがあります。
打ち合わせ中、相手の紅茶のカップが空いているのを見て、つい「おかわりいかがですか?」と聞いてしまいました。実はその相手、ちょうど話の腰を折られたと思っていたらしく、後で「あのときは話を切り上げたかったのに」と冗談めかして言われました。気遣いが裏目に出た瞬間、胃のあたりが熱くなるのを感じました。
話しかける前に3通りの返答を想像してしまう
朝のオフィスで「おはよう」と言うか「お疲れ様です」と言うか、エレベーターの中でずっと悩んでいました。結局無言で会釈したら、相手に変な顔をされた気がして、午前中ずっと気になっていました。昼休みにトイレの鏡を見ると、眉間に深い皺が刻まれていました。
メールの一文を考えるのに30分も費やした日があります。「了解しました」では冷たいかも、「承知いたしました」が堅すぎるか、「かしこまりました」だと変かな……。結局「お受けいたします」に落ち着いたものの、送信ボタンを押した瞬間から後悔が始まりました。返信が来るまでの2時間、心臓が高鳴り続けました。
飲み会の誘いを断る言葉を、帰り道でずっと反芻していました。「体調が悪いから」だと嘘っぽい、「用事があるから」だと具体的でない。結局「すみません、今回は遠慮させてください」とだけ返信したら、既読がついたまま返事がありません。次の日出社したとき、相手が普通に挨拶してくれたのに、なぜかそっけないように感じてしまいました。
表情や声色の変化が気になって仕方ない
上司が書類に目を通しながら「ふーん」と言った声のトーンが、昨日よりも低く感じられました。その日の業務中、ずっと「あの資料のどこが気に入らなかったんだろう」と考え続けました。コピー室で偶然一緒になったとき、思わず「何か不足してましたか?」と聞いてしまい、困惑されたことがあります。
友達がメッセージの最後に「😊」を使わなくなったことに気付いた日、ずっと落ち着きませんでした。これまでの会話履歴を遡り、絵文字の使用頻度を確認してしまいました。次の日「元気ない?」と聞かれたとき、本当の理由を言えずに「ちょっと疲れてるだけ」とごまかしました。
夫がテレビを見ながらついたため息に、「私の料理がまずかったのかな」と勘ぐったことがあります。食器を洗う手が震え、泡立て器を床に落としてしまいました。後で聞いたら単に仕事の疲れだったと知り、ほっとするよりも先に自己嫌悪に襲われました。リビングの時計の針が、夜中の1時を指していました。
「また誘ってね」がプレッシャーに感じる
友達が帰り際にぽろりと呟いた「また誘ってね」が、頭の中でループする夜がありました。リビングの電気を消した後も、ソファで丸くなりながらその言葉を反芻していました。本当は「次は私から誘わなきゃ」と思っているのに、カレンダーを見るたびに胃が重くなります。
ある日、勇気を出してカフェに誘ってみました。メッセージを送った直後、スマホの画面が暗くなる度にドキドキが止まりませんでした。既読がついてから返事が来るまでの30分間、冷蔵庫の氷を何個も頬に当てていました。返信の「いいね!楽しみ😊」スタンプを見た瞬間、逆に「楽しませなきゃ」という義務感がのしかかりました。
当日、おしゃれなカフェのテラス席で手帳を広げながら、話題のリストを確認していました。自然な会話の流れを作るために、前日から考えたネタが20項目もありました。友達が「最近どう?」と聞いてくれたとき、用意していた話題を順番に話している自分に気付きました。帰り道、「楽しかったね」と言われたのに、なぜか虚しさが残りました。
次の誘いを考えるたびに、前回以上の準備が必要に感じられます。SNSでいいねを押すタイミングさえ計算してしまうようになりました。ある夜、ベランダで星空を見上げながら、「このままじゃ友情が義務になってしまう」と呟いていました。遠くの星が瞬くように、心の奥で何かが揺らいでいるのを感じました。
「人間関係=しんどい」が刷り込まれていた
小学校の教室で、グループ分けのときに最後まで選ばれなかった日のことを、今でも鮮明に覚えています。チョークの粉が舞う空気の中、先生が「じゃあこっちの組に入りなさい」と指差した瞬間、頬が火照りました。それ以来、休み時間の度にトイレの個室で過ごすようになりました。
中学時代の文化祭で、劇の台本を任されたことがありました。一生懸命書いたのに、主演の子が「これじゃやりにくい」と文句を言ったのです。放課後の教室で一人で台本を書き直しながら、涙が原稿用紙を濡らしました。それ以来、自分の意見を言うのが怖くなりました。
アルバイト先の先輩に「なんか暗いね」と言われた日、帰り道でずっと下を向いて歩いていました。アパートの階段を上りながら、「私の存在そのものが周りを不快にさせてるんだ」と思い込んでしまいました。次の日からメイクを濃くして、無理に笑顔を作る練習を始めました。
結婚式の二次会で、突然スピーチを振られたことがあります。立ち上がった瞬間、足がガクガク震えて、声が裏返りました。周りの笑い声が、嘲笑に聞こえてしまいました。それ以来、人前で話すときは必ず手の平に爪を立てて、痛みで緊張を紛らわせるようになりました。
心地よい距離感って、どうやってつくるの?
図書館で借りた心理学の本に「パーソナルスペース」の図解があった日、電車の優先席に座る位置を変えてみました。他人との物理的な距離を意識することで、不思議と心の余裕が生まれるのを感じました。隣の人の鞄が触れそうになると、そっと席をずれる練習を始めたのです。
メールの返信時間を「最短2時間後」と自分ルールを決めました。即答しなければいけないという焦りが減り、文面を落ち着いて考えられるようになりました。ある日、友達から「返信遅くてごめん」とメッセージが来たとき、「私もゆっくりで大丈夫だよ」と返せるようになっていました。
飲み会の誘いには「今回は遠慮します」の一言を覚えました。最初は罪悪感でいっぱいでしたが、3回目くらいから相手も自然に受け入れてくれるようになりました。ある日、主催者が「無理しないでね」と付け加えてくれたとき、初めて「断っても大丈夫なんだ」と実感できました。
趣味の陶芸教室で、隣の人と作品を見せ合うのが楽しみになりました。作陶中の無言の時間が、かえって心地よい繋がりを感じさせてくれたのです。窯から取り出した湯飲みの欠けらさえも、今では愛おしい思い出の一部です。
第8章のまとめ
この章を書き終えて、窓の外で桜の花びらがひらひら舞うのを見つめています。去年の今頃は、花見の誘いをどう断ろうかと悩んでいたのに、今年は「午前中だけなら」と参加してみました。満開の桜の下で、知り合いと少し距離を置いて座っているのが、意外にも居心地良かったのです。
先週、久しぶりに旧友と会いました。以前なら3時間も話した後にぐったりしていたのに、今回は「またね」と軽く別れることができました。駅のホームで電車を待ちながら、自分の成長に気付いて、ふと笑みがこぼれました。
最後に、この文章を読んでいるあなたへ。きっとあなたも、人間関係の迷路で何度も躓いてきたのでしょう。でも大丈夫。ほら、今この瞬間もあなたは呼吸をしています。それだけで十分、明日への一歩を踏み出せている証拠です。無理に近づかなくても、遠ざかりすぎなくてもいい。丁度いい距離を見つける旅は、まだ途中なのですから。春風が頬を撫でるように、ゆっくりと進んでいきましょう。
第9章:わたしと他人の境界線
「嫌われたくない」が全ての判断軸だった
24歳の誕生日、私は自分が選んだケーキを食べられませんでした。友達が「せっかくだからサプライズで!」と、苦手なチョコレートケーキを用意してくれたからです。フォークの先が震えながら、私は笑顔で「おいしい!」と繰り返していました。喉の奥で甘さが苦味に変わる感覚を、紅茶で必死に流し込んだのです。
その夜、キッチンのシンクで食器を洗いながら、ふと涙がこぼれました。リビングに残ったろうそくの匂いが、自分の中に巣くう「いい人」の仮面を炙り出しているようでした。翌日、SNSに投稿された誕生日の写真に、みんなから「幸せそう!」のコメントが並びました。でも、写真に写った自分の笑顔が、なぜか他人のように見えたのです。
仕事の打ち合わせでは、いつも「どちらでもいいです」が口癖でした。同僚が「A案とB案、どっちがいい?」と聞くたび、相手の目を盗んで呼吸を整えていました。ある日、先輩に「君の本音が知りたいんだ」と言われ、初めて「実は…」と意見を伝えたら、「そういう考え方もあるね」と受け止めてくれたのです。そのとき、胸のあたりにあった重い石が、少しだけ転がり落ちるのを感じました。
相手の感情に飲まれて、自分を見失う
カフェで友達が彼氏の愚痴をこぼし始めたとき、コーヒーカップの縁に指紋がくっきり付きました。彼女の怒りの波動が、私の胃のあたりをぎゅっと締め付けます。「私も同じ経験あるよ」と共感しながら、実は昨日から頭痛がしていたことには触れませんでした。帰り道、駅の階段で足が止まり、なぜかホームのベンチで30分も座り込んでしまいました。
家族の集まりで、姉が母に反抗的な態度を取ったときのことです。リビングの空気が一瞬で凍りつき、食卓の上のサラダボウルが歪んで見えました。母の沈黙と姉のため息の間で、私は無意識に「ねえ、このお魚おいしいよ」と話題をそらしていました。深夜、布団の中で自分の小さな声が繰り返されます。「本当は止めたかった。本当は何も言いたくなかった」。
あるプロジェクトで、クライアントの機嫌を損ねないようにと、3日連続で午前3時まで作業していました。4日目の朝、パソコンの前で意識がふっと遠のき、キーボードに額をぶつけました。鏡に映った目の下のクマが、他人の期待に押しつぶされそうな自分を嘲笑っているようでした。
嫌なことを「嫌」と言えない苦しさ
歯医者の予約を5回もキャンセルしたことがあります。毎回「また日程調整しますね」と嘘をつき、受話器を置くたびに自己嫌悪に襲われました。6回目、歯がズキズキ痛みだしたとき、ようやく「実は…歯医者が怖いんです」と打ち明けました。受付の女性が「大丈夫ですよ、ゆっくり来てくださいね」と言ってくれた声が、なぜか涙を誘いました。
ママ友グループのランチで、苦手なエビ料理が出た日です。アレルギーではないのに「食べられない」と言えず、一口ずつ時間をかけて噛んでいました。喉が締め付けられる感覚の中、誰かが「おいしいね」と言うたびに、無理やり笑顔を作っていました。帰宅後、洗面所で吐いたとき、初めて「自分を傷つけてまで合わせる必要はない」と気付いたのです。
上司の飲み会の誘いを断れず、体調不良で早退したことがあります。タクシーの窓に頬を押し付けながら、街灯の光が涙に滲んで見えました。翌日「楽しみにしてたのに」と言われ、また謝罪の言葉を並べる自分がいました。エレベーターの鏡に映った青白い顔が、「あなたはもう限界よ」と囁いているようでした。
心の境界線を引くってどういうこと?
図書館で借りた心理学の本に「境界線は優しさの柵」と書いてありました。最初は意味がわかりませんでした。ある雨の日、隣の席の同僚が私の資料を無断でコピーしたとき、「それ、許可取ってくれますか?」と言ってみたのです。声が震えていたのに、同僚は「ごめん、悪い癖なんだ」と笑って謝ってくれました。そのとき、柵の向こうから差し伸べられた手のような温かさを感じたのです。
友達とのLINEの返信が遅くなったとき、「既読スルーしたと思われたらどうしよう」と焦る代わりに、小さなスタンプを送ってみました。既読がついてから2時間後、「ゆっくりでいいよ」の返事が来たとき、画面の光が優しく包み込んでくれるようでした。
今では、苦手な誘いが来たら「今回は遠慮します。また誘ってね」と返す練習をしています。最初は心臓がバクバクしましたが、5回目くらいから相手も自然に受け入れてくれるようになりました。先週、主催者が「無理しないでね」と付け加えてくれたとき、境界線の向こう側にも優しさがあることを知りました。
夜、ベランダで星空を見上げながら思います。境界線とは、他人を遠ざける壁ではなく、自分を守るための柔らかい柵なのだと。月明かりが、そっと心の柵を銀色に縁取ってくれるようでした。
「わたしの気持ちを優先してもいい」と思えた日
雨の降る木曜日の午後、私は初めて「NO」と言いました。同僚の飲み会の誘いを、震える手でメッセージを打ったのです。「今日はちょっと…」と送信ボタンを押した瞬間、心臓が口から飛び出しそうになりました。スマホの画面が暗くなるたびに、既読通知を確認しては深呼吸を繰り返しました。
返信が「了解!また今度ね😊」と返ってきたとき、窓の外を流れる雨粒がキラキラ輝いて見えました。胸の奥で固まっていた氷が、少しずつ溶けていく感覚がありました。その夜、久しぶりに好きな小説を最後まで読み切り、紅茶の香りに包まれながら「これでよかったんだ」と呟きました。
翌日のオフィスで同僚が普通に挨拶してくれたとき、涙が出そうになりました。自分が恐れていた拒絶反応は、全て想像の産物だったと気付いたのです。昼休みに一人で公園を散歩しながら、枯れ葉を踏む音が心地よく響きました。
その日を境に、少しずつ自分の気持ちに耳を傾ける練習を始めました。苦手な飲み物を注文したとき、友達が「そういう好みなんだ」と受け入れてくれたこともありました。夜空の月が欠けていくように、完璧な「いい人」の仮面が剥がれていくのを感じました。
自分と他人は違う…それが安心につながった
友達の家で観た映画の感想が、まるで正反対だった日があります。私は主人公の選択に共感したのに、友達は「理解できない」と言いました。最初は自分の感じ方が間違っているのかと不安になりましたが、翌日メールで「でもあなたの見方も素敵だね」と送られてきて、はっとしました。
カフェのテラスで、知人がコーヒーに砂糖を3杯入れるのを見て驚いたことがあります。私はブラック派なのに、彼女は「甘さが幸せ」とにっこり笑いました。その瞬間、人それぞれの「普通」があることに気付き、なぜかほっとしたのです。
仕事のプレゼンで、上司と意見が対立したときのことです。ドキドキしながら自分の考えを伝えたら、「なるほど、そういう視点も必要だね」と言われました。会議室の窓から差し込む光が、今まで見えなかった角度を照らし出しているようでした。
今では、意見の違いを恐れなくなりました。スーパーのレジで店員さんが間違えたお釣りを渡したとき、そっと指摘できるようになりました。相手の「ありがとう」の言葉が、お互いの違いを認め合う魔法の呪文のように聞こえました。
距離を取る=冷たい、じゃない
ママ友グループのランチに参加する回数を減らした頃、逆に個人的に誘われるようになりました。「無理して来なくていいよ」と言われたとき、初めて本当の安心感を覚えました。公園のベンチで二人きりで話すうちに、深い絆が生まれるのを感じました。
SNSの通知をオフにした最初の週、孤独になるかと思いきや、逆にゆったりとした時間が流れました。インスタグラムの投稿をしなくても、夕焼けの美しさは変わりませんでした。ベランダで育てたパンジーの花が、小さな蕾を開かせるのを見つめる時間が増えました。
親戚の集まりで早めに帰るとき、「体調管理できて偉いね」と叔母に言われたことがあります。その言葉が、距離を取ることが悪いことではないと教えてくれました。帰りの電車で見た満月が、やさしく見守っているようでした。
今では、苦手な人との付き合い方を自分で選べるようになりました。年に数回の挨拶だけの関係も、ある種の心地よさがあることに気付きました。図書館で偶然会った元同僚と、本の話だけで盛り上がった午後は、特別な思い出になりました。
第9章のまとめ
この章を書き終えて、窓の外で風に揺れる洗濯物を見つめています。以前なら「早く取り込まなきゃ」と焦っていたのに、今日は布が踊る様子を楽しんでいます。境界線を引くことは、心の洗濯物を干すような作業なのかもしれません。
先日、友人に「最近のあなた、生きやすそうだね」と言われました。鏡を見ると、眉間の皺が浅くなっているのに気付きました。無理に笑顔を作らなくても、自然な表情でいられることが増えてきたのです。
最後に、この文章を読んでいるあなたへ。きっとあなたも、他人との境界線で何度も迷ったのでしょう。でも大丈夫。ほら、今この瞬間も洗濯物は風に揺れています。少しずつ、自分のペースで柵を編んでいけばいいのです。完璧な境界線なんて必要なくて、ゆるやかな結び目がいつか優しいネットワークになるのですから。
第10章:ひとり時間が教えてくれたこと
ひとりでカフェに行く幸せ
木曜日の午前10時、私はいつものカフェの隅っこ席に座っていました。ガラス越しに差し込む陽光が、マーブル模様のテーブルを優しく撫でています。隣の席で老紳士が新聞を広げる音、奥の厨房から聞こえるコーヒー豆を挽く音、それらがちょうど良い距離感で耳に届きます。メニューを開かなくても、今日はカプチーノに決めていました。泡立て器がカップを叩く軽やかな音が、私だけのためのBGMのように感じられます。
初めてひとりでカフェに入ったのは、20歳の誕生日でした。友達との約束が直前でキャンセルになり、泣きそうになりながら入った小さな喫茶店で、初めて「孤独」と「孤独感」が別物だと知りました。ウエイトレスさんが「お誕生日ならサービスでクッキーどうぞ」と差し出してくれたとき、涙がこぼれそうになったのを覚えています。あの日から、私は週に一度の「カフェひとり時間」を自分の儀式にしました。
今では、季節ごとに通うカフェを変えるのが楽しみです。春は桜の見える窓辺、夏はクーラーの効きすぎないテラス席、秋は落ち葉が舞う公園沿いの席。冬になると、暖炉の近くのソファ席を探します。メニューにない隠しメニューを教えてもらったこともありました。バリスタさんが「いつもコーヒーばかりだから」と、特別にハーブティーをブレンドしてくれたのです。
誰にも気を遣わず、本のページをめくる速度も、コーヒーを飲むペースも全て自分次第。ふと気付くと、2時間も同じ景色を見つめていることがあります。窓の外を通り過ぎる人々の表情が、物語の登場人物のように思えてきます。この時間だけは、他人の感情の波に飲み込まれない、穏やかな海の底にいるような気分です。
雨の音だけ聞いていた休日
台風接近の日曜日、私はカーテンを閉め切った部屋で過ごしていました。ベランダの雨戸が風に揺れる音、雨樋を伝う水の流れる音、遠くで雷が鳴る低い響き。それらが混ざり合って、不思議な安眠音楽を作り出しています。ソファに横たわり、天井のシミをぼんやり眺めながら、時計の針が進むのを感じていました。
こんな日は、普段なら焦ってしまう「何もしない時間」が許されます。読みかけの本を手に取っても、10ページで眠りに落ちても誰にも責められません。冷蔵庫の残り物で作った簡単なスープの味が、なぜか平日の3倍おいしく感じられます。湯気が眼鏡を曇らせるのも、悪くないと思えるのです。
ある梅雨の午後、私は雨音を録音してみました。スマホを窓際に置いて1時間。後でイヤホンで聴くと、実際の雨とは違うリズムが耳に残りました。テレビの音も人の声もない、純粋な自然の音だけの世界。それを聴きながら絵を描いたら、いつもと違う色使いができたのです。雨粒の形をした水色の点描が、画用紙の上で踊りました。
雨の日は、外出できない焦りより、自分と向き合える安らぎを教えてくれます。傘をさす手間も、他人とすれ違う緊張もない。ただひたすらに、自分という器を満たしていく時間。窓ガラスを伝う水滴が、心の曇りを洗い流してくれるようです。
SNSを閉じて見えたもの
ゴールデンウィーク、私は思い切ってSNSアプリを全て削除しました。最初の3日間、手元のスマホが重すぎる異物に感じられました。電車の中でついポケットを探る手、通知がないのに画面を点ける癖。でも4日目、通勤路の桜並木が、いつもより濃いピンクに見えるのに気付いたのです。
カフェのテラスで、隣の席の女性がインスタ映えしそうなパンケーキの写真を撮っているのを見かけました。ふと「私も撮りたかったかも」と思い、でもカメラを向けずにフォークを手に取ったら、蜂蜜の香りがまっすぐ鼻腔に届きました。スマホの画面越しじゃなく、自分の目で見る景色の鮮やかさに驚きました。
2週間後、友達に会ったとき「最近元気?」と心配されました。SNSで近況を共有していないからです。「実はデジタルデトックス中で」と伝えると、彼女は「私もやってみようかな」と呟きました。その夜、手紙を書いてみました。便箋にインクが滲む様子が、既読マークよりずっと温かく感じられました。
今では週末だけSNSを開くようになりました。情報の洪水に溺れなくなり、代わりに現実の小さな発見が増えました。公園のベンチで昼寝する猫の腹の動き、パン屋の新しい看板のフォント、夕暮れ時の街灯の点灯順序。どれも投稿する必要のない、私だけの宝物です。
予定のない日がこんなに安心するなんて
3連休の真ん中の日、私は意図的に予定を空けました。目覚まし時計をかけず、カーテンの隙間から入る光で自然に目が覚めます。枕元のメモには「今日やること:呼吸する」と書いてあります。珈琲を淹れるのに20分かけました。豆を挽く香り、お湯を注ぐ音、ゆっくり膨らむドリップペーパー。
昼過ぎ、ふらりと図書館へ向かいました。目的の本は探さず、ただ棚の間を歩くだけ。背表紙の色のグラデーションが、抽象画のように美しく見えます。3階の窓際で、中学生が一生懸命勉強している横姿を見て、なぜか懐かしい気持ちになりました。
夕方、近所のスーパーでお惣菜を買いました。迷う必要のない選択。鶏のから揚げとポテトサラダ、それにデザートのヨーグルト。レジのおばさんが「ゆっくり過ごしてるね」と笑顔で言いました。その言葉が、今日一日の肯定のように胸に染みました。
夜、ベランダで夜空を見上げながら思いました。予定のない日とは、自分という畑を耕す日なのだと。雑草を抜き、土を柔らかくし、そっと種をまく時間。明日がどんな天気でも、今日の私には静かな恵みが降り注いでいます。
小さな日常のなかの静けさ
朝6時、カーテンの隙間から差し込む薄明かりがゆらめいています。コーヒーミルの音がキッチンに響き、豆を挽くたびに芳ばしい香りが広がります。湯沸かし器の蒸気が天井に触れる音、ドリップするお湯の滴る音。この時間だけは、世界がまだ目覚めきっていないような、柔らかな静けさに包まれています。
通勤路の公園で、ふと足を止めたことがあります。ベンチの脇に咲くタンポポの綿毛が、朝露に濡れて光っていました。誰も気に留めないようなその瞬間が、なぜか胸に深く刻まれました。地面に座り込んで接写してみると、水滴の中に小さな虹が浮かんでいるのが見えました。10分ほど遅刻しましたが、その日の仕事はなぜか冴えわたったのです。
夜の入浴時間は、私だけの瞑想タイムです。湯船に沈めた耳から聞こえる水の音が、海底にいるような安らぎを与えてくれます。シャンプーの泡がはじける音、タイルに伝わる隣の部屋の生活音。全てが遠い世界の出来事のように感じられます。ある晩、湯気に揺れる電球の光を見つめながら、初めて「生きている実感」というものを味わいました。
コンビニの深夜アルバイトで、レジ打ちの合間に気付いたことがあります。店内BGMのない時間帯、冷蔵庫のモーター音と時計の秒針の音がシンクロしているのです。そのリズムに合わせて呼吸していると、なぜか涙がこぼれそうになりました。静寂の中にある秩序が、私の心拍を整えてくれるようでした。
「誰とも話さない」ことの価値
図書館の閲覧室で、3時間誰とも話さずに過ごした日のことです。ページをめくる音、椅子のきしむ音、時折聞こえる深呼吸。それらが心地よい白噪音のように感じられました。帰り際、司書さんと目が合って軽く会釈したとき、言葉を超えた通じ合いを感じたのです。
歯科医院の待合室で、雑誌を読まずに窓の外を見つめていました。ビルの谷間を飛ぶ鳩の群れが、突然旋回する様子に引き込まれます。受付の女性が「お待たせしました」と呼ぶ声が、なぜか優しく聞こえました。治療中も、ずっとあの鳩の動きを思い出していました。痛みよりも先に、羽ばたく音が頭に残ったのです。
オンライン会議が続いたある日、意図的にマイクをオフにしてみました。相手の話にうなずく代わりに、手帳に落書きをしながら聞きます。ふと窓の外に目をやると、蜘蛛の巣に引っかかった葉が風に揺れていました。その瞬間、議論の内容が突然クリアに理解できたのです。沈黙が思考を整理してくれることを学びました。
夜の散歩で、たまたま入った銭湯で気付きました。浴室の湯気の中、誰も他人と話さずに自分の体と向き合っています。湯船に浸かる時のため息が、共鳴し合うように聞こえました。言葉ではない、肉体の声が交わる空間。帰り道、道端の猫に「おやすみ」と呟いた自分の声が、驚くほど柔らかく響きました。
ひとり=孤独、ではなかった
美術館で、好きな絵の前に1時間も佇んでいたことがあります。最初は周りの視線が気になりましたが、次第に絵の具の盛り上がりや筆の跡に引き込まれていきました。ふと気付くと、隣に立っていた老婦人と同時にため息をついていました。言葉を交わさなくても、同じ美しさを分かち合える瞬間があるのです。
新型のカフェで、隣の席の客と偶然同じ本を読んでいた日です。お互い気付いていながら、最後まで話しかけませんでした。帰り際に本を鞄にしまうタイミングがぴったり合い、思わず笑みが漏れました。その夜、読み終えた本の最後のページに、見知らぬ人との奇妙な絆を感じたのです。
夜行バスの車窓から、流れ星を見つけたことがあります。叫びたい衝動を抑え、そっと手を合わせました。前の席で寝息を立てていた大学生が、ちょうどその時咳払いをしました。誰にも話さないその瞬間が、特別な共有体験のように思えました。
図書館の同じ席で3日連続で会う女性と、4日目に目配せを交わしました。5日目、彼女が席を立つ際に置いていった栞が、私の読んでいた本のものと同じだと気付きました。以来、私たちは毎朝会釈を交わすようになり、それが朝のルーティーンになりました。言葉のない交流が、かえって深い信頼を築くことを教わりました。
第10章のまとめ
この章を書き終えて、窓の外で夕焼けが街を染めています。オレンジ色の光がビルのガラスに反射し、無数の小さな太陽が生まれています。以前なら「写真に収めなきゃ」と焦っていたのに、今はただこの瞬間を味わっています。
先日、久しぶりに友人と会ったとき、「あなた落ち着いたね」と言われました。鏡を見ると、確かに眉間の皺が浅くなっていました。無理に会話を埋めようとしなくても、沈黙が心地よいことを知ったからかもしれません。
最後に、この文章を読んでいるあなたへ。きっとあなたも、孤独と静寂の違いに気付き始めているのでしょう。どうか、ひとりの時間を恐れないでください。静けさの中には、自分という楽器を調律する音色が潜んでいます。今日という日の終わりに、そっと耳を澄ませてみてください。あなただけの旋律が、きっと聞こえてくるはずです。
第11章:心の声を聞く練習
頭の中にずっと誰かの声がいた
私の場合は、朝起きてから夜眠るまで、頭の中にいろんな声が響いていました。職場の上司の声、母の声、友達の声。ときどきは、もう何年も会っていない誰かの声まで、ふいに思い出したように現れてきます。「それで本当に大丈夫?」「もっと頑張ったほうがいいんじゃない?」「そんなことしたら嫌われるよ」–そんな言葉が、まるで自分の本心のように聞こえていました。
学生時代、授業中にノートを取る手が止まったとき、「ちゃんとしなさい」「気を抜くな」という先生の声が頭の中で響きました。大人になっても、その声は形を変えて私の中に残り続けました。新しい仕事を任されたとき、最初に浮かぶのは「失敗したらどうしよう」という不安と、「期待に応えなきゃ」という焦りでした。自分の気持ちよりも、他人の期待や評価が優先されてしまう。そんな毎日が、いつの間にか当たり前になっていました。
ある日、友達とカフェで話していたとき、「最近、自分が何をしたいのかわからなくなることが多いんだ」と打ち明けました。友達は「それ、私もあるよ」と言いながら、「でも、ちゃんと自分の声を聞いてあげてる?」と聞いてきました。そのとき、私ははっとしました。自分の声って、どんな声だったんだろう。思い返してみても、いつも他人の声にかき消されて、自分の本音がどこにあるのかわからなくなっていたのです。
夜、ベッドの中で目を閉じてみると、頭の中がざわざわしていました。今日一日で言われたこと、やらなきゃいけないこと、気をつけるべきこと……。そのすべてが、私の心の中で大きな音を立てていました。静かなはずの夜なのに、心はまるで満員電車のようにぎゅうぎゅう詰めでした。
「本当はどうしたい?」が答えられなかった
「本当はどうしたい?」と聞かれて、すぐに答えられる人はどれくらいいるのでしょうか。私の場合は、いつも答えに詰まってしまうタイプでした。友達とランチに行くときも、「何食べたい?」と聞かれて「なんでもいいよ」と答えてしまう。仕事で新しいプロジェクトに誘われたときも、「やってみたい?」と聞かれれば「うん」と言いながら、本当はどうしたいのか自分でもわかっていませんでした。
ある日、カウンセリングを受ける機会がありました。カウンセラーの先生が、「じゃあ、あなたはどうしたいですか?」と優しく聞いてくれました。でも、そのとき私は、何も答えられませんでした。頭の中では「こうしたほうがいい」「こうしたら喜ばれる」「こうしたら嫌われない」という条件ばかりがぐるぐる回っていて、自分の「したい」がどこにも見つからなかったのです。
それに気づいたとき、少しだけ悲しくなりました。私はずっと、誰かの期待に応えようと頑張ってきたけれど、自分の気持ちを置き去りにしてきたのかもしれない。そう思ったら、胸の奥がきゅっと痛くなりました。
その夜、自分に「本当はどうしたい?」と問いかけてみました。でも、すぐに答えは出てきませんでした。代わりに、「こうしなきゃ」「こうあるべき」という声が、また頭の中で響きました。私はそっと目を閉じて、しばらく呼吸を整えました。自分の中にある「したい」という気持ちが、どこかに隠れているのだとしたら、そっと探しに行こう。そんなふうに思いました。
不安の奥にある“小さな本音”
「不安」という感情は、ときどき本音を隠すカーテンのように感じます。たとえば、友達に誘われて出かけるとき、「断ったら嫌われるかも」と不安が膨らみます。でも、その奥には「今日はひとりで過ごしたい」という小さな本音が隠れていることがあるのです。
仕事で新しいことにチャレンジするとき、「失敗したらどうしよう」「みんなに迷惑をかけたらどうしよう」という不安が先に立ちます。でも、その奥には「本当はやってみたい」「自分の力を試してみたい」という気持ちが、そっと息をひそめていることもあるのです。
私はある日、ノートに「不安」と「本音」を書き分けてみました。「断ったら嫌われるかも」と書いた横に、「本当は今日は家でゆっくりしたい」と書く。「失敗したらどうしよう」の横に、「でもやってみたい」と書く。そうやって、少しずつ自分の本音を見つけていく練習を始めました。
最初はうまくいきませんでした。不安の声のほうが大きくて、本音がかき消されてしまうことも多かったです。でも、何度も繰り返しているうちに、不安の奥で小さく手を振っている自分の気持ちに気づけるようになってきました。「本当はこうしたいんだ」と思えたとき、心の中に小さな灯りがともるような感覚がありました。
心の声は、最初はとても小さい
心の声は、最初は本当に小さくて、かすかな囁きのようです。テレビの音や、スマホの通知音、誰かの話し声に簡単にかき消されてしまいます。だから、私は意識的に「静かな時間」を作るようになりました。
朝のまだ誰も起きていない時間、カーテンを開けて外の空気を吸い込む。夜、寝る前に部屋の明かりを落として、深呼吸をする。そんな時間の中で、ふと「今日はこれがしたいな」「この本を読んでみたいな」という小さな声が聞こえてくるのです。
ある日、散歩をしていたとき、道端に咲いている小さな花に目が留まりました。「きれいだな」と思ったその瞬間が、私の心の声でした。誰かに見せるためでも、写真を撮るためでもなく、ただ「きれい」と感じた自分の気持ち。それが、心の声なのだと気づきました。
心の声は、最初はとても小さいけれど、聞こうとすれば必ずどこかにあります。忙しい日々の中で、ふと立ち止まって耳を澄ませてみる。そうやって少しずつ、自分の本音をキャッチする練習を続けています。心の声を聞くことは、自分を大切にする第一歩なのだと、今は思えるようになりました。
書き出すことで本音が見えてくる
ある雨の土曜日、私は引き出しの奥から革表紙のノートを取り出しました。最初のページを開くと、5年前に書いた「今日の目標:笑顔を絶やさない」という文字が目に飛び込んできました。その下には、びっしりと他人からの評価を気にするメモが書き連ねられていました。ペンを握りしめ、今日の日付を書いた瞬間、滝のように言葉が溢れ出したのです。
「実はあの時、すごく傷ついていた」
「本当は参加したくなかった飲み会」
「上司の言葉をずっと引きずっている」
書きなぐる文字は震えていましたが、ページが進むにつれて次第に整っていきました。3日目、ふと気付くと「私って本当は〇〇が好きだったんだ」という文が散見されるようになりました。インクの滲みが涙の跡のようにも見えました。
ある晩、書き終えたノートをパラパラめくっていると、特定の単語が繰り返されていることに気付きました。「疲れた」「一人になりたい」「本が読みたい」。それらの言葉を繋ぎ合わせると、私の本音の地図が浮かび上がってきました。翌日、図書館で借りた本のタイトルが、偶然その地図の目的地を示しているように感じられたのです。
今では、朝起きて最初の5分間を「脳内掃除タイム」にしています。枕元のメモ用紙に頭に浮かぶままの言葉を書き連ね、後でゆっくり読み返します。先週のメモに「コーヒーより紅茶が飲みたい」と書いてあったので、思い切ってカフェでオーダーしてみました。温かいカップの感触が、自分を認める悦びを教えてくれました。
嫌な気持ちを“否定しない”ことの大切さ
電車で隣の人の香水がきつくて、思わず席を立った日がありました。以前なら「我慢すべきだ」と自分を責めていたでしょう。でもその日は、心の中で「今の私はこの香りが苦手なんだ」とつぶやいてみました。ホームのベンチに座り、次の電車を待ちながら、なぜかほっとした息が漏れました。
友達の冗談に傷ついたとき、無理に笑う代わりに「今ちょっと複雑な気分なんだ」と伝えてみました。相手は驚いた顔をしましたが、「教えてくれてありがとう」と言ってくれました。その夜、鏡の前で自分の表情を観察していると、無理な笑顔よりも少し曇った顔の方が愛おしく見えました。
ある朝、目覚まし時計を投げつけそうになった自分に気付きました。枕元のメモに「朝が苦手なんだ」と太字で書いて貼っておきました。次の日から15分早く寝るようにしたら、時計の音が優しい目覚ましに変わりました。
今では、イライラしたときは台所で氷を握りしめます。冷たさが手のひらを刺激しながら、「今私は怒っているんだ」と実感させてくれるのです。溶けていく氷と共に、感情も少しずつ和らいでいきます。冷蔵庫の野菜室で偶然見つけた皺くちゃな人参が、なぜか愛嬌たっぷりに見えた日もありました。
正直であることが、怖くなくなった日
ママ友のランチ会で、「実は子育ての話ばかりだと疲れる」と打ち明けたことがあります。沈黙が流れた後、誰かが「私もそう思ってた」と囁き、みんなで笑い合いました。その後の話題は本や映画に移り、なぜか以前より深い話ができるようになりました。
職場で「無理です」と初めて言えた日、窓の外で雀が勢いよく飛び立つのを見ました。上司は少し不機嫌そうでしたが、翌日には別のメンバーをアサインしてくれました。その夜、いつもより深く眠れた気がしました。枕カバーの匂いが、なぜか懐かしい子どもの頃の布団を思い出させました。
先月、友人に「あなたと話すと疲れるときがある」と伝えました。ドキドキしながらも、後半に「でもあなたの存在は大切だよ」と付け加えました。友人はしばらく考えて、「もっとお互い楽になれる方法探そう」と言ってくれました。その後のカフェでの会話が、なぜか以前より軽やかに感じられました。
先日、道に迷っている人に「私もよくわからないんです」と正直に答えました。すると相手が「そうですか、じゃあ一緒に探しましょう」と笑顔で返してくれたのです。結局二人で看板を探し、無事目的地に着いたとき、正直でいることの清々しさを味わいました。
第11章のまとめ
この章を書き終えて、窓の外で夕立が上がりました。雨上がりのアスファルトに映る虹を見つめながら、自分の心もこんな風に色づいていくのだと思いました。最初はかすかだった本音の声が、少しずつ鮮やかな色を持ち始めているようです。
先日、久しぶりに会った姉に「あなた変わったね」と言われました。鏡を見ると、確かに目元の力が抜けているのに気付きました。無理に笑顔を作らなくても、自然な表情でいられることが増えてきたのです。
最後に、この文章を読んでいるあなたへ。きっとあなたも、心の声に耳を澄ませる練習を始めているのでしょう。どうか焦らないでください。ほら、今この瞬間もあなたの胸の奥で、小さな声が息をしています。その声がどんなに小さくても、きっとあなただけの色を持っているはずです。ゆっくり、ゆっくり、その声に色を塗っていけばいい。いつかきっと、虹のように鮮やかな自分の声と出会える日が来ますから。
第12章:自分を守るために、手放したもの
無理な付き合いはやめた
金曜日の夜7時、スマホが震えて友達からのメッセージが届きました。「今から飲みに行かない?」画面の光が暗い部屋でぼんやり浮かび、左手の指がぎゅっと鞄の紐を握りしめました。この1週間、毎日残業が続いていたのに、断る言葉が喉に引っかかります。「ごめん、今日はちょっと…」と打ち始めた指が止まり、結局「楽しそう!行くよ」と送信してしまったあの日のことを思い出しました。
翌朝、鏡に映った顔が鉛色になっているのを見て、決心しました。次の誘いが来たとき、深呼吸してから「今回は遠慮するね」と返信しました。既読がついてから返事がない10分間、冷蔵庫の氷を頬に当てながら過ごしました。返ってきたのは「了解!また今度」のスタンプだけ。その夜、初めて8時間続けて眠れたのです。
ある春の日、ママ友グループの昼食会を欠席しました。公園のベンチでおにぎりを食べながら、子供たちの笑い声を遠くから聞いていると、なぜか涙がこぼれました。これまで我慢してきた「空気を読むエネルギー」が、どれほど大きかったかに気付いたからです。帰宅後、グループチャットの通知をオフにしました。翌週、誰も何も言わないことに、逆にほっとしました。
今では、月に一度の「ひとりカフェデー」を大切にしています。最初は罪悪感に苛まれましたが、3回目からは珈琲の香りが以前より深く感じられるようになりました。窓越しに見える通行人の表情が、なぜか優しく見えるのです。
心がざわつくSNSから距離を置いた
ある朝、インスタグラムを開いたまま電車を乗り過ごしたことがありました。キラキラした投稿の洪水に飲まれ、自分の日常が色褪せて見えたのです。その晩、ベッドでスマホを握りしめ、「いいね」の数を確認する自分に嫌気が差しました。
完璧な“いい人”を演じるのをやめた
同僚の誕生日プレゼントを選ぶのに、3時間もデパートを彷徨ったことがありました。相手の好みをリサーチし、予算を計算し、包装紙の色まで悩み抜きました。でも当日、渡した瞬間の同僚の「え、結構ですよ」という言葉に、心が砕けそうになりました。帰りの電車で、プレゼント袋のリボンが緩んでいくのを見ながら、自分がどれだけ無理をしていたかに気付いたのです。
ある日、ママ友の愚痴を2時間聞いた後、頭痛がひどくて寝込んでしまいました。それまで「聞いてあげないと」と思い込んでいましたが、その日を境に「今日はちょっと無理かも」と言えるようになりました。最初は相手が不機嫌になるのではと心配でしたが、逆に「いつもありがとう」と言われたとき、本当の優しさとは違うのだと悟りました。
飲み会で苦手な話題が始まったとき、無理に合わせる代わりに席を外してみました。トイレの鏡で深呼吸していると、隣の個室から「私も疲れてたんだ」と誰かの呟きが聞こえました。戻ると、誰も私の不在に気付いていませんでした。その事実が、なぜか清々しい発見に感じられたのです。
今では、苦手な人に無理に笑顔を作らなくなりました。代わりに、自然な表情で「今日は調子どう?」と聞けるようになりました。相手の反応が冷たくなっても、それは私のせいではないと学んだからです。喫茶店の窓ガラスに映った自分の顔が、以前よりずっと柔らかく見えるようになりました。
我慢は美徳じゃないと気づいたとき
頭痛がする日も、熱がある日も、会社を休めないと思い込んでいました。ある朝、39度の熱でふらつきながら出勤し、エレベーターで倒れそうになったのです。上司が「そんな状態で来る方が迷惑だ」と叱責した言葉が、逆に解放へのきっかけになりました。翌日から、体調不良はきちんと休むと決めたのです。
歯の痛みを3ヶ月我慢した末、神経を抜くことになった経験があります。治療台で「もっと早く来れば良かったですね」と歯科医に言われたとき、我慢することがどれほど自分を傷つけるか実感しました。それ以来、身体のSOSサインを無視しないようになりました。
ある雨の日、重たい荷物を持ちながら傘をさす友達を手伝おうとして、自分の鞄を濡らしてしまいました。家に着いてから「手伝ってと言ってよ」と伝えると、友達は驚いた顔で「あなたも大変だったのに」と返しました。そのとき初めて、助けを求めることが相手への信頼だと気付いたのです。
今では、電車で席を譲られても「大丈夫です」と断れるようになりました。以前なら「悪いから座らなきゃ」と思っていましたが、疲れているときは素直に「ありがとう」と言います。譲ってくれた人の笑顔が、偽りのない優しさだとわかったからです。
やめてみたら、思ったより世界は優しかった
SNSの通知をオフにした最初の1週間、孤独感に襲われました。でも2週間目、公園のベンチでスズメのさえずりに耳を澄ませていると、心臓の鼓動が穏やかになるのを感じました。地面に落ちた銀杏の実を拾い、ポケットに入れて帰るのが新しい楽しみになりました。
飲み会を断り続けたら、逆に個人的に誘われるようになりました。小さなバーで2人きりで話すうちに、表面的な付き合いでは気付けなかった共通点が見つかりました。氷がグラスで転がる音が、なぜか以前より鮮明に聞こえるようになりました。
「すぐ返信しなくていい」と自己許可したら、メッセージの返信が遅れても誰も怒らないことに気付きました。ある日、3日経ってから「ごめん、元気だった?」と返したら、「心配してたよ」という返事が来て、温かい気持ちになりました。
図書館で借りた本の返却期限を過ぎたとき、正直に「読み終わらなかったんです」と伝えました。司書さんが「また借りに来てくださいね」と笑顔で言ってくれたのが、なぜか目頭を熱くさせました。罪悪感ではなく、許される心地よさを初めて知った瞬間でした。
第12章のまとめ
この章を書き終えて、窓の外で桜の花びらが舞うのを見つめています。去年の今頃は、花見の誘いに必死で参加していましたが、今年はベランダでひとりお茶を淹れています。隣家から聞こえる子供の笑い声が、遠くの祭りのように心地よく響きます。
先日、街中で倒れている人を助けたことがあります。以前なら「見て見ぬふりをするべきか」と悩んだでしょうが、今は迷わず駆け寄れました。自分を守ることを学んだからこそ、本当に必要な優しさがわかるようになったのです。
最後に、この文章を読んでいるあなたへ。きっとあなたも、たくさんの「やらなきゃ」を背負ってきたのでしょう。でも大丈夫。ほら、今この瞬間も春の風が頬を撫でています。手放した分だけ、新しいものが手に入るのだと気付いたら、少しずつ荷物を降ろしていけばいい。枯れ葉が土になるように、捨てたものはいつか優しい栄養になるのですから。
第13章:わたしにとっての“安心”とは
安心できる人のそばにいること
私の場合は、安心できる人のそばにいる時間が、何よりも心の支えになってきました。たとえば、静かなカフェの窓際で、友達と向かい合っておしゃべりしているとき。話題は取り立てて特別なことじゃなくて、昨日見たドラマの話とか、最近お気に入りのカフェの話とか。そんな、なんでもない時間が、心の奥までじんわりと温かくなるのです。
思い返せば、私はずっと「誰かの目」を気にしながら生きてきました。うまく会話できているかな、変なこと言ってないかな、相手は退屈していないかな。そんなふうに、頭の中でぐるぐる考え続けてしまうのが私の癖です。だけど、ごくたまに、「この人の前なら、素の自分でいても大丈夫」と思える人に出会うことがあります。
その人の前だと、言葉を選ばなくてもいいし、沈黙が怖くない。むしろ、静かな時間さえも心地よく感じられます。相手がコーヒーを飲みながら、ふっと窓の外を眺めている。その横顔を見ているだけで、なんだか自分も呼吸が深くなるのです。
初めて「安心できる人」に出会ったのは、大学時代のことでした。新しい環境に馴染めず、毎日どこか緊張していた私に、ひとりの先輩が声をかけてくれました。「疲れてる?」と、ただそれだけ。だけど、その一言に、私は思わず涙がこぼれそうになりました。自分でも気づかなかった心の疲れを、そっと見抜いてくれたような気がしたのです。
それ以来、私は「この人といるときだけは、無理しなくていい」と思えるようになりました。言いたいことがうまく言えなくても、笑顔がぎこちなくても、全部まるごと受け止めてくれる。そんな存在が、私にとっての「安心」の始まりでした。
大人になってからも、安心できる人はそう多くはありません。でも、数は少なくても、たった一人でも「この人の前なら大丈夫」と思える人がいるだけで、世界が少しだけ柔らかく見える気がします。
安心できる人のそばにいると、心の鎧がゆっくりとほどけていきます。自分の弱さも、情けなさも、全部見せてもいいんだと、やっと思えるのです。そんなとき、私はやっと「私自身」に戻れる気がします。
もし今、あなたのそばに、安心できる人がいなかったとしても大丈夫です。私もずっと、ひとりで不安を抱えていた時期がありました。でも、心を開いて少しずつ人と関わっていくうちに、「この人なら大丈夫かもしれない」と思える瞬間が、必ずやってきます。
安心できる人のそばにいること。それは、私にとって「生きていてもいいんだ」と思わせてくれる、何よりも大切な時間です。
決まりきった朝のルーティン
私には、毎朝決まってやることがあります。目覚ましが鳴ったら、まずカーテンを少しだけ開けて、外の光を部屋に入れます。まだ眠そうな空気の中で、窓の外の空をぼんやり眺めるのが、私の一日の始まりです。
それから、ゆっくりとベッドから起き上がり、キッチンでお湯を沸かします。お気に入りのマグカップに紅茶のティーバッグを入れて、静かにお湯を注ぐ。その間、何も考えずに湯気を見つめていると、心が少しずつ落ち着いてきます。
朝ごはんは、トーストとヨーグルト。それだけのシンプルなメニューでも、「今日もちゃんと自分を労わってあげよう」と思えるのです。テレビをつけたり、スマホを見たりしないで、ただ静かに朝の空気を味わう。そんな時間が、私にとっては小さな「安心」の儀式でした。
昔は、朝がとても苦手でした。目覚めた瞬間から、今日も何か失敗するんじゃないか、誰かに迷惑をかけるんじゃないかと、不安でいっぱいだったのです。でも、あるとき気づきました。朝の過ごし方を少し変えるだけで、一日の心の調子がずいぶん違ってくることに。
それからは、どんなに忙しい日でも、朝のルーティンだけは崩さないようにしています。たとえば、外が雨の日も、晴れの日も、同じようにカーテンを開けて、同じように紅茶を淹れる。それだけで、心が「今日も大丈夫」と言ってくれる気がするのです。
決まりきった朝のルーティンは、私にとって「自分を守る小さな盾」のようなものです。どんなに外の世界がざわざわしていても、ここだけは変わらない。そんな場所があるだけで、私は安心して一日を始められるのです。
もし、あなたが今、朝が苦手だったり、不安でいっぱいだったりするなら、ほんの小さなことでいいので、毎日繰り返せる「自分だけの朝の習慣」を作ってみてください。好きな音楽を一曲聴くでもいいし、窓を開けて深呼吸するでもいい。決まりきったことを繰り返すことで、心は少しずつ「大丈夫」を覚えていきます。
決まりきった朝のルーティン。それは、私が「今日も私でいられる」と思える、静かで優しい時間です。
「これがあれば大丈夫」というアイテム
私には、「これがあれば大丈夫」と思えるお守りのようなアイテムがいくつかあります。たとえば、小さなハンカチ。お気に入りの色と、やわらかな手触り。ポケットにそっと忍ばせておくだけで、外の世界に出ていく勇気が湧いてきます。
子どもの頃から、私は何かに触れていると落ち着くタイプでした。授業中、緊張して手が震えるときは、制服の袖をぎゅっと握りしめていました。大人になってからも、その癖はずっと変わりません。だから、外出するときは必ず、手触りのいいハンカチや、好きな香りのハンドクリームをバッグに入れて出かけます。
ある日、友達と待ち合わせをしていたとき、急に不安になってしまったことがありました。人混みの中で、うまく呼吸ができなくなって、心臓がドキドキしてきて。そんなとき、ポケットの中のハンカチをそっと握りしめました。すると、手のひらに伝わる柔らかさが、少しずつ私の心を落ち着かせてくれたのです。
「これがあれば大丈夫」というアイテムは、人によって違うと思います。私の友達は、小さなぬいぐるみのキーホルダーをバッグにつけています。別の友人は、好きな香りのリップクリームを持ち歩いているそうです。どんなものでも、自分が「これさえあれば」と思えるものがあれば、それが心の支えになります。
私は、そういう「お守りアイテム」を持つことは、決して子どもっぽいことじゃないと思っています。むしろ、大人になればなるほど、そういう小さな安心が必要になる気がします。忙しい毎日の中で、自分だけの「安心」を持ち歩くこと。それは、自分を大切にするための、ささやかな工夫なのです。
もし、今あなたが「不安で仕方ない」と感じるときがあったら、ぜひ「これがあれば大丈夫」と思えるものを探してみてください。お気に入りのペンでも、手帳でも、アクセサリーでも。自分だけの「安心」をそっとポケットに忍ばせておくことで、世界が少しだけ優しく見えるかもしれません。
「これがあれば大丈夫」というアイテム。それは、私が外の世界に出ていくときの、小さな勇気の源です。
スケジュールを空白にする勇気
私は、予定がぎっしり詰まっていると、心がどんどん苦しくなっていきます。カレンダーにたくさんの予定が書き込まれていると、それだけで息苦しくなってしまうのです。昔は、「予定がないとダメな人間だ」と思い込んでいました。友達と会う約束、仕事の締め切り、家族の用事。全部をきちんとこなしていないと、自分の存在価値がなくなってしまうような気がしていました。
でも、あるときふと、「何も予定がない一日」があってもいいんじゃないかと思うようになりました。最初は、空白のスケジュールを見るだけで不安になりました。「こんなに暇でいいのかな」「誰にも必要とされていないみたい」と、心がざわざわしました。
それでも、勇気を出して、週に一度だけ「何も予定を入れない日」を作ってみました。朝起きて、窓の外を眺めて、好きな音楽を聴きながらゆっくり朝ごはんを食べる。誰にも会わず、誰とも話さず、ただ自分のペースで一日を過ごす。そんな日が、思っていたよりもずっと心地よかったのです。
空白のスケジュールは、私に「自分のための時間」をくれました。何もしなくてもいい、何かをしなければいけないというプレッシャーから解放される。その自由さが、私の心をふわっと軽くしてくれたのです。
今では、スケジュール帳に「空白の日」を作ることが、私の大切な習慣になっています。友達に誘われても、無理に予定を詰め込まない。自分の心が「今日は休みたい」と言っているときは、その気持ちを優先するようにしています。
スケジュールを空白にする勇気。それは、忙しさに流されがちな私たちにとって、とても大切なことだと思います。何もしていない自分を責めなくていい。むしろ、何もしない時間こそが、心を整えてくれるのです。
もし今、あなたが「予定がないと不安」と感じているなら、ほんの少しだけ勇気を出して、スケジュールを空白にしてみてください。その時間が、あなたの心に静かな安心をもたらしてくれるはずです。
私は、空白の時間の中で、自分の呼吸や、心の声や、小さな幸せに気づくことができました。スケジュールを空白にする勇気は、私にとって「自分を大切にする」ということの、最初の一歩だったのかもしれません。
信頼できる言葉だけを信じる
私には、ずっと心に刺さっていた言葉がありました。高校時代、クラスメイトからふと言われた「なんか暗いよね」。そのひと言が、何年も胸の奥に引っかかっていたのです。誰かと話すたび、ふとその言葉がよみがえってきて、「また暗いと思われてるかも」と自分を責めてしまう。そんな日々が続きました。
でもある日、信頼できる友人が「あなたの静かなところが好きだよ」と呟いてくれたのです。雨の降るカフェで、彼女が紅茶のカップを傾けながら言ったその言葉は、まるで長い冬の後に咲いた桜のようでした。その瞬間、私は気づいたのです。傷つく言葉ばかり拾い集めるのではなく、信じられる人の言葉を大切にすればいいんだと。
それからは、人の言葉を全部受け止めようとするのをやめました。心ない言葉が飛んでくるときは、そっと耳をふさぐ。代わりに、信頼できる人からの優しい言葉をノートに書き留めるようにしたのです。たとえば、母が電話の最後に必ず言う「無理しないでね」とか、仕事仲間が励ましてくれた「あなたの丁寧さが救われたよ」とか。
そうやって、信頼できる言葉だけを選んで受け取るようになると、心が軽くなっていくのがわかりました。誰かの評価に左右されるのではなく、自分が「この人の言葉なら信じられる」と思える人たちの声を、心の拠り所にできるようになったのです。
今でも、時々傷つく言葉を浴びることがあります。でも、そんなときはノートを開いて、書き溜めた優しい言葉を読み返すようにしています。そうすると、少しずつ自分の中に「大丈夫」という感覚が広がってくるのです。信頼できる言葉だけを信じる。それは、私が自分を守るために選んだ、静かな抵抗でした。
自分にとっての“安全地帯”を知る
私の安全地帯は、駅から少し離れた古本屋の二階にあります。木の床がきしむ音、ほんのりカビ臭い紙の香り、埃っぽい陽光が差し込む窓際の席。そこで一冊の文庫本を広げているときだけは、誰にも邪魔されない安心感に包まれるのです。
安全地帯を見つけるまでには、長い時間がかかりました。最初は、人混みの少ない公園のベンチを試してみました。でも、子ども達の歓声が突然聞こえてくるのが苦手で。次に喫茶店の隅席を選んでみたけど、隣の席の会話が気になって落ち着かない。ようやく見つけたのが、この古本屋の二階でした。
店主のおじいさんが、いつも黙ってうなずいてくれるのも気に入っています。必要以上に話しかけてこない、でも困った顔をすればそっとお茶を出してくれる。そんな距離感が、ちょうどいいのです。
ここにいると、背中から力が抜けていくのを感じます。本棚の影に身を隠しているような、小さな生き物になったような気分。誰かの目を気にせず、ただ自分と本だけの時間が流れます。時計を見る必要もなく、携帯の着信音も聞こえない。世界から切り離されたような、でもどこか温かい場所。
安全地帯は、人それぞれ違うのだと思います。友人は河原のサイクリングロードを「心が洗われる場所」と言っていました。別の知人は、深夜のコンビニの駐車場でタバコを吸うのが落ち着くと言っていました。形はどうであれ、自分だけの安全地帯があるということが大切なのです。
もし今、あなたが「どこにも居場所がない」と感じているなら、小さな安全地帯を探してみてください。図書館の奥の席でも、ファミレスの窓際でも、通勤路のたった一箇所の坂道でも。そこで深呼吸してみると、不思議と心が落ち着く瞬間があるはずです。
私の古本屋の二階は、いつでも私を待っていてくれます。埃っぽい空気も、きしむ床も、全部私の「大丈夫」の一部。自分にとっての安全地帯を知っているということが、どれほど心の支えになるか。あなたにもきっと、そんな場所が見つかりますように。
安心の感覚は、自分で育てられる
朝、目覚めたときにふと「今日は何かいいことがありそう」と思える日があります。特別な理由はないのです。空がいつもより明るいとか、聞こえてくる鳥の声が優しいとか、そんな些細なことで。そういう日は、不思議と心が軽やかで、人混みの中でもあまり疲れないのです。
でも、そういう日ばかりじゃありません。むしろ、朝からどんよりした気分の日の方が多い。そんなとき、私は無理に気分を上げようとしないようにしています。代わりに、小さな「安心の種」をまくのです。たとえば、いつもより丁寧に紅茶を淹れてみる。窓を開けて深呼吸する回数を増やす。お気に入りの靴下を履く。そんな小さなことが、少しずつ安心の感覚を育ててくれる気がするから。
安心の感覚は、突然大きな変化でやってくるものじゃないのだと思います。毎日少しずつ、自分を労わる時間を積み重ねていく。傷ついたときは早めに休む、苦手な人とは距離を取る、無理な約束は断る。そんな選択の積み重ねが、やがて心の中に「ここなら安全」という土壌を作ってくれるのです。
ある冬の日、私は電車で突然不安に襲われたことがありました。呼吸が浅くなり、手のひらに冷や汗がにじんで。そのとき、鞄から取り出したのは、いつも持ち歩いているハンカチではなく、母が編んでくれた手袋でした。毛糸の柔らかな感触が、少しずつ心を落ち着かせてくれたのです。その瞬間、私は気づきました。自分で選んだ安心が、ちゃんと私を守ってくれるんだと。
安心の感覚を育てるのは、ガーデニングに似ているかもしれません。毎日水をやり、陽当たりを考え、時には害虫から守る。そうしてやっと、小さな芽が育つように。私たちの心も、丁寧に扱えば、きっと柔らかな花を咲かせてくれるはずです。
もし今、あなたが「安心なんて感じられない」と思っているなら、ほんの小さなことから始めてみてください。枕カバーをやわらかい布地に変える。通勤中に聴く音楽を穏やかな曲にする。夜、寝る前にひと呼吸置く時間を作る。そんなことが、きっと未来の安心の種になります。
私の安心の感覚は、まだ小さな芽です。でも、日々の優しさを注ぎ続ければ、いつかしっかりとした根を張る日が来ると信じています。あなたの安心の種も、きっとゆっくりと育っていきますように。
第13章のまとめ
「安心」は、遠くにある特別なものじゃない。そう気づいたのが、この章を生きてきた私の収穫でした。誰かに与えてもらうものではなく、自分で見つけ、育てていくもの。それは、朝の紅茶の湯気の中にも、古本屋の埃っぽい棚の間にも、そっと忍ばせたハンカチの感触の中にもありました。
外の世界にばかり安心を求めていた頃の私は、いつも飢えていました。もっと認められたい、もっと愛されたい。でも、心の奥ではわかっていたのです。本当に必要なのは、他人からの評価じゃない。自分自身が「ここにいていいんだ」と思える、小さな居場所なのだと。
安心できる人、慣れ親しんだ習慣、お守りのようなアイテム、空白の時間。それら全部が、私の心を支える網の目のようにつながっています。ひとつが崩れても、他のものでカバーできる。そうやって、少しずつ自分を守る術を学んできました。
この章を読み終えたあなたに伝えたいのは、たったひとつのこと。あなたの安心は、すでにあなたの中に芽吹き始めている、ということ。雨の日も嵐の日も、その小さな芽を見失わないでください。毎日少しずつ、優しい言葉をかけてあげてください。いつかきっと、あなただけの花が咲く日が来ますから。
第14章:涙のあとに気づいたこと
泣いたあとの心の静けさ
涙が止まらなくなったあの日、私はベッドの上で丸くなっていました。頬についた涙が乾いてひりひりする。窓の外では夕立が降っていて、雨音が部屋中に響いています。泣き疲れて、ふと目を開けると、なぜか心が穏やかになっているのに気づきました。まるで嵐の後の海のように、荒れ狂った感情がすっかり凪いでいるのです。
泣く前は、胸の奥でぐるぐると渦巻いていた不安や悲しみ。それが涙という形で外に出て行ったあと、心にぽっかりと空間ができたような感覚がありました。重かった肩が軽くなり、呼吸が深くなる。涙を流し切ったあとの静けさは、とても不思議なものだと感じます。あんなに苦しかった気持ちが、どこか遠くへ流れていったみたいに。
ある冬の夜、仕事でのミスをずっと引きずってしまったことがありました。布団に入っても頭の中で失敗がリプレイされて、眠れないまま朝を迎えそうになったとき、突然ぽろぽろと涙がこぼれ出したのです。最初は驚きましたが、そのまま泣き続けました。すると、いつの間にか心のざわめきが消え、すーっと眠りにつけたのです。翌朝目覚めたとき、窓の外に雪が積もっていて、世界が真っ白に変わっていました。涙が心の埃を洗い流してくれたのかもしれない。そう思うと、泣くことも悪くないなと思えた瞬間でした。
泣いたあとの静けさは、自分を客観的に見つめる時間を与えてくれます。感情の渦に飲まれていたときには見えなかったことが、ふと頭に浮かんだり。あのときああ言えばよかった、とか、実は自分が我慢しすぎていたんじゃないか、とか。涙が心の窓を開いて、新しい風を通してくれるような感覚です。
今では、無理に泣くのを止めなくなりました。涙が出そうになったら、静かな場所を見つけて、そっと泣くようにしています。涙と一緒に流れ出ていくものがあると信じているから。そして、泣き終わったあとの穏やかな時間が、私にとっては大切な回復の時間なのです。
「泣いていい」が許された体験
「泣いていいよ」と肩をポンと叩かれたとき、私は初めて自分の涙を肯定してもらえた気がしました。大学の図書館の裏階段で、バイト先でのトラブルを思い出してしくじっていたときのことです。友達がたまたま通りかかって、何も聞かずにそっと隣に座ってくれました。その子が小さな声で呟いたひと言が、私の心の錠を開けたのです。
それまでは、人前で泣くのが恥ずかしくて仕方ありませんでした。涙を見せることは弱さを見せることだと思い込んでいたのです。でも、友達の「泣いていいよ」は、魔法の言葉のように感じられました。許可をもらった瞬間、堰を切ったように涙が溢れ出て。階段の隅で肩を震わせながら、どれだけ泣いたか覚えていません。
泣き終わったあと、友達はにっこり笑って「すっきりした?」と聞いてくれました。頬の涙をハンカチでふきながら頷くと、「また泣きたくなったら、いつでも付き合うよ」と付け加えてくれたのです。その優しさが、どれほど私の支えになったかわかりません。
あの日以来、私は少しずつ自分の涙を受け入れられるようになりました。泣きたいときは無理に笑顔を作らない。トイレの個室でそっと涙を流すこともあるし、夜のベッドの中で枕に顔を埋めることもあります。でも、もう「泣いてはいけない」と自分を責めることはなくなりました。
先日、電車の中で小さな女の子が転んで泣いているのを見かけました。お母さんが「痛かったね、よく泣いたね」と頭を撫でながら声をかけていました。その光景を見て、ふとあの図書館の階段を思い出しました。泣くことは、決して恥ずかしいことじゃない。むしろ、心が自然にしているメンテナンスなのかもしれない。そう思えるようになったのは、あの日「泣いていい」と言ってくれた友達のおかげです。
誰にも言えなかったことを話せた日
五年間、胸の奥にしまっていた秘密を話したのは、去年の桜の季節でした。近所の公園のベンチで、幼馴染みと花見をしながら。手に持ったおにぎりが冷たくなるのも忘れて、私はずっと握りしめたまま話し続けました。震える声で、あのときのことを。誰にも言えなかった悔しさと、自分を責め続けた日々のことを。
幼馴染みは黙って聞いてくれました。時々「うん」と相槌を打ちながら、でも決して途中で遮ったりしなかった。桜の花びらがひらひらと膝の上に落ちてくるのを見ながら、私は初めて自分の傷を晒すことができたのです。
話し終わったとき、幼馴染みがそっと私の手を握りました。「よく言えたね」と。そのひと言で、また涙が溢れそうになりました。長い間、心の奥で腐りかけていた想いを外に出せたせいか、胸が軽くなるのを感じました。まるで重い荷物を下ろしたような、そんな解放感があったのです。
夜、家に帰ってからベッドに横たわると、不思議とぐっすり眠れました。何年も続いていた夜中の目覚めがなく、朝まで深い眠りに落ちていたのです。秘密を話すということは、暗い部屋のカーテンを開けるようなものなのかもしれません。光が差し込めば、怪物だと思っていた影はただの洋服かけだったりするのですから。
あの日以来、私は少しずつ自分の気持ちを言葉に出す練習をしています。全部を話せなくてもいい、ほんの一部でも。言葉にすることで、モヤモヤした気持ちが形を成していく感覚があります。幼馴染みがくれた「よく言えたね」という言葉は、今でも私の心の支えです。誰かに話せたという事実が、私に勇気をくれたのです。
言葉にならない気持ちを受け止めてくれた人
涙も言葉も出ない夜、ただ黙って隣に座ってくれた人がいました。会社の先輩です。プロジェクトの失敗を引きずって、オフィスの屋上で一人うずくまっていたときのこと。先輩はコーヒーの缶を二つ持って現れ、私の隣にそっと腰を下ろしました。何も聞かず、ただ空を見上げながらコーヒーを飲む。その沈黙が、どんなにありがたかったか。
三十分ほど経ったとき、先輩がふと呟きました。「星、きれいだね」。見上げると、都会の空にかすかに光る星が三つ四つ。その瞬間、押し殺していた涙がこぼれ落ちました。言葉にならない悔しさや不安が、星の光に溶けていくようでした。先輩は相変わらず黙ったまま、タオルハンカチを差し出してくれました。
あの夜から、私は「言葉にしなくてもわかってくれる人」がいることを知りました。説明しなくても、弁解しなくても、ただ一緒に時間を過ごしてくれる存在の大切さを。先輩とはその後、そのことを話題にしたことはありません。でも、屋上で見た星のことを、私は一生忘れないでしょう。
先月、後輩がオフィスの廊下で泣いているのを見かけました。私は迷わず、自動販売機で温かい缶コーヒーを買って、そっと隣に置きました。何も聞かず、ただ同じ方向を見つめる。後輩が「ありがとう」と呟いた声が、小さく響きました。言葉にならない気持ちを抱える人に、私もそっと寄り添えるようになっていたのです。
あの日の先輩のように。星の光のように。言葉にならない気持ちは、きっと優しい沈黙の中で癒されていくのだと思います。誰かの痛みに寄り添うとき、最も必要なのは完璧なアドバイスじゃない。ただそこにいるという温もりなのかもしれません。
いつも泣きたかったのは、安心が欲しかったから
深夜のコンビニの駐車場で、突然涙が止まらなくなったことがあります。寒い夜で、吐く息が白く曇るなか、買ってきたおにぎりの包装を破ろうとして、なぜか手が震え出したのです。プラスチックのフィルムがうまく剥がれない。その小さなもどかしさが、最後の引き金になりました。膝を抱えて車のヘッドライトに照らされながら、私は泣きじゃくっていました。
後で振り返ると、あのときの涙はおにぎりのせいじゃなかったのです。三ヶ月間休みなく働き続けた疲労。上司の何気ない叱責を五日間も反芻していたこと。友達からの「元気?」というメールに返信できない自分へのいらだち。それらがじわじわと心に染み出して、些細なきっかけで溢れ出したのでした。
泣きながら気づいたのです。私が求めていたのは、ただ「大丈夫だよ」と頭を撫でてくれる人の温もりだったのだと。誰かに「頑張ってるね」と認めてもらえること。失敗しても責められない場所。そんな安心が、心底欲しかったのだと。
子どもの頃から、私はよく泣いていました。おもちゃを貸してと言われて泣く。授業で当てられて泣く。でも大人になるにつれて、泣くことは恥ずかしいことだと学びました。だから、涙はトイレの個室や夜の布団の中に隠すようになりました。だけど、隠せば隠すほど、心の奥で「誰かに気づいてほしい」という願いが強くなっていったのです。
あのコンビニの夜から、私は少しずつ変わりました。信頼できる友人に「今日、泣きそうだった」と打ち明けてみたり、カウンセラーの先生に「安心できる場所が欲しい」と伝えてみたり。すると驚くことに、周りの人たちは私が思っていた以上に優しかったのです。母が久しぶりに「辛いときはいつでも帰っておいで」と言ってくれた日、私は電話口でまた泣いてしまいました。でも今度の涙は、安心からこぼれた温かいものでした。
泣きたいときは、安心を求める心のサインなのかもしれません。無理に泣き止もうとせず、そっと自分の胸に手を当ててみてください。「大丈夫、ここは安全だよ」と、心の奥にしまった子どもに語りかけるように。きっと、泣いた後の心は軽やかになっているはずです。
涙は、ちゃんと理由がある
電車のホームで、見知らぬ女性が急に泣き出したことがあります。朝のラッシュアワー、誰もが忙しそうにスマホを見ているなか、彼女はぼろぼろと涙をこぼしながらベンチに座っていました。周りの人は気づかないふりをしています。でも私は、彼女の涙に理由があることを確信していました。きっと、朝食のお味噌汁がこぼれたとか、そんなことじゃない。積もりに積もった何かが、ふと溢れ出したのだろうなと。
私自身、人には理解されにくい理由で泣くことがあります。たとえば、スーパーのレジで「ありがとう」と言われたとき。公園のベンチに置かれた花束を見つけたとき。テレビドラマの主人公が空を見上げるシーンで。そんなとき友人に理由を聞かれると、うまく説明できなくて困ってしまいます。「だって、あの花束を置いた人の優しさが伝わってきて」と言っても、きっと笑われるだけでしょうから。
でも、涙には必ず理由があります。昨日の上司のひと言が心に刺さったまま眠れなかったから。一週間ため込んだ寂しさが、ふとした瞬間に溢れ出したから。あるいは、ただ疲れが溜まっていて、心が敏感になっていたから。表面に見えるきっかけは些細なことでも、その奥にはちゃんとした理由が横たわっているのです。
先月、飼っていた金魚が死んだときのことを思い出します。たった300円の金魚なのに、私はベランダでしばらく泣いていました。実はその日、仕事で大きなミスをして、ずっと自分を責め続けていたのです。金魚の死は、押し殺していた感情の蓋を開ける出来事でした。涙は金魚のためではなく、自分自身を労わるためだったのだと後で気づきました。
今では、理由がわからなくても涙が出るときは、素直に泣くようにしています。心が「そろそろメンテナンスが必要です」と教えてくれているのだと受け止めるように。涙の理由を探すよりも、ただハンカチで頬を拭う。そうしているうちに、ふと心の重りが外れる瞬間が訪れるのです。
涙のあと、少しだけ笑えた理由
泣き腫らした目でコンビニのアイスを買いに行ったとき、店員さんが「大丈夫ですか?」と声をかけてくれませんでした。むしろ、いつも通り淡々とレジを済ませて「お気をつけて」と笑顔をくれたのです。その何気ない日常性が、なぜかとてもありがたくて。帰り道、アイスの袋を提げながら、ふっと笑えてしまったことがあります。
涙のあとに訪れる小さな笑い。それは、嵐のあとの虹のようなものかもしれません。先日、大切な書類を雨で濡らしてしまい、喫茶店のトイレで泣いていたときのこと。鼻をかんだティッシュがなくなり、仕方なくトイレットペーパーで顔を拭っていたら、不格好すぎて鏡の自分を見て吹き出してしまいました。泣きながら笑うという、不思議な気分でした。
涙のあとの笑顔は、特別に輝いて見えます。公園で泣いていたら、小さな女の子が「お姉さん、これあげる」とたんぽぽの綿毛をくれたことがありました。くしゃくしゃの涙顔で受け取ると、彼女はにっこり笑って走り去っていったのです。そのときのたんぽぽの綿毛は、今でも手帳に挟んであります。
大人になってから気づいたのですが、涙のあとって心がとても柔らかくなるんです。いつもなら気にしないような小さな優しさに気づけたり、ささやかな幸せを感じられたり。先週、泣いたあとに飲んだインスタントの味噌汁が、なぜかすごく美味しく感じられたときは、思わず笑みがこぼれました。
涙のあとに笑えるのは、心が少し軽くなった証拠なのかもしれません。重かった荷物を下ろして、ふと周りを見渡せる余裕が生まれるのでしょう。今では、泣いたあとの自分を少し楽しむ余裕も出てきました。冷たい水で顔を洗い、ホットミルクを飲みながら「また一つ、強くなれたね」と呟くのです。
もしあなたが今、泣いたばかりだとしたら、窓の外を見てみてください。いつもと変わらない風景が、なぜか優しく見えるかもしれません。涙が心のレンズを曇りからクリアに変えてくれたのかもしれませんよ。そして、そのうちきっと、ふとした瞬間に笑っている自分に気づくはずです。
第14章のまとめ
涙は、決して無駄じゃない。この章を書き終えた今、そう強く思います。泣いたあとの静けさで見える世界。誰かに受け止めてもらえた安心。言葉にならなかった気持ちの重さ。どれもが、涙という名の浄化作用を通して私に教えてくれたことです。
子どもの頃は、泣くたびに「弱い自分」を責めていました。でも今はわかります。涙は心の掃除であり、自分を守るための自然な反応なのだと。あの日コンビニの駐車場で泣いた私に、夜風は「よく頑張ったね」と囁いていたのかもしれません。
この章を読んでくれたあなたへ。もし今、泣きたい気持ちがあるなら、どうか無理に止めないでください。涙はやがて土にかえり、新しい命を育む雨になるのですから。そして泣き終わったら、そっと窓を開けてみてください。涙が洗った後の世界は、きっとほんのり優しい色をしているはずです。
私の涙のあとには、いつも小さな笑顔が待っていてくれました。それはたんぽぽの綿毛かもしれないし、見知らぬ人の何気ない笑顔かもしれない。あなたの涙のあとに咲く花も、きっと素敵な色をしていると思います。どうか、その花を見逃さないでくださいね。
「気にしすぎてるな」と気づけるようになった
私の場合は、ずっと「気にしすぎる自分」に気づかないまま生きてきました。小さなことでも心がざわざわして、夜になってもそのざわめきが消えず、眠れなくなることもよくありました。でも、そのたびに「なんでこんなことで悩むんだろう」「もっと強くならなきゃ」と自分を責めてばかりいたのです。
ある日のことです。友達とカフェで話していたとき、ふとした沈黙が訪れました。私は「今の言い方、変だったかな」「もしかして嫌な気持ちにさせたかも」と、頭の中でぐるぐると考え始めてしまいました。友達の表情や声色を何度も思い出しては、「大丈夫だったかな」と心配が止まらなくなりました。
その帰り道、ふと気づいたのです。「ああ、また気にしすぎてるな」と。以前の私なら、そのまま自己嫌悪の渦に飲み込まれていたかもしれません。でも、そのときは少し違いました。自分の心の動きを、まるで離れた場所から眺めているような、不思議な感覚があったのです。
「気にしすぎてるな」と気づくこと。それは、私にとって小さな革命でした。今までは、気にしすぎる自分と一体化してしまっていて、どこからが「私」なのか、どこからが「不安」なのか、区別がつかなかったのです。でも、「あ、今、気にしすぎてる」と自分に声をかけることで、ほんの少しだけ心に余白が生まれました。
それからというもの、私は気にしすぎている自分に気づいたとき、そっと心の中で「今、気にしすぎてるよ」とつぶやくようになりました。まるで、子どもが転んだときに「大丈夫?」と声をかけるような、そんな優しい気持ちで。
気にしすぎることは、決して悪いことではありません。むしろ、それだけ人の気持ちや空気に敏感で、細やかに感じ取れるということ。だけど、その感受性が自分を苦しめることもあるのです。だからこそ、「気にしすぎてるな」と気づくことは、自分を守るための大切な第一歩だと、今では思えるようになりました。
気づくことができると、不思議と心が少しだけ軽くなります。「またやってるな、私」と、どこかおかしくて、くすっと笑いたくなるときもあります。そんなときは、無理に気持ちを変えようとせず、ただ「そうだよね、気にしすぎちゃうよね」と自分に寄り添ってみるのです。
大人になってからも、私は何度も同じような場面に出会います。仕事でミスをしたとき、誰かの言葉が引っかかったとき、夜中にふと昔のことを思い出してしまったとき。そんなときも、「あ、また気にしすぎてる」と気づけるだけで、心の中に小さな灯りがともるような気がします。
気にしすぎる自分を責めるのではなく、気づいてあげること。それが、私が自分と仲直りするための最初の一歩でした。
自分の感受性を責めない
私は昔から、感受性が強いと言われてきました。小さなことにもすぐに心が動いてしまうし、誰かの悲しそうな顔を見ると、自分のことのように胸が痛くなります。映画や本の中の登場人物の気持ちに、涙が止まらなくなることもしょっちゅうです。
でも、それが「生きづらさ」につながることも多かったのです。周りの人は平気そうなのに、どうして自分だけこんなに傷つきやすいんだろう。どうして、みんなみたいに「気にしないよ」と笑い飛ばせないんだろう。そんなふうに、自分の感受性を責めてしまうことが、何度もありました。
ある日、仕事でちょっとした注意を受けたときのことです。上司はきっと、何気なく言っただけだったのでしょう。でも私は、その言葉が心に突き刺さって、しばらくの間、胸が苦しくなってしまいました。「こんなことで落ち込むなんて、私って弱いな」と、また自分を責めてしまいました。
だけど、ふと気づいたのです。感受性が強いからこそ、私は人の痛みに気づけるし、誰かが困っていたらすぐに手を差し伸べたくなる。友達が悩んでいるときは、何も言わなくても「大丈夫?」と声をかけることができる。それって、悪いことじゃないんじゃないか、と。
自分の感受性を責めるのは、とても苦しいことです。まるで、自分という存在そのものを否定しているような気持ちになります。でも、感受性は「弱さ」ではなく「やさしさ」なのだと、少しずつ思えるようになりました。
もちろん、感受性が強いことで傷つくこともあります。でも、その分だけ、世界の美しさや人のあたたかさにも敏感でいられる。雨の音や、春の風、誰かの小さな笑顔に、心がふわっと温かくなる瞬間がある。そんな自分を、少しずつ大切にしたいと思うようになりました。
感受性を責めるのではなく、「ありがとう」と言ってあげる。今日もたくさん感じて、たくさん悩んで、たくさん泣いた自分に、「よく頑張ったね」と声をかけてあげる。そんなふうに、自分に優しくできる日は、心がすこしだけやわらかくなります。
人と比べて「自分はダメだ」と思うのではなく、「自分には自分の感じ方がある」と受け止めてみる。そうすると、不思議と世界がやさしく見えてくるのです。
ひと呼吸おいて「まあ、いいか」
気にしすぎる私にとって、「まあ、いいか」という言葉は、最初はとても遠いものでした。何か失敗したとき、誰かに何か言われたとき、頭の中で何度もその場面を繰り返しては、「どうしてあんなことを言ってしまったんだろう」「もっと気をつければよかった」と自分を責めてばかりいました。
でも、あるとき友達が、私の悩みを聞いてくれたあとに、ふっと「まあ、いいじゃん」と言ってくれたのです。その言葉が、私の心にふわっと染み込んできました。「そんなに気にしなくても大丈夫だよ」と、やさしく包み込んでくれるような響きがありました。
それから私は、何かあったときに、ひと呼吸おいて「まあ、いいか」とつぶやいてみるようになりました。最初は、なかなかうまくできませんでした。心の中では、「でも、やっぱり…」と不安や後悔が渦巻いていました。でも、何度も繰り返すうちに、少しずつ「まあ、いいか」が心の中に居場所を作ってくれるようになったのです。
「まあ、いいか」と思えると、肩の力がふっと抜けます。完璧じゃなくてもいい、みんなに好かれなくてもいい、失敗しても大丈夫。そんなふうに、自分を許すことができるようになりました。
もちろん、すぐに気持ちが切り替わるわけではありません。気にしすぎる自分が顔を出して、「本当に大丈夫かな」「やっぱりあのとき…」と心配になることもあります。でも、そんなときも「まあ、いいか」と自分に言ってあげることで、少しずつ心が軽くなっていきました。
「まあ、いいか」は、魔法の言葉です。自分を許すこと、手放すこと、そして前に進むこと。すべてをやさしく包み込んでくれる、あたたかい言葉だと思います。
日々の中で、何度も「まあ、いいか」とつぶやいてみてください。失敗したとき、誰かに何か言われたとき、自分を責めそうになったとき。ひと呼吸おいて、「まあ、いいか」と心の中でつぶやく。それだけで、心がふわっと軽くなる瞬間が、きっと訪れるはずです。
考えすぎた自分に「ありがとう」
私はいつも、何かあるとすぐに考えすぎてしまいます。夜、布団に入ってからも、今日あった出来事を何度も思い返しては、「あのとき、こう言えばよかったかな」「もしかして、あの人を傷つけてしまったかも」と、頭の中でぐるぐると考え続けてしまうのです。
そんな自分が、ずっと嫌いでした。「なんでこんなに考えすぎるんだろう」「もっと気楽に生きられたらいいのに」と、何度も思いました。でも、ある日ふと、「考えすぎるのも、私の大切な一部なのかもしれない」と思えるようになったのです。
考えすぎるということは、それだけ物事を深く受け止めているということ。人の気持ちや空気を敏感に感じ取って、どうしたらみんなが心地よく過ごせるかを、無意識に考えているのかもしれません。自分のことだけでなく、周りの人のことも大切に思っているからこそ、考えすぎてしまうのだと思います。
だから、最近は考えすぎた自分に「ありがとう」と言うようにしています。今日もたくさん考えて、たくさん悩んで、たくさん気を遣ってくれた自分に、「お疲れさま」と声をかけてあげるのです。
考えすぎる自分を責めるのではなく、「ありがとう」と受け止めてあげる。そうすることで、心がすこしだけあたたかくなります。考えすぎる自分も、私の大切な一部。だから、無理に変えようとせず、そっと寄り添ってあげたいと思うのです。
夜、眠る前に「今日もいろいろ考えたね。ありがとう」と自分に声をかける。そんな小さな習慣が、私の心をやさしく包んでくれます。考えすぎることも、気にしすぎることも、全部ひっくるめて「私」なんだと、今では思えるようになりました。
気にしすぎる自分と仲直りすることは、簡単なことではありません。でも、少しずつ、少しずつ、自分にやさしくできるようになったとき、心がふわっと軽くなる瞬間がやってきます。考えすぎる自分に「ありがとう」と言える日は、きっと、あなたの心にもやさしい光が差し込むはずです。
第16章:わたしが選んだ生き方
過去の自分を抱きしめるイメージ
私の場合は、過去の自分を思い出すと、胸がきゅっと苦しくなることがよくあります。あのとき、もっと上手にできていればよかったのに。あのとき、もう少し堂々としていれば、きっと傷つかずに済んだのに。そんなふうに、何年も前の出来事を、まるで昨日のことのように思い出しては、自分を責めてしまうことがありました。
小学生の頃、友達とのちょっとしたすれ違いで、夜眠れなくなったことがあります。教室の片隅で、みんなが楽しそうに話しているのを遠くから見て、「私、何か変なこと言ったかな」と心配になって、家に帰ってからもずっとそのことばかり考えていました。母に「どうしたの?」と聞かれても、うまく言葉にできなくて、ただ「なんでもない」と答えてしまった自分。今思い出しても、あのときの小さな自分は、とても不安で、心細かったのだと思います。
大人になってからも、同じようなことが何度もありました。新しい職場で、みんなの輪にうまく入れなくて、帰り道の電車の中で涙が出そうになった日。好きな人に思い切って話しかけたのに、思ったような返事がもらえなくて、自分のことを責め続けた夜。どれも、今の私を作ってくれた大切な思い出だけれど、思い出すたびに、心が少し痛くなります。
でも、最近はそんな過去の自分を、そっと抱きしめるイメージを持つようになりました。あのときの私に、「よく頑張ったね」「大丈夫だったよ」と声をかけてあげる。まるで、寒い日に毛布をかけてあげるみたいに、やさしく包み込むのです。
「そんなに気にしなくてもよかったんだよ」と、今の私が過去の私に語りかける。あのときは、世界がとても狭くて、目の前の出来事がすべてのように感じていたけれど、本当はもっと広い世界があったんだよ、と。泣きたいときは泣いてもいいし、不安なときは誰かに頼ってもいい。そうやって、少しずつ自分を許せるようになりました。
過去の自分を抱きしめることは、簡単なことではありません。ときどき、どうしても許せない出来事や、思い出すだけでつらくなる瞬間もあります。でも、それも全部「私」なんだと、今では思えるようになりました。
もし、あなたにも抱きしめてあげたい過去の自分がいるなら、そっと目を閉じて、あの頃の自分にやさしい言葉をかけてあげてください。「よく頑張ったね」「大丈夫だったよ」「今はもう、安心していいよ」と。そうすると、不思議と心があたたかくなって、少しだけ前を向ける気がしてきます。
頑張らなくても、愛されてたこと
私の場合は、ずっと「頑張らなきゃ」「もっとしっかりしなきゃ」と思いながら生きてきました。人に迷惑をかけないように、みんなに嫌われないように、いつも気を張って、空気を読みすぎて、気がつけば心も体もくたくたになっていたのです。
でも、あるときふと気づいたことがあります。頑張っていないときの私も、誰かにとっては大切な存在だったんだ、ということ。たとえば、家族と過ごす休日。ソファでごろごろしながら、何もせずにただ一緒にいるだけで、母が「今日もいてくれて嬉しいよ」と言ってくれたこと。友達と何気なくおしゃべりしているとき、「あなたがいると安心する」と言われたこと。そんな小さな瞬間が、私にとっては宝物のように心に残っています。
頑張らなくても、愛されていた。そう思えたとき、心の中の重たい荷物がすっと軽くなりました。もちろん、頑張ることは大切です。でも、それだけが「自分の価値」じゃないんだと、今では思います。
昔の私は、いつも「もっと頑張らなきゃ」と自分を追い立てていました。失敗したときは、「こんな自分じゃダメだ」と落ち込んで、うまくいったときも「まだまだ足りない」と思ってしまう。そんなふうに、ずっと自分に厳しくしてきたのです。
だけど、頑張っていないときの私も、ちゃんと誰かに愛されていた。何もできなくても、ただそこにいるだけで、誰かの心をあたためていた。そう気づいたとき、涙が出るほど嬉しかったのを覚えています。
これからは、頑張らない自分も大切にしたいと思います。疲れたときは休んでいいし、うまくいかない日があっても大丈夫。そんなふうに、自分にやさしくできるようになったのは、たくさんの人の愛に気づけたからです。
もし、今のあなたが「頑張らなきゃ」と苦しくなっていたら、どうか思い出してほしいです。頑張らなくても、あなたはちゃんと愛されている。何もできなくても、あなたの存在そのものが、誰かにとって大切なんです。
気にしすぎるのも“わたし”の一部
私の場合は、「気にしすぎる自分」をずっと嫌っていました。もっと強くなりたい、もっと鈍感になりたい、そう思って何度も自分を変えようとしました。でも、どれだけ頑張っても、やっぱり私は気にしすぎてしまうのです。
ある日、ふと鏡を見ながら思いました。「気にしすぎるのも、私なんだな」と。無理に変えようとするのではなく、受け入れてみよう。そう思ったとき、心がふわっと軽くなりました。
気にしすぎるからこそ、人の気持ちに敏感になれる。小さな変化にも気づけるし、誰かが困っていたらすぐに気づいてあげられる。そんな自分を、少しずつ好きになっていきました。
もちろん、気にしすぎて苦しくなることもあります。でも、それも含めて「私」なんだと思えるようになったのです。気にしすぎる自分を責めるのではなく、「今日もよく頑張ったね」と声をかけてあげる。そうすると、心がやさしく包まれる気がします。
気にしすぎるのは、決して悪いことではありません。それは、あなたのやさしさであり、感受性であり、世界を豊かに感じる力です。だから、無理に変えようとしなくていい。気にしすぎる自分も、大切な「わたし」の一部なんです。
もし、今のあなたが「気にしすぎて苦しい」と感じているなら、どうか自分を責めないでください。そのままのあなたで大丈夫。気にしすぎる自分も、きっとあなたを守ってくれているのです。
第15章のまとめ
この章では、「気にしすぎる自分」と仲直りするための、小さなヒントを綴ってきました。気にしすぎてしまうことに気づくこと、自分の感受性を責めないこと、ひと呼吸おいて「まあ、いいか」と言ってみること。そして、考えすぎた自分に「ありがとう」と伝えること。
過去の自分を抱きしめるイメージを持つこと、頑張らなくても愛されていたことに気づくこと、気にしすぎるのも「わたし」の一部だと受け入れること。それぞれが、少しずつ心をやわらかくしてくれる大切なステップでした。
気にしすぎる自分を責めてばかりいた日々から、少しずつ自分にやさしくできるようになった今、私は「このままの自分でいいんだ」と思えるようになりました。もちろん、これからも気にしすぎてしまうことはあると思います。でも、それも全部「私」なんです。
あなたも、どうか自分にやさしくしてあげてください。気にしすぎる自分も、泣き虫な自分も、頑張りすぎてしまう自分も、全部ひっくるめて「あなた」なんです。そのままのあなたで、きっと大丈夫。心が疲れたときは、そっと自分を抱きしめてあげてください。
この章が、あなたの心に小さなやさしさを届けられたら嬉しいです。気にしすぎる自分と、少しずつ仲直りしていけますように。
第16章:わたしが選んだ生き方
自分の「好き」を中心に選ぶ暮らし
私の場合は、長い間「べき論」に縛られて生きてきました。みんながしているから、普通だから、社会人として当然だから。そんな言葉に翻弄されながら、気がつけば心がすり減っていくような日々を送っていました。朝は満員電車に揺られ、夜は疲れて帰宅するだけ。休日も「どこかに出かけなきゃ」と焦って、結局何もできずに月曜を迎える。そんな生活が続くうちに、ふと気づいたのです。「これ、本当に私が望んでいた生き方なのかな」と。
転機は、ある雨の土曜日の朝でした。窓の外を流れる雨の音を聞きながら、ベランダに置いた小さな植木鉢を眺めているとき、突然胸が熱くなりました。土から顔を出す双葉の緑が、雨粒に揺れている様子に、なぜか涙がこぼれたのです。その瞬間、「私、本当はこんな小さなことが好きだったんだ」と気づきました。大勢でにぎわう場所より、静かな時間。派手なイベントより、植物の成長をそっと見守る瞬間。そういう「好き」を、ずっと後回しにしていたことに。
それからは、少しずつ生活を変えていきました。朝は30分早く起きて、コーヒーを淹れながら窓の外を眺める時間を作る。通勤ラッシュを避けるため、思い切ってシェアオフィスに変えてみる。休日は無理に外出せず、図書館で好きな本を読んだり、散歩道で見つけた野草の写真を撮ったり。最初は「こんなことでいいのかな」と不安もありましたが、次第に心が軽やかになっていくのを感じました。
「好き」を中心に生きるというのは、決して特別なことではありません。たとえば、夕飯のメニューを、誰かの好みではなく自分の食べたいものにしてみる。インテリアショップで、「実用的かどうか」より「触り心地が好き」という理由でクッションを選ぶ。そんな小さな選択の積み重ねが、いつのまにか私の日常を優しく彩ってくれました。
もちろん、すべてを「好き」だけで選べるわけではありません。でも、意識的に「好き」に目を向けることで、生きることが少しずつ楽になりました。まるで、長い間閉じていた窓を開けたら、柔らかな風が入ってきたような感覚です。
最近では、街を歩いていても「あ、このお店の看板の色、好きだな」「この道の木漏れ日がきれい」と、小さな発見が増えました。それは、自分自身との対話を大切にしたからこそ見えてきた世界です。あなたにも、きっとそんな「好き」がたくさんあるはず。どうか、それをそっと手のひらに乗せて、大切に育ててあげてください。
小さくても幸せを感じる仕事
以前の私は、「立派なキャリアを築かなければ」という思いに縛られていました。大企業でバリバリ働く人たちを見ては、「私もああなりたい」と思い、でも実際にその環境に身を置くと、毎日のように頭痛がしてしまう。そんなジレンマを抱えながら、5年ほど会社員として働いていた時期があります。
転機は、あるパートタイムの仕事でした。地域のコミュニティセンターで、子供たちに絵本の読み聞かせをするというアルバイトです。給料は以前の半分以下ですが、子供たちのキラキラした目や、「次はどんなお話?」と期待される瞬間が、私の心を満たしてくれました。帰り道、ふと空を見上げたら、夕焼けがとてもきれいで。そのとき、「これでいいんだ」と胸が熱くなったのを覚えています。
今では、フリーランスとして小さな仕事をいくつか掛け持ちしています。ライターとして文章を書いたり、手作りの雑貨を販売したり。収入は不安定なときもありますが、自分のペースでできることが何よりの幸せです。先日など、お客様から「あなたの作ったコースター、毎日使ってるよ」とメッセージをもらったときは、嬉しくてしばらく画面を見つめていました。
「小さくても幸せを感じる仕事」とは、誰かにとって特別なことでなくてもいいのです。たとえば、花屋さんで一輪の花をアレンジする時間。カフェでお客様の好みを覚えて、いつもよりちょっと濃いめのコーヒーを淹れる瞬間。そんな「小さな幸せ」の積み重ねが、いつのまにか仕事の喜びになっていくのです。
もちろん、周りから「もっと安定した仕事をしたら?」と言われることもあります。でも、朝起きるのが辛くないこと、仕事の後にも心に余裕があること。そういう「当たり前」が、私にとっては何より大切なのです。あなたにも、きっと心が軽やかに動き出す仕事があるはず。大きさではなく、自分に合ったサイズを見つけられたら、それはとても素敵なことだと思います。
「合わない場所」に無理に馴染まない
私は長年、「どこにいても馴染めない自分が悪い」と思い込んでいました。職場の飲み会で浮いてしまうこと、ママ友の井戸端会議についていけないこと。そんなたびに、「もっと努力しなきゃ」と自分を責めていたのです。でもある日、ふと気づきました。合わない場所に無理にいる必要はないんだ、と。
きっかけは、転職したばかりの職場での出来事です。オフィスがオープンスペースで、常に誰かが話し声やキーボードの音を立てている環境でした。最初は「慣れるだろう」と我慢していましたが、次第に頭痛がするようになり、集中できない日々が続きました。ある朝、通勤電車の中で涙が止まらなくなり、そのまま最寄り駅のベンチに座り込んでしまったのです。
そのとき携帯に届いたのは、昔から付き合いのある友達からのメッセージでした。「無理しすぎてない? あなたらしい場所、きっとあるよ」。たったそれだけの言葉に、私は号泣してしまいました。それから勇気を出して、リモートワークが可能な職場に転職したのです。
今の職場は、小さなチームでそれぞれが自分のペースで働ける環境です。大きな音が苦手な私のために、ヘッドホンの着用が許可されています。たまに「もっとコミュニケーションを」と言われることもありますが、無理に合わせる必要がないことがわかり、心が軽くなりました。
「合わない場所」にいるときのしんどさは、本当に辛いものです。でも、それはあなたが悪いわけではありません。光の当たり方、風の通り方、空気の質。場所にも相性があるように、人にも居心地の良い場所があるのです。
もし今、あなたが「ここにいると苦しい」と感じているなら、どうか自分を責めないでください。無理に馴染もうとしなくていい。あなたに合った場所が、きっとどこかにあるはずです。少しずつ、自分の居場所を探す旅に出てみませんか。
気を遣わない関係が、いちばん長続きする
昔の私は、人間関係でいつも疲れ果てていました。相手の機嫌を損ねないように、空気を読みすぎて。LINEの返信も、言葉の端々まで考えてしまい、結局何時間も返せないことが多かったのです。でも、そんなに気を遣った関係ほど、長続きしなかったことに気づきました。
転機は、大学時代の友人との再会でした。5年ぶりに会ったのに、なぜか昔と同じように話せる。お互いの近況を報告しあい、沈黙が続いても気まずくならない。帰り際に「またね」と言われたとき、その自然さがとても心地よかったのです。気を遣わなくてもいい関係があるんだ、と初めて実感しました。
今、大切にしている友人とは、無理に会う約束をしません。「今日はちょっと疲れてるから」と素直に伝えられるし、相手からも同じように連絡が来ます。先日など、2ヶ月ぶりに会った友達と、公園のベンチで3時間も話し込んでしまいました。お互いの変化を受け入れながら、でも変わらない部分を認め合える。そんな関係が、私にはぴったりなのです。
気を遣わない関係とは、無関心なわけではありません。むしろ、お互いのありのままを受け入れる信頼があるからこそ、自然体でいられるのです。たとえば、料理が苦手な私が手作りクッキーを渡したとき、「ありがとう、でも次は買ってきて」と笑われたこと。そのときの安心感は、今でも忘れられません。
人間関係に疲れたときは、一度立ち止まってみてください。本当に気を遣わなければいけない相手ですか? 無理をしなくても、自然にいられる関係はありませんか? 気を遣わない関係こそ、長い時間をかけて育まれるものだと思います。あなたにも、そんな風に肩の力を抜いて付き合える人が、きっといるはずです。
忙しいより、心が満たされる選択
私の場合は、忙しさこそが「ちゃんと生きている証拠」だと思い込んでいた時期がありました。朝から晩まで予定を詰め込んで、手帳が真っ黒になると、なんだか安心できる気がしていたのです。友達との約束、仕事の締め切り、家族の用事。ひとつひとつをこなすたび、「私、ちゃんと頑張ってる」と自分に言い聞かせていました。
でも、ある日ふと気づいたのです。どれだけ予定をこなしても、心が満たされる瞬間がなかなか訪れないことに。むしろ、どんどん心が乾いていくような、そんな感覚でした。夜、ベッドに入っても、頭の中は「明日は何をしなきゃいけないんだっけ」と、次のタスクのことでいっぱい。目を閉じても、心がざわざわして眠れない日が増えていきました。
そんなある日、仕事で大きなミスをしてしまいました。上司に謝りながら、涙が止まらなくなってしまったのです。そのとき初めて、「ああ、私、もう限界だったんだ」と気づきました。忙しさで自分をごまかしてきたけれど、本当はずっと心が悲鳴をあげていたのだと思います。
それから、少しずつ「忙しい」を手放す練習を始めました。最初は不安でいっぱいでした。予定が空白の日があると、「私、何もしていない」と責める気持ちが湧いてきて、落ち着かなかったのです。でも、勇気を出して何も予定を入れない日を作ってみました。朝はゆっくりコーヒーを淹れて、ベランダでぼんやり空を眺める。お昼は近所のパン屋さんで買ったパンを、公園のベンチで食べる。夕方は、好きな音楽を聴きながら、部屋の片隅で本を読む。
そんな「何もしない時間」が、少しずつ私の心を満たしてくれるようになりました。忙しさで埋めていた心の隙間に、やさしい風が通り抜けるような、そんな感覚です。「今日は何もしていないけど、なんだか幸せだな」と思える日が増えていきました。
もちろん、今でも忙しい日々はあります。でも、忙しさに流されるのではなく、「本当にやりたいこと」「心が満たされること」を選ぶようにしています。友達との約束も、無理に詰め込まず、「今日は会いたいな」と思ったときだけ声をかける。仕事も、できるだけ自分のペースで進めるように心がけています。
「忙しいより、心が満たされる選択」。それは、私にとってとても大きな変化でした。自分の心の声に耳を傾けて、「今、何がしたい?」と問いかける。そんな小さな習慣が、毎日をやさしく彩ってくれるのです。
もし、今のあなたが「忙しさ」に追い立てられているなら、どうか少しだけ立ち止まってみてください。心が満たされる瞬間を、大切にしてあげてください。きっと、あなたの毎日が少しずつやわらかく、あたたかくなっていくはずです。
変わらないままで、できることが増えた
ずっと私は、「変わらなきゃ」と思っていました。もっと明るく、もっと社交的に、もっと強く。気にしすぎる自分を変えたくて、いろいろな本を読んだり、自己啓発のセミナーに参加したりもしました。でも、どれだけ努力しても、結局私は私のままでしかいられませんでした。
あるとき、友達に「昔から変わらないよね」と言われたことがあります。その言葉が、なぜか心に引っかかりました。「変わっていない自分はダメなのかな」と、少し落ち込んでしまいました。でも、よく考えてみると、変わらないままでもできることが、少しずつ増えていることに気づいたのです。
たとえば、人前で話すのが苦手だった私が、少人数のミーティングなら自分の意見を言えるようになったこと。知らない人と話すのが怖かった私が、近所のパン屋さんで「このパン、おいしいですね」と店員さんに声をかけられるようになったこと。大きな変化ではないけれど、少しずつ「できること」が増えていったのです。
変わらないままでいい。むしろ、変わらない部分があるからこそ、安心できる場所や人ができるのだと思います。私の繊細さや、気にしすぎる性格も、そのままでいい。そのままの自分で、少しずつ世界を広げていけばいいんだ、と今では思えるようになりました。
「変わらないままで、できることが増えた」という実感は、私にとって大きな自信になりました。無理に自分を変えようとしなくても、毎日を丁寧に積み重ねていけば、自然とできることが増えていく。そんなふうに思えるようになったのは、たくさんの失敗や、たくさんの優しさに出会ってきたからだと思います。
もし、今のあなたが「変わらなきゃ」と苦しんでいるなら、どうか自分を責めないでください。変わらないままでも、できることはきっと増えていきます。あなたのペースで、あなたらしい一歩を踏み出してみてください。きっと、その一歩が、あなたの世界をやさしく広げてくれるはずです。
自分に正直な生き方は、想像以上に心地よい
私の場合は、ずっと「こうあるべき」という枠の中で生きてきました。人に合わせて、空気を読んで、波風を立てないように。自分の本当の気持ちを押し殺して、「大丈夫」と笑ってみせることが、当たり前になっていました。
でも、ある日ふと「本当はどうしたい?」と自分に問いかけてみたのです。そのとき、胸の奥から小さな声が聞こえました。「本当は、もう少しゆっくり歩きたい」「本当は、無理して笑いたくない」。その声に耳を傾けてみると、心がふわっと軽くなった気がしました。
それから、少しずつ自分に正直になる練習を始めました。たとえば、友達の誘いを断るとき。「今日は疲れているから、ごめんね」と素直に伝えてみる。仕事で無理なお願いをされたとき、「今は難しいです」と勇気を出して言ってみる。最初はドキドキしましたが、不思議と相手も受け入れてくれることが多かったのです。
自分に正直な生き方は、想像以上に心地よいものでした。無理をしなくていい。自分の気持ちを大切にできる。そんな毎日は、まるでやわらかな毛布に包まれているような安心感がありました。
もちろん、すべてがうまくいくわけではありません。ときには、正直に伝えたことで誤解されたり、距離ができてしまうこともあります。でも、それでも「自分に嘘をつかない」という選択が、私の心を守ってくれるのです。
もし、今のあなたが「自分に正直でいるのは怖い」と感じているなら、どうか少しずつでいいので、自分の気持ちに耳を傾けてみてください。あなたの本音は、きっとあなたをやさしく導いてくれるはずです。自分に正直な生き方は、想像以上に心地よい。私は、そう信じています。
第16章のまとめ
この章では、「わたしが選んだ生き方」について、私自身の経験や感じたことをお話ししてきました。自分の「好き」を中心に選ぶ暮らし、小さくても幸せを感じる仕事、合わない場所に無理に馴染まないこと、気を遣わない関係がいちばん長続きすること。そして、忙しいより心が満たされる選択をすること、変わらないままでできることが増えていくこと、自分に正直な生き方が想像以上に心地よいこと。
どれも、私が「自分らしく生きる」ために大切にしてきたことです。無理に変わろうとせず、ありのままの自分を受け入れる。そんな毎日が、少しずつ私の心をやわらかくしてくれました。
もし、今のあなたが「どう生きたらいいのか分からない」と悩んでいるなら、どうか自分の心の声に耳を傾けてみてください。あなたの「好き」や「心地よさ」が、きっとあなたをやさしく導いてくれるはずです。どんな小さな一歩でも大丈夫。あなたらしい生き方を、少しずつ見つけていけますように。
この章が、あなたの心にそっと寄り添うことができたなら、とても嬉しいです。
第17章:わたしと同じ誰かのために
昔の自分に手紙を書くような気持ちで
もし今、過去の私に手紙を書けるとしたら、どんな言葉を贈るでしょうか。中学時代の教室の片隅で、友達の笑い声を遠くに感じながら、ノートの端に落書きをしていたあの少女に。就職したての頃、トイレの個室で涙をこらえていた二十代の私に。きっと、こんなふうに綴るのだと思います。
「大丈夫だよ。あなたは弱くない。今は辛いかもしれないけど、この繊細な心が、いつか誰かを優しく包む力になるから」。そう伝えたい。過去の私がどれだけ自分を責めていたか、どれだけ「普通になりたい」と願っていたか、よく知っているからです。
先日、古い日記を読み返していて、胸が痛くなりました。二十歳の私が書いた「どうして私はこんなに傷つきやすいんだろう。もっと鈍感になりたい」という言葉。今の私は、その言葉の横にそっと「あなたの感受性は宝物だよ」と書き添えました。まるで、過去の自分に手紙を返すように。
私たちはみんな、過去の自分にメッセージを送ることができるのだと思います。今この瞬間、苦しんでいる誰かに寄り添うように。公園のベンチで俯いている見知らぬ人に、「大丈夫?」と声をかけるように。この文章を書いている今も、私は過去の自分や、同じように悩んでいるあなたに、そっと手を差し伸べたいと思っています。
あなたが感じすぎるのは、弱さじゃない
「感じすぎるのは、弱さじゃない」。この言葉を、どうか胸に刻んでください。敏感で、傷つきやすく、すぐに涙が出てしまう。そんな自分を責めていた日々が、私にもありました。でもある日、図書館で偶然手に取った詩集の一節が心に刺さりました。「繊細な心は、世界を深く泳ぐための鰭(ひれ)だ」。
あなたの感じる力は、弱点ではなく、深く生きるための才能です。誰よりも早く悲しみに気づき、誰よりも細やかな喜びを味わえる。それは、まっすぐで優しい心の証しです。たとえば、道端に咲いたたんぽぽの綿毛が風に揺れる様子に胸を打たれる瞬間。子供の無邪気な笑い声に、ふと懐かしさが込み上げる瞬間。そんな些細な感動を抱きしめられるのは、あなたの強さです。
感じすぎて苦しくなったときは、どうか自分にこう言ってあげてください。「よく感じるね、ありがとう」と。あなたの感受性が、世界を少しずつ優しい場所に変えていくのですから。
“気にしすぎ”はやさしさのかたち
「気にしすぎ」と自分を責める前に、どうか思い出してください。それはあなたの優しさが形になったものなのだと。友達のため息に気づいて声をかけるのは、あなたの優しさ。仕事のミスを何度も反省するのは、責任感の強さ。LINEの既読がつかないことに不安を感じるのは、相手を大切に思っているから。
電車で席を譲るべきか悩んでしまうのも、道に迷っている人に声をかけるか逡巡するのも、全部あなたの優しさの表れです。確かに、それが時として自分を苦しめることもあるでしょう。でも、その優しさが誰かを救う瞬間もあるのです。
先月、駅のホームで涙をこらえていた女性に、勇気を出してティッシュを渡したことがあります。後日、偶然再会したときに「あのとき本当に助かりました」と言われて、ハッとしました。私の「気にしすぎる性格」が、誰かの支えになっていたのです。
あなたの「気にしすぎ」は、きっと誰かの心にそっと灯る蝋燭のような存在。どうか、それを否定しないでください。やがてその優しさが、あなた自身をも照らす日が来ますように。
心の痛みに気づけるあなたがすごい
心の痛みに気づけることは、実はとても尊い能力です。まるで、ほんの小さな擦り傷にも気づける敏感な肌のように。あなたは、自分や他人の心の変化を、誰よりも早く察知できるレーダーを持っているのです。
先日、スーパーのレジで、お釣りを受け取る手が震えていたおばあさんに気づきました。声をかけると、認知症のご主人の介護で疲れていると打ち明けてくれました。後日「あなたが気づいてくれたおかげで、少し楽になりました」と言われたとき、ハッとしました。私の「過剰」だと思っていた感受性が、誰かを支える力になったのです。
心の痛みに気づく力は、世界を優しくする種のようなもの。あなたが感じる痛みは、決して無駄ではありません。どうか、その感受性を恥じないでください。あなたの気づく力が、きっと誰かの暗闇に灯りをともす日が来ます。
世界はまだ、優しさを必要としている
雨の日のコンビニで、傘を持たないお年寄りに自分の傘を差し出した学生を見かけました。お年寄りは「いいよ、大丈夫だから」と遠慮していましたが、学生は「明日返してくれればいいです」と笑顔で傘を手渡していました。その瞬間、傘の縁から零れる雨粒が虹色に光って見えたような気がしました。世界は確かに、こんな小さな優しさを待ち望んでいるのだと。
先日、駅のホームで迷子になった子供が泣いているのを見たことがあります。駆け寄った数人の通行人が、まるで自然な流れのようにその子を囲み、優しい声をかけ始めました。スマートフォンで駅員を呼ぶ人、お菓子を渡す人、手を握って安心させる人。その光景を見ていて、ふと気づいたのです。私たちの社会は、敏感で気づく力のある人たちの優しさで支えられているのだと。
あなたの感じる力は、世界がまだ失っていない希望の証しです。スーパーのレジで「大丈夫ですか?」と声をかける店員さん、電車で席を譲り合う人たち、SNSで見知らぬ人の悩みに寄り添うコメント。どれも、あなたのような気づく力を持つ人たちが紡いでいる優しさの糸です。
大きなニュースにならない日常の小さな優しさが、実は社会の接着剤になっています。あなたが誰かにかける「大丈夫?」というひと言が、その人の一日を救うことがあります。感じすぎるからこそ気づける、誰かの心のSOSに手を差し伸べることは、紛れもなく尊い行為です。
世界は今、あなたのような感受性を必要としています。傷つきやすいからこそ分かる痛み、敏感だからこそ気づける悲しみ。それらを優しさに変換する力が、きっと誰かを救うのです。どうか、自分の感受性を閉じ込めないでください。あなたの優しさが、明日の世界を少しだけ柔らかくするのですから。
あなたのままで、大丈夫
「そのままでいい」。この言葉を、どれほどの人が胸に刻めるでしょうか。私自身、30歳の誕生日に友人から贈られた手紙にこの言葉が書かれていて、泣きそうになったのを覚えています。当時は「もっとこうあるべき」と自分を追い詰めていた時期でしたが、その手紙の最後に書かれた「今のあなたが一番素敵だよ」の一言が、肩の力をふっと抜かせてくれました。
近所のカフェで働くバリスタの青年が、お客さんに「今日のコーヒー、ちょっと苦めですけど大丈夫ですか?」と確認しているのを耳にしたことがあります。お客さんは「あなたの丁寧さが好きなの」と笑顔で答えていました。完璧ではなくても、そのままの姿を受け入れられる関係が、そこにありました。
あなたが誰かの期待に応えようと無理をする必要はありません。朝起きるのが辛い日は、布団の中で星の形のシワができるまでぐずぐずしていていい。人混みが苦手なら、無理してイベントに参加しなくていい。あなたの「そのまま」が、誰かを安心させることもあるのです。
先月、五年ぶりに同窓会に出席しました。当時「変わってないね」と言われるのが怖くて避けていましたが、実際に会ってみると「あなたらしいままでいいんだよ」と言われたのです。そのとき、ドレスに付けたブローチの輝きが、なぜかいつもより鮮やかに見えました。
あなたのままでいい。この言葉を、どうか魔法の呪文のように唱えてみてください。朝、鏡を見るたびに。夜、布団に入る前に。小さな声でいいから、「そのままで大丈夫」と自分に囁いてみる。きっと、心の奥から温かなものが湧き上がってくるはずです。
あなたの物語が、あなたを救ってくれる
日記のページをめくると、三年前の私が「今日もまた泣いてしまった。どうして私は弱いんだろう」と書いていました。その横に、今の私は青いペンで「よく頑張ったね。あの涙が今の私を作ってくれた」と書き加えました。自分の物語を読み返すことで、過去の私が今の私を励ましてくれるような気がするのです。
近所の公園で、毎朝ベンチに座ってノートに書き込んでいる女性を見かけます。ある日、風でページがめくれた瞬間、「生きててよかった」という文字が目に入りました。後で話を聞くと、彼女はうつ病を克服するために毎日自分の気持ちを書き留めているとのこと。「文字にすることで、自分が自分を救っている気がする」と教えてくれました。
あなたの物語は、あなただけの宝物です。誰にも理解されないと思ったあの日の涙も、一人で抱え込んだ不安も、全部ひっくるめてあなたの歴史です。それを否定する必要はありません。むしろ、その物語こそが、あなたを支える杖になるのです。
先週、古い手帳を整理していたら、五年前のメモが落ちてきました。「今日、上司に怒られた。でも、本当は違う方法があったかもしれない」。その横に、現在の私は赤いスタンプで「よく耐えた! 今の私はあの日に感謝してる」と押しました。過去の自分との対話が、不思議と現在を軽やかにしてくれるのです。
もし今、あなたが苦しんでいるなら、ぜひ自分の物語を紡いでみてください。ノートでもスマホのメモでも、夜空に向かっての囁きでもいい。あなたの言葉が、あなた自身を優しく包み込んでくれる日が来ます。そしてその物語が、いつか誰かの灯りになるかもしれません。
第17章のまとめ
この章では、同じように繊細な心を抱えるあなたへのメッセージを綴ってきました。過去の自分に手紙を書くような気持ちで、感じすぎることを弱点ではなく優しさの証として、心の痛みに気づける能力を誇りに思ってほしい。世界がまだ優しさを必要としていること、あなたのままで大丈夫なこと、そしてあなた自身の物語が救いになることを。
私たちの感受性は、時に重荷に感じるかもしれません。でもそれは、暗闇の中でほんの少しの光を捉える望遠鏡のようなもの。あなたが感じる痛みも喜びも、全てが意味のあるものです。どうか、自分を責めるのをやめて、そのままでいる勇気を持ってください。
最後に、ある詩の一節を贈ります。「繊細な魂は/静かな革命を起こす/涙で大地を潤し/優しさで世界を紡ぐ」。あなたの存在そのものが、もうすでに美しい物語なのです。どうか、その物語を大切に育てていってください。
第18章:繊細な心と一緒に生きていく
変わらない部分が、わたしらしさだった
子供の頃から、私はひどく人見知りでした。新しいクラスになじむのにいつも時間がかかり、休み時間は図書室で本を読んでいることが多かったのです。母が心配して「もっと友達と遊んだら?」と言うたびに、胸がぎゅっと締めつけられるような気持ちになっていました。でも今思えば、あのとき本の世界に没頭していた時間が、私の感受性を育んでくれたのかもしれません。
先日、小学校の同窓会で久しぶりに友人に会ったとき、「あなたって本当に変わらないよね」と言われました。最初は傷ついたような気がしたのですが、よく考えてみると、それは私の核になる部分がずっと保たれている証拠なのだと気づきました。人混みが苦手なこと、小さな変化に敏感なこと、誰かの悲しみに共感しすぎてしまうこと。それらは確かに昔から変わらない部分ですが、今ではそれらが私らしさの源泉だと感じられるようになりました。
この数年で、私はたくさんのことを変えようとしました。早起きを習慣にしたり、社交の場に積極的に参加したり。でも、本当に大切なのは変わらない部分を受け入れることだったのです。毎朝コーヒーカップを両手で包み込むように持つ癖、雨の日には必ず窓辺でぼんやり過ごす時間、他人のちょっとした親切に胸が熱くなる瞬間。そんな「変わらない私」の断片が、日々の安心感を紡いでくれるのです。
「このまま」で進んでいく覚悟
「変わらなければ」という焦りは、長い間私の心を縛りつけていました。30歳を目前にしたある夜、鏡を見ながら「このままで大人になれるのか」と不安でたまらなくなったことがあります。でも翌朝、窓から差し込む朝日がふと教えてくれました。変わる必要なんてない、と。ただ「このまま」で進めばいいんだ、と。
最近、職場で後輩から相談を受ける機会が増えました。私の繊細さを「洞察力」と呼んでくれるのです。ミーティングで誰も気づかなかったチームメンバーの疲れに最初に気づいたり、クライアントの本音をくみ取った提案ができたり。それはすべて、私が「このまま」でいたからこそできることでした。
「このまま」で進む覚悟とは、自分を否定しない勇気です。満員電車が苦手なら早めの便を使えばいいし、人付き合いが疲れるなら無理に付き合わなくていい。自分らしいペースで歩いていくことで、道の両側に咲く花に気づけるようになりました。急がなくていい、競わなくていい。ただ、自分の呼吸に合わせて一歩ずつ進めばいいのです。
繊細さは、日々を豊かに彩る力
朝の散歩道で、たんぽぽの綿毛が風に乗って飛んでいく様子を見つめていたら、突然子供の頃の記憶がよみがえりました。同じようにしゃがみ込んで綿毛を追いかけ、制服のスカートを汚して母に叱られたあの日。繊細さは、そんな儚い瞬間を宝石箱にしまう力です。スーパーのレジで店員さんが疲れた顔をしたら、そっと「お疲れさまです」と伝える。通勤中に見かけた猫のひげの動きに思わず微笑む。そんなささやかな瞬間の積み重ねが、私の日常をきらきらと輝かせてくれます。
先月、友人と海辺を歩いていたときのことです。彼女が「波の音ってうるさいね」と言うのに、私は「貝殻が転がる音がオーケストラみたい」と答えていました。後でその話をしたら、「あなたの感性って素敵」と言われたのです。繊細さはフィルターのようなもの。同じ世界を見ても、より鮮やかに、より深く感じることができる。それは紛れもない才能なのです。
誰かに優しくできる“余白”を持てた
自分を受け入れるようになってから、不思議と他人に優しくできる余裕が生まれました。以前は自分をいっぱいいっぱいにして他人まで気が回らなかったのに、今ではスーパーのレジで困っているお年寄りに自然に声をかけられます。心に余白ができた分、世界が広がったような気がします。
先週、駅のホームで泣いている女性を見かけました。以前の私なら「余計なお世話かな」と通り過ぎていたでしょう。でもその日は、そっとティッシュを差し出したのです。彼女は驚いた顔からふっと笑みを浮かべ、「実は今日、大切な人を送るんですか?」と尋ねたら、卒業式で娘と別れる母親だとわかりました。ほんの10分のおしゃべりが、お互いの心を温かくしてくれたのです。
繊細な心は、時として重荷に感じます。でもその感度の高さが、誰かのSOSをキャッチするアンテナにもなるのです。自分を大切にした分だけ、他人にも優しくなれる。そんな循環が生まれるとき、私たちの繊細さは社会の優しさを育む種になるのだと思います。
これからも、揺れながら生きていく
人生は海のようなものだと、最近つくづく思います。穏やかな日もあれば、突然嵐が来る日もある。波が押し寄せては引き、また押し寄せる。私の心も、いつも同じリズムで揺れているような気がします。繊細な気質を持っているからこそ、その揺れは人一倍大きく感じるのかもしれません。でも、揺れること自体が悪いことじゃないんだと、少しずつ学び始めました。
先月、久しぶりに海辺を訪れたときのことを思い出します。砂浜に座って波の音を聞いていると、遠くから大きな波が近づいてきました。最初は「ああ、この波に飲み込まれたらどうしよう」と怖くなったのですが、実際に足元に届くと、それは優しく砂を撫でるように引いていったのです。そのとき、ふと気づきました。揺れても、流されない強さが私にはあるんだと。
日常生活でも、同じようなことがあります。仕事でミスをした日、人間関係で傷ついた日、自分を責めてしまった夜。そんなときは、まるで波に揉まれているような感覚に襲われます。でも、翌朝窓から差し込む朝日を見ると、「また一日、始まるんだ」と自然に体が動き出します。揺れながらも、前に進む力が、きっと誰にでも備わっているのでしょう。
これからも、完全に平静でいられる日は来ないかもしれません。繊細な心を持っている限り、ちょっとした風にも葉っぱが揺れるように、敏感に反応してしまうでしょう。でも、それでいいのです。揺れることでしか感じられない風の温もりも、波の音の儚さも、全部ひっくるめて私の人生なのですから。
今日も自分を労わる一歩を
朝、目覚めたらまず窓を開けることにしています。新鮮な空気が部屋に流れ込むと、昨日の疲れが少しずつ洗い流されていくような気がするからです。カーテンの隙間から差し込む光の角度で、季節の移り変わりを感じるのも好きです。こんな小さな習慣が、私にとっては大切なセルフケアになっています。
先週、仕事で大きなプロジェクトが終わった日のことです。達成感よりもまず襲ってきたのは、どっと疲れが出たことでした。そんなとき、私はいつも近所の銭湯に行きます。湯船にゆっくり浸かりながら、天井の木目をぼんやり眺める。湯気の中で、自分がとても小さな存在に思えて、なぜかほっとするのです。帰り道に買うアイスクリームの甘さが、いつもより格別に感じられました。
自分を労わる方法は、人それぞれ違うと思います。友人は毎晩、手帳に「今日のよかったこと」を3つ書くそうです。別の友人は、月に一度だけ「何もしない日」を作ると言っていました。私の場合は、古いレコード屋さんで気に入ったジャケットを見つけると、なぜか心が落ち着きます。レコードプレーヤーの針が盤面に触れる「パチン」という音が、私の心のスイッチを切り替えてくれるのです。
大切なのは、無理に誰かと同じ方法を真似しないこと。あなただけの「ほっとする瞬間」を、少しずつ見つけていけばいいのです。今日は窓辺で10分だけ太陽の光を浴びる。明日は散歩道で見つけた四つ葉のクローバーをポケットに入れておく。そんな小さな一歩が、積み重なって心の支えになります。
読んでくれたあなたに、ありがとう
この文章をここまで読んでくださったあなたへ。本当に、ありがとうございます。きっとあなたも、人一倍敏感で、時に生きづらさを感じながらも、前を向いて歩いていらっしゃるのでしょう。この物語が、ほんの少しでもあなたの心の杖になれたら、こんなに嬉しいことはありません。
先日、夜遅くにコンビニでコーヒーを買っていたときのことです。レジで「大丈夫ですか? 疲れてないですか?」と店員さんに声をかけられました。その優しさに、なぜか涙がこぼれそうになりながらも、「大丈夫です、ありがとう」と答えられました。あなたがこの文章を読んでくれているその優しさも、きっと誰かの心に届いているはずです。
もしもこの物語が、あなたの中で小さな灯りをともせたなら。それがたとえ蝋燭の炎のようにかすかな光でも、どうか大切に育ててください。やがてその光が、あなた自身を照らし、時には他の誰かを導く道標になる日が来るかもしれません。
最後に、私がいつも心に留めている言葉を贈ります。「繊細であることは、静かな革命だ」。あなたが感じるすべてのことが、世界を少しずつ優しい場所に変えていくのです。どうか、自分を信じて歩み続けてください。あなたの物語は、まだまだ続いていきます。
第18章のまとめ
この最終章では、繊細な心と共に生きる日々の本当の豊かさについて綴ってきました。揺れながらも前に進むことの大切さ、自分を労わる小さな習慣の積み重ね、そして読者のあなたへの感謝の気持ち。どれも、自分を受け入れることで見えてきた景色です。
ある雨の午後、窓辺で雨粒がガラスを伝うのを見ていたときのことを思い出します。一粒のしずくが分裂したり、合流したりしながら、複雑な軌跡を描いていました。私たちの人生もきっと、そんなしずくの軌跡のようなもの。予測不能な道のりでも、最後には必ず大地に還るように、自分らしい終着点にたどり着けると信じています。
繊細な心は、時に重荷に感じるかもしれません。でもそれは、世界を深く味わうための特別なレンズでもあります。どうかそのレンズを曇らせないでください。ときどき息を吹きかけて曇りを払い、そしてときにはレンズ越しに見える世界の美しさに驚いてください。
この物語が終わっても、あなたの日常は続いていきます。朝起きて、深呼吸して、今日という日を歩いていく。その一歩一歩が、あなただけの物語を紡いでいきます。どうか、その物語を愛おしむように、自分自身を大切にしてください。
最後までお付き合いいただき、本当にありがとうございました。あなたの心に、そっと寄り添うことができたなら幸いです。
おわりに
私のこの物語は、決して特別なものではありません。どこにでもいる、ちょっと気にしすぎてしまう誰かの、静かな日常のひとコマです。けれど、こうして言葉にしてみると、不思議と胸の奥が温かくなります。まるで、長い間しまい込んでいたお気に入りのマフラーを、久しぶりに首に巻いたときのような心地よさ。誰かにそっと寄り添ってもらえたような、そんな安心感が、今の私の中にふんわりと広がっています。
昔の私は、気にしすぎる自分をずっと責めていました。どうしてこんなに小さなことが気になるんだろう。どうしてみんなみたいに、もっと気楽に生きられないんだろう。自分の繊細さが、まるで重たい荷物のように感じていた日々もありました。だけど、こうして少しずつ自分と向き合いながら、たくさんの涙や戸惑いを経て、今は「このままでもいいのかもしれない」と思えるようになりました。
繊細な心は、ときに生きづらさを連れてきます。人の顔色や言葉の端々に、必要以上に心が揺れてしまうこともあります。夜、布団の中であれこれ考えすぎて眠れなくなる日も、いまだにゼロにはなりません。でも、そのたびに思うのです。ああ、私は今日もちゃんと感じて、ちゃんと悩んで、ちゃんと生きているんだな、と。
もし、今この文章を読んでいるあなたが、「私も同じ」と少しでも感じてくれたなら、それだけで私はとても嬉しいです。あなたの気にしすぎる心も、あなたの優しさも、全部そのままで大丈夫です。無理に変わろうとしなくていいし、誰かと比べて落ち込む必要もありません。あなたの繊細さは、あなたにしかない大切な宝物です。時には重たく感じるかもしれませんが、きっとそれは、あなたの世界を豊かに彩る力でもあるのです。
これからも、きっといろんなことがあると思います。嬉しいことも、悲しいことも、どうしようもなく心がざわつく日も。でも、そんなときは、どうか自分を責めないでください。あなたの心が疲れたときは、そっと自分を抱きしめてあげてほしいのです。誰かの優しさに触れたときのように、自分にも優しくしてあげてください。ゆっくり深呼吸をして、「今日もよく頑張ったね」と声をかけてあげてください。
私も、これからもきっと揺れながら生きていきます。完璧じゃなくていいし、強くなくてもいい。気にしすぎる自分も、泣き虫な自分も、全部ひっくるめて「私」です。そんな自分と、これからも仲良く暮らしていこうと思います。
最後まで読んでくださって、本当にありがとうございました。あなたの毎日が、どうか少しでもあたたかく、やさしいものでありますように。あなたの繊細な心が、これからもあなたらしく、自由に羽ばたけますように。私の物語が、あなたの心のどこかにそっと寄り添えたなら、それ以上の幸せはありません。
また、どこかで。
Kindle紹介文(商品ページ用)
繊細な心と一緒に生きることにした
〜「気にしすぎる自分」と仲直りする物語〜
「LINEの既読がつかないだけで、ずっと気にしてしまう」
「人と話した後、あの一言まずかったかな…と寝る前まで反省会」
「他人の顔色が気になりすぎて、自分の気持ちがわからなくなる」
そんな“気にしすぎる自分”に、心が疲れていませんか?
この本は、HSP(Highly Sensitive Person)としての気質を持つ著者が、自分との関係を少しずつ、やさしく整えていった記録です。
💭 こんなあなたに届けたい
- なんでこんなに傷つきやすいの?と悩んでいる人
- 自分の感情がコントロールできなくてつらい人
- 気にしすぎる性格を「直す」のではなく、「受け入れたい」と思っている人
- 同じ気持ちの誰かの体験談を読んで、安心したい人
- 韓国エッセイのような、やさしくて読みやすい文章に癒されたい人
📖 本の内容(全18章構成)
HSPという言葉に出会って救われたこと、
仕事や人間関係で心が折れそうになった日々、
感情に飲み込まれて苦しかった経験、
そして、少しずつ「気にしすぎる自分」と仲直りしていった道のり──。
ひとり時間の大切さ、安心できる人との出会い、自分との境界線を取り戻すこと、
そんな“小さな発見”をやさしく綴ったエピソード集です。
🌼 読後に得られるもの
- 「こんなふうに感じるのは、自分だけじゃなかった」と思える安心感
- 無理に変わらなくても、穏やかに生きていけるという希望
- 誰かと比べずに、「わたしはわたし」でいいという小さな肯定
- 心が疲れたときに、そっと読み返したくなる一冊
気にしすぎるのは、弱さじゃない。
それは、やさしさや思いやりの裏返しかもしれません。
この本を通して、あなたの“繊細な心”と、少しでも仲良くなれますように
✍️ 著者プロフィール(Kindle著者欄用)
著者:はるか(仮名・女性)
1980年代生まれ。二児の母。
昔から「気にしすぎ」と言われることが多く、自分を責めがちな性格に悩んできました。
出産・育児を経て、HSPという言葉と出会い、「繊細な心」は直すものではなく、一緒に生きていくものだと気づきます。
自分の気持ちをうまく言葉にできなかった頃の私に届けるようなつもりで、エッセイを書いています。
現在は、静かな暮らしを大切にしながら、日々の小さな発見や気づきを文章にして発信中。
好きなものは、空の色、静かなカフェ、お気に入りの紅茶と文房具。