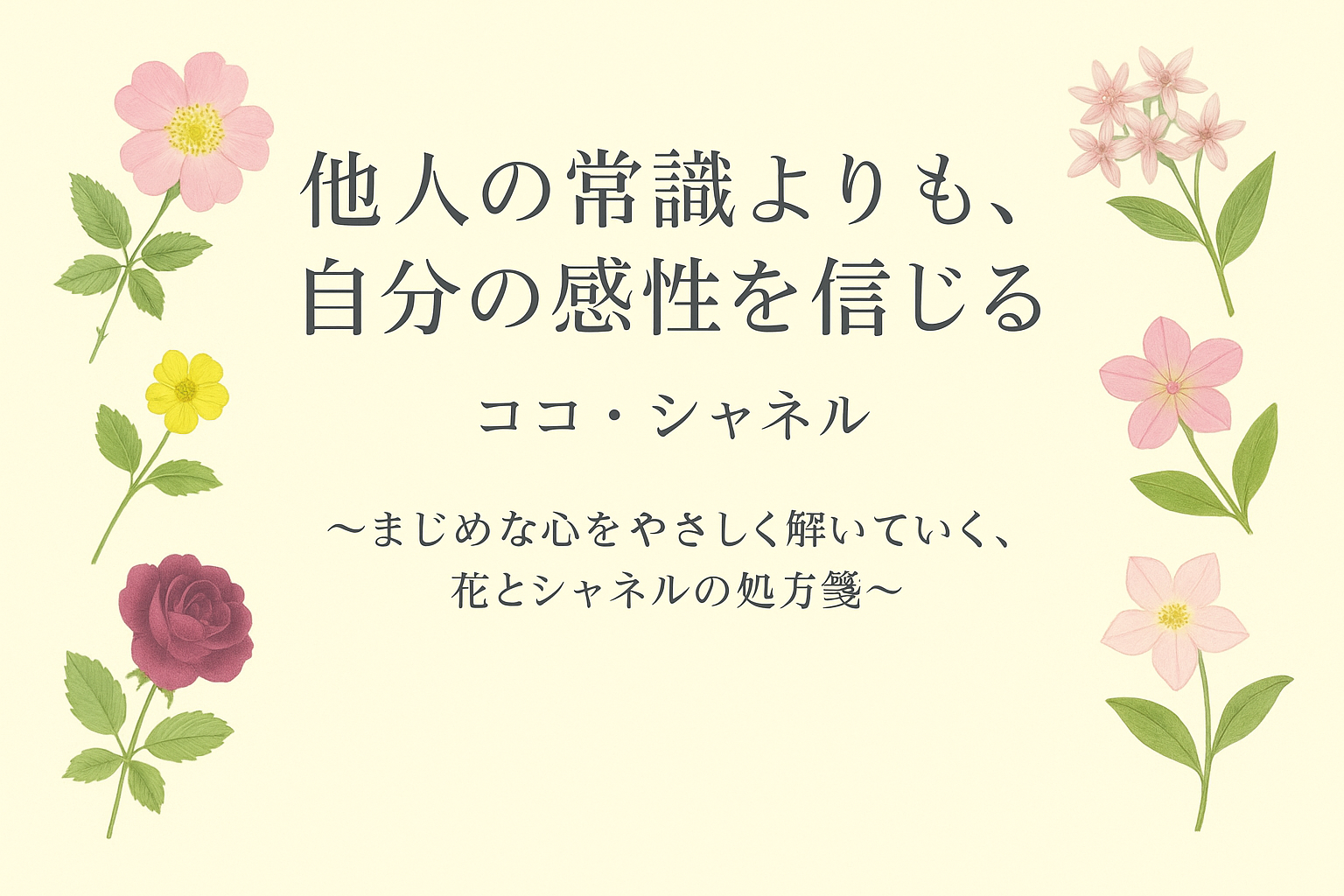贅沢をしていない人たちが、静かに困っている社会
東京都では、2025年に最低賃金が時給1,226円に引き上げられました。
一見、朗報に思えるこの数値ですが、実際にこの時給でフルタイム(1日8時間×月22日程度)働いている方の手取り月収は下記のものが差し引かれることによっておよそ15万3千円前後にとどまります。
給与から差し引かれる主なものは
-
健康保険料
-
厚生年金保険料
-
雇用保険料
-
所得税(源泉徴収)
-
住民税
これらの合計控除率は、収入水準・扶養家族の有無・地域などによって変動しますが、20〜30%程度を見込むことがよくあります(通信・家計系サイトの手取り早見表でもその程度の控除を仮定しているものが多い)。たとえば、月給22万円の場合、控除後の手取りを「22万円 × 0.75~0.85」あたりになるものとして計算してみました。
いま、この手取り額で生活している多くの人たちが、こう感じ始めています。
「頑張って働いているのに、何も贅沢をしていないのに、生活が苦しいのはなぜ?」
節約は、すでに“限界まで”している
- 食費は自炊中心、冷凍野菜や特売品を活用
- 洋服はファストファッションかリユースショップ
- 外食や旅行は、ここ何年もしていない
- 通信費も格安SIMに変更し、サブスクは1つか2つに厳選
- エアコンや暖房も、光熱費が気になってなるべく我慢
これらは“特別に節約している人の特徴”ではなく、今や多くの人が当たり前に行っている日常の工夫です。
それでも、月末が近づくと生活必需品(洗剤、シャンプー、靴下、通勤用の傘など)を買うことさえためらうという声が増えています。
見えにくい「ぎりぎりの暮らし」
たとえば、都内で月収15万3千円(最低賃金×フルタイムの手取り)を得ている人の最低ラインの生活をシミュレーションしてみると:
- 家賃:60,000円(23区外や築年数の古い物件)
- 食費:25,000円(1日あたり約830円)
- 光熱水費:12,000円(電気・ガス・水道)
- 通信費:1,000円(格安SIM、通話は最低限)
- 通勤・雑費:8,000円
- 医療・日用品・予備費:10,000円
合計:約116,000円
この残額から、急な医療費や冠婚葬祭費、スマホの故障、家電の買い替えなどに備えなければなりません。
これは、「余裕がない」というより、常に薄氷の上に立っているような状態です。
生活保護との比較から見えること
現在、東京都区部で単身者が受けられる生活保護(生活扶助+住宅扶助)は、およそ13〜15万円台が目安です。
一方、最低賃金でフルタイム勤務した場合の手取りは15万3千円前後。
この2つは金額的に大差がないだけでなく、
- 生活保護では医療費が原則無料だが、労働者は3割自己負担
- 働くために昼食代や身だしなみなど追加コストがかかる
- 体力や時間的余裕も削られる
結果として、「働いている人のほうが生活の自由度が低い」という逆転現象すら起きています。
「努力が足りない」という誤解
こうした話をすると、「もっと頑張ればいい」「スキルを身につけて転職すれば?」という意見も返ってきます。
もちろん、自己研鑽やキャリアアップは大切です。
しかし、誰もが同じようにチャンスを得られるわけではありません。
家庭の事情、体調、年齢、過去の経験――それぞれに理由があって、今の働き方にとどまっている人がたくさんいます。
むしろ大切なのは、「働くすべての人が暮らしを安心して送れる社会」ではないでしょうか。
問い直したい、「生活に必要な額とは何か」
「生活に必要な額」とは、ただ飢えず、凍えず、住む場所があればいいということではありません。
- 毎日を不安なく過ごすための、予備費
- 病気のときに無理をしなくていい医療アクセス
- 社会とつながるための通信や交通手段
- 自分自身を整えるための最低限の余裕
これらを含んでこそ、「人間らしい生活」です。
最低賃金は“最低の生活”を意味していいのか?
「働いても生活できない」と感じる人が増えている今、
私たちが見直すべきは。。。
- 最低賃金の水準そのもの
- 公的支援のあり方
- “努力が足りない”とされてしまう空気
ではないでしょうか。
誰もが裕福さを求めているのではなく、ただ安心して暮らしたいだけ。
そのシンプルな願いすら叶いにくい社会は、きっと誰にとっても生きづらいはずです。
行き詰まりと、かすかな展望
この問題には「これだ!」という代案がまだ見当たりません。
労賃より高いからと生活保護を減らすのは本末転倒ですし、最低賃金を急に上げれば今度は「3人でやっていた作業を2人で」という圧縮労働が起きてしまう。
日本は空気も水もきれいで、治安も世界的に見れば良い。宗教が違えど共存できるたぐいまれな社会
それでも、暮らすことを考えると、打開策がなかなか見つからない。
唯一思い浮かぶのは、食料の自給や地域での助け合いといった、生活をお金に依存しすぎない方向への模索
「生きる」ことの基盤を、社会全体で再構築していく必要があるのかもしれません。